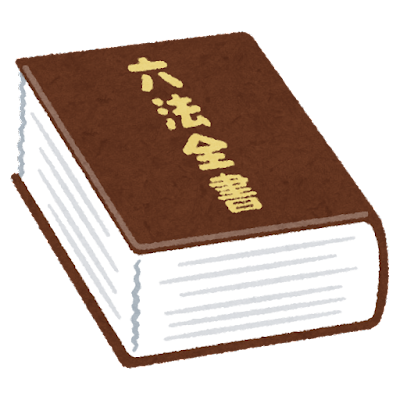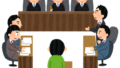第二次世界大戦後、日本は連合国軍最高司令官総司令部(GHQ)の指導のもと、民主化と非軍事化を進めました。日本国憲法が1947年に施行されると同時に、民主主義を支える公正な選挙制度が必要とされました。このため、戦前の選挙法を改正し、現代的な選挙法が制定されました。日本国憲法は主権在民を基礎としており、国民が自由に選挙で代表者を選ぶことが民主政治の根幹となります。公職選挙法は、この憲法の精神を具現化するための法的枠組みを提供しています。
- 公職選挙法 第1条(この法律の目的)
- 公職選挙法 第2条(この法律の適用範囲)
- 公職選挙法 第3条(公職の定義)
- 公職選挙法 第4条(議員の定数)
- 公職選挙法 第5条(選挙事務の管理)
- 公職選挙法 第5条の2(中央選挙管理会)
- 公職選挙法 第5条の3(中央選挙管理会の技術的な助言及び勧告並びに資料の提出の要求)
- 公職選挙法 第5条の4(中央選挙管理会の是正の指示)
- 公職選挙法 第5条の5(中央選挙管理会の処理基準)
- 公職選挙法 第5条の6(参議院合同選挙区選挙管理委員会)
- 公職選挙法 第5条の7(参議院合同選挙区選挙管理委員会の技術的な助言及び勧告並びに資料の提出の要求)
- 公職選挙法 第5条の8(参議院合同選挙区選挙管理委員会の是正の指示)
- 公職選挙法 第5条の9(参議院合同選挙区選挙管理委員会の処理基準)
- 公職選挙法 第5条の10(合同選挙区都道府県の選挙管理委員会の委員の失職の特例)
- 公職選挙法 第6条(選挙に関する啓発、周知等)
- 公職選挙法 第7条(選挙取締の公正確保)
- 公職選挙法 第8条(特定地域に関する特例)
- 公職選挙法 第19条(永久選挙人名簿)
- 公職選挙法 第20条(選挙人名簿の記載事項等)
- 公職選挙法 第21条(被登録資格等)
- 公職選挙法 第22条(登録)
- 第二十三条は削除されました。 公職選挙法 第24条(異議の申出)
- 公職選挙法 第25条(訴訟)
- 公職選挙法 第26条(補正登録)
- 公職選挙法 第27条(表示及び訂正等)
- 公職選挙法 第28条(登録の抹消)
- 公職選挙法 第28条の2(登録の確認及び政治活動を目的とした選挙人名簿の抄本の閲覧)
- 公職選挙法 第28条の3(政治又は選挙に関する調査研究を目的とした選挙人名簿の抄本の閲覧)
- 公職選挙法 第28条の4(選挙人名簿の抄本の閲覧に係る勧告及び命令等)
- 公職選挙法 第29条(通報及び調査の請求)
- 公職選挙法 第30条(選挙人名簿の再調製)
- 公職選挙法 第30条の2(在外選挙人名簿)
- 公職選挙法 第30条の3(在外選挙人名簿の記載事項等)
- 公職選挙法 第30条の4(在外選挙人名簿の被登録資格等)
- 公職選挙法 第30条の5(在外選挙人名簿の登録の申請等)
- 公職選挙法 第30条の6(在外選挙人名簿の登録等)
- 第三十条の七 削除
- 公職選挙法 第30条の8(在外選挙人名簿の登録等に関する異議の申出)
- 公職選挙法 第30条の9(在外選挙人名簿の登録等に関する訴訟)
- 公職選挙法 第30条の10(在外選挙人名簿の表示及び訂正等)
- 公職選挙法 第30条の11(在外選挙人名簿の登録の抹消)
- 公職選挙法 第30条の12(在外選挙人名簿の抄本の閲覧等)
- 公職選挙法 第30条の13(在外選挙人名簿の修正等に関する通知等)
- 公職選挙法 第30条の14(在外選挙人証交付記録簿の閲覧)
- 公職選挙法 第30条の15(在外選挙人名簿の再調製)
- 公職選挙法 第30条の16(在外選挙人名簿の登録等に関する政令への委任)
- 公職選挙法 第35条(選挙の方法)
- 公職選挙法 第36条(一人一票)
- 公職選挙法 第37条(投票管理者)
- 公職選挙法 第38条(投票立会人)
- 公職選挙法 第39条(投票所)
- 公職選挙法 第40条(投票所の開閉時間)
- 公職選挙法 第41条(投票所の告示)
- 公職選挙法 第41条の2(共通投票所)
- 公職選挙法 第42条(選挙人名簿又は在外選挙人名簿の登録と投票)
- 公職選挙法 第43条(選挙権のない者の投票)
- 公職選挙法 第44条(投票所における投票)
- 公職選挙法 第45条(投票用紙の交付及び様式)
- 公職選挙法 第46条(投票の記載事項及び投函)
- 公職選挙法 第46条の2(記号式投票)
- 公職選挙法 第47条(点字投票)
- 公職選挙法 第48条(代理投票)
- 公職選挙法 第48条の2(期日前投票)
- 公職選挙法 第49条(不在者投票)
- 公職選挙法 第49条の2(在外投票等)
- 公職選挙法 第50条(選挙人の確認及び投票の拒否)
- 公職選挙法 第51条(退出せしめられた者の投票)
- 公職選挙法 第52条(投票の秘密保持)
- 公職選挙法 第53条(投票箱の閉鎖)
- 公職選挙法 第54条(投票録の作成)
- 公職選挙法 第55条(投票箱等の送致)
- 公職選挙法 第56条(繰上投票)
- 公職選挙法 第57条(繰延投票)
- 公職選挙法 第58条(投票所に出入し得る者)
- 公職選挙法 第59条(投票所の秩序保持のための処分の請求)
- 公職選挙法 第60条(投票所における秩序保持)
- 公職選挙法 第61条(開票管理者)
- 公職選挙法 第62条(開票立会人)
- 公職選挙法 第63条(開票所の設置)
- 公職選挙法 第64条(開票の場所及び日時の告示)
- 公職選挙法 第65条(開票日)
- 公職選挙法 第66条(開票)
- 公職選挙法 第67条(開票の場合の投票の効力の決定)
- 公職選挙法 第68条(無効投票)
- 公職選挙法 第六十八条の二(同一氏名の候補者等に対する投票の効力)
- 公職選挙法 第六十八条の三(特定の参議院名簿登載者の有効投票)
- 公職選挙法 第六十九条(開票の参観)
- 公職選挙法 第七十条(開票録の作成)
- 公職選挙法 第七十一条(投票、投票録及び開票録の保存)
- 公職選挙法 第七十二条(一部無効に因る再選挙の開票)
- 公職選挙法 第七十三条(繰延開票)
- 公職選挙法 第七十四条(開票所の取締り)
- 公職選挙法 第七十五条(選挙長及び選挙分会長)
- 公職選挙法 第七十六条(選挙立会人)
- 公職選挙法 第七十七条(選挙会及び選挙分会の開催場所)
- 公職選挙法 第七十八条(選挙会及び選挙分会の場所及び日時)
- 公職選挙法 第七十九条(開票事務と選挙会事務との合同)
- 公職選挙法 第八十条(選挙会又は選挙分会の開催)
- 公職選挙法 第八十一条(衆議院比例代表選出議員若しくは参議院比例代表選出議員の選挙又は参議院合同選挙区選挙の選挙会の開催)
- 公職選挙法 第八十二条(選挙会及び選挙分会の参観)
- 公職選挙法 第八十三条(選挙録の作成及び選挙録その他関係書類の保存)
- 公職選挙法 第八十四条(繰延選挙会又は繰延選挙分会)
- 公職選挙法 第八十五条(選挙会場及び選挙分会場の取締り)
- 公職選挙法 第八十六条(衆議院小選挙区選出議員の選挙における候補者の立候補の届出等)
- 公職選挙法 第八十六条の三(参議院比例代表選出議員の選挙における名簿による立候補の届出等)
- 公職選挙法 第八十六条の四(衆議院議員又は参議院比例代表選出議員の選挙以外の選挙における候補者の立候補の届出等)
- 公職選挙法 第八十六条の五(候補者の選定の手続の届出等)
- 公職選挙法 第八十六条の六(衆議院比例代表選出議員の選挙における政党その他の政治団体の名称の届出等)
- 公職選挙法 第八十六条の七(参議院比例代表選出議員の選挙における政党その他の政治団体の名称の届出等)
- 公職選挙法 第八十六条の八(被選挙権のない者等の立候補の禁止)
- 公職選挙法 第八十七条(重複立候補等の禁止)
- 公職選挙法 第八十七条の二(衆議院小選挙区選出議員又は参議院選挙区選出議員たることを辞した者等の立候補制限)
- 公職選挙法 第八十八条(選挙事務関係者の立候補制限)
- 公職選挙法 第八十九条(公務員の立候補制限)
- 公職選挙法 第九十条(立候補のための公務員の退職)
- 公職選挙法 第九十一条(公務員となつた候補者の取扱い)
- 公職選挙法 第九十二条(供託)
- 公職選挙法 第九十三条(公職の候補者に係る供託物の没収)
- 公職選挙法 第九十四条(名簿届出政党等に係る供託物の没収)
- 公職選挙法 第九十五条(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙以外の選挙における当選人)
- 公職選挙法 第九十五条の二(衆議院比例代表選出議員の選挙における当選人の数及び当選人)
- 公職選挙法 第九十五条の三(参議院比例代表選出議員の選挙における当選人の数及び当選人となるべき順位並びに当選人)
- 公職選挙法 第九十六条(当選人の更正決定)
- 公職選挙法 第九十七条(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙以外の選挙における当選人の繰上補充)
- 公職選挙法 第九十七条の二(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙における当選人の繰上補充)
- 公職選挙法 第九十八条(被選挙権の喪失と当選人の決定等)
- 公職選挙法 第九十九条(被選挙権の喪失に因る当選人の失格)
- 公職選挙法 第九十九条の二(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙における所属政党等の移動による当選人の失格)
- 公職選挙法 第百条(無投票当選)
- 公職選挙法 第百一条(衆議院小選挙区選出議員の選挙における当選人決定の場合の報告、告知及び告示)
- 公職選挙法 第百一条の二(衆議院比例代表選出議員の選挙における当選人の数及び当選人の決定の場合の報告、告知及び告示)
- 公職選挙法 第百一条の二の二(参議院比例代表選出議員の選挙における当選人の数及び当選人となるべき順位並びに当選人の決定の場合の報告、告知及び告示)
- 公職選挙法 第百一条の三(衆議院議員又は参議院比例代表選出議員の選挙以外の選挙における当選人決定の場合の報告、告知及び告示)
- 公職選挙法 第百二条(当選等の効力の発生)
- 公職選挙法 第百三条(当選人が兼職禁止の職にある場合等の特例)
- 公職選挙法 第百四条(請負等をやめない場合の地方公共団体の議会の議員又は長の当選人の失格)
- 公職選挙法 第百五条(当選証書の付与)
- 公職選挙法 第百六条(当選人がない場合等の報告及び告示)
- 公職選挙法 第百七条(選挙及び当選の無効の場合の告示)
- 公職選挙法 第百八条(当選等に関する報告)
- 公職選挙法 第109条(衆議院小選挙区選出議員、参議院選挙区選出議員又は地方公共団体の長の再選挙)
- 公職選挙法 第110条(衆議院比例代表選出議員、参議院比例代表選出議員又は地方公共団体の議会の議員の再選挙)
- 公職選挙法 第111条(議員又は長の欠けた場合等の通知)
- 公職選挙法 第112条(議員又は長の欠けた場合等の繰上補充)
- 公職選挙法 第113条(補欠選挙及び増員選挙)
- 公職選挙法 第113条 第2項(増員選挙)
- 公職選挙法 第113条 第3項(補欠選挙の同時実施)
- 公職選挙法 第113条 第4項・第5項(補欠選挙の期日と準用)
- 公職選挙法 第114条(長が欠けた場合及び退職の申立てがあつた場合の選挙)
- 公職選挙法 第115条(合併選挙及び在任期間を異にする議員の選挙の場合の当選人)
- 公職選挙法 第115条第2項(在任期間を異にする参議院比例代表選出議員の選挙の合併)
- 公職選挙法 第115条第3項(比例代表選出議員の選挙合併とくじによる当選人の決定)
- 公職選挙法 第115条第4項(比例代表選出議員の名簿順の優先決定)
- 公職選挙法 第115条第5項(在任期間を異にする参議院比例代表選出議員の当選人決定)
- 公職選挙法 第115条第6項(在任期間を異にする参議院選挙区選出議員の当選人決定)
- 公職選挙法 第115条第7項(選挙区選出議員の選挙合併時におけるくじ引きでの当選者決定)
- 公職選挙法 第115条第8項(第100条第9項の準用)
- 公職選挙法 第115条第9項(繰上補充における在任期間の短い議員の当選者決定)
- 公職選挙法 第116条(議員又は当選人がすべてない場合の一般選挙)
- 公職選挙法 第117条(設置選挙)
- 公職選挙法 第118条
- 公職選挙法 第129条(選挙運動の期間)
- 公職選挙法 第130条(選挙事務所の設置及び届出)
- 公職選挙法 第130条第2項(選挙事務所の設置及び届出)
- 公職選挙法 第131条(選挙事務所の数)
- 公職選挙法 第131条第2項(選挙事務所の移動制限)
- 公職選挙法 第131条第3項(選挙事務所の標札掲示)
- 公職選挙法 第132条(選挙当日の選挙事務所の制限)
- 公職選挙法 第133条(休憩所等の禁止)
- 公職選挙法 第134条(選挙事務所の閉鎖命令)
- 公職選挙法 第135条(選挙事務関係者の選挙運動の禁止)
- 公職選挙法 第136条(特定公務員の選挙運動の禁止)
- 公職選挙法 第136条の2(公務員等の地位利用による選挙運動の禁止)
- 公職選挙法 第137条(教育者の地位利用の選挙運動の禁止)
- 公職選挙法 第137条の2(年齢満十八年未満の者の選挙運動の禁止)
- 公職選挙法 第137条の3(選挙権及び被選挙権を有しない者の選挙運動の禁止)
- 公職選挙法 第138条(戸別訪問)
- 公職選挙法 第138条の2(署名運動の禁止)
- 公職選挙法 第138条の3(人気投票の公表の禁止)
- 公職選挙法 第139条(飲食物の提供の禁止)
- 公職選挙法 第140条(気勢を張る行為の禁止)
- 公職選挙法 第140条の2(連呼行為の禁止)
- 公職選挙法 第141条(自動車、船舶及び拡声機の使用)
- 公職選挙法 第141条 第2項(自動車、船舶及び拡声機の追加使用の条件)
- 公職選挙法 第141条 第3項(比例代表選出議員選挙での自動車、船舶及び拡声機の追加使用)
- 公職選挙法 第141条 第4項(比例代表選出議員選挙における自動車、船舶及び拡声機の使用制限)
- 公職選挙法 第141条 第5項(選挙運動のために使用される自動車、船舶及び拡声機の表示)
- 公職選挙法 第141条 第6項(選挙運動に使用される自動車の種類)
- 公職選挙法 第141条 第7項(小選挙区及び比例代表選挙における自動車の無料使用)
- 公職選挙法 第141条 第8項(地方公共団体の議員や長の選挙における自動車の無料使用)
公職選挙法の概要
目的と適用範囲
- 目的:公職選挙法の目的は、公正かつ適正な選挙の実施を確保することです。これにより、選挙人の自由な意思表明が保障され、民主政治の健全な発展が図られます。
- 適用範囲:この法律は、衆議院議員、参議院議員、地方公共団体の議会の議員および長の選挙に適用されます。
公職の定義
- 公職:衆議院議員、参議院議員、地方公共団体の議会の議員および長の職を指します。
議員の定数
- 衆議院議員:定数は465人で、そのうち289人が小選挙区から、176人が比例代表から選出されます。
- 参議院議員:定数は248人で、そのうち100人が比例代表から、148人が選挙区から選出されます。
- 地方公共団体の議員:定数は地方自治法に基づいて定められます。
選挙事務の管理
- 中央選挙管理会:衆議院(比例代表選出)議員および参議院(比例代表選出)議員の選挙事務を管理します。
- 地方選挙管理委員会:衆議院(小選挙区選出)議員、参議院(選挙区選出)議員、都道府県の議会の議員および知事、市町村の議会の議員および長の選挙事務を管理します。
選挙の公正確保
- 啓発活動:選挙管理機関は、選挙が公正かつ適正に行われるよう、選挙人の政治常識を向上させるための啓発活動を行います。
- 取締り:検察官、公安委員会、警察官は、公正に選挙の取締りを行わなければなりません。
特定地域の特例
- 交通至難地域:交通が不便な地域などにおいては、特別な規定を設けることができます。
公職選挙法 第一章 総則
公職選挙法 第1条(この法律の目的)
原文:
第一条 この法律は、日本国憲法の精神に則り、衆議院議員、参議院議員並びに地方公共団体の議会の議員及び長を公選する選挙制度を確立し、その選挙が選挙人の自由に表明せる意思によつて公明且つ適正に行われることを確保し、もつて民主政治の健全な発達を期することを目的とする。
解説:
公職選挙法 第2条(この法律の適用範囲)
原文:
第二条 この法律は、衆議院議員、参議院議員並びに地方公共団体の議会の議員及び長の選挙について、適用する。
解説:
この法律は、以下の選挙に適用されます:
- 衆議院議員の選挙:日本の国会の下院にあたる衆議院の議員を選ぶための選挙。
- 参議院議員の選挙:日本の国会の上院にあたる参議院の議員を選ぶための選挙。
- 地方公共団体の議会の議員及び長の選挙:都道府県、市町村などの地方自治体の議会の議員および市町村長や都道府県知事を選ぶための選挙。
この法律は、国政選挙と地方選挙の両方に適用されることを規定しています。
公職選挙法 第3条(公職の定義)
原文:
第三条 この法律において「公職」とは、衆議院議員、参議院議員並びに地方公共団体の議会の議員及び長の職をいう。
解説:
- 衆議院議員:日本の国会の下院に所属する議員。
- 参議院議員:日本の国会の上院に所属する議員。
- 地方公共団体の議会の議員:都道府県や市町村などの地方自治体の議会に所属する議員。
- 地方公共団体の長:市町村長や都道府県知事など、地方自治体の行政のトップ。
この定義により、選挙に関する法律の適用対象が明確にされています。
公職選挙法 第4条(議員の定数)
原文:
第四条 衆議院議員の定数は、四百六十五人とし、そのうち、二百八十九人を小選挙区選出議員、百七十六人を比例代表選出議員とする。
2 参議院議員の定数は二百四十八人とし、そのうち、百人を比例代表選出議員、百四十八人を選挙区選出議員とする。
3 地方公共団体の議会の議員の定数は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)の定めるところによる。
解説:
- 衆議院議員:総数は465人で、そのうち289人が小選挙区から、176人が比例代表から選ばれます。小選挙区選出は全国の小選挙区ごとに1人を選びます。比例代表は全国をいくつかのブロックに分けて、政党の得票数に応じて議席を配分します。
- 参議院議員:総数は248人で、そのうち100人が比例代表から、148人が選挙区から選ばれます。参議院の選挙区は都道府県単位で行われます。
- 地方公共団体の議会の議員:定数は地方自治法に基づいて決められます。各地方自治体(都道府県、市町村)の議員数は、その地域の人口や他の要因に応じて決められます。
公職選挙法 第5条(選挙事務の管理)
原文:
第五条 この法律において選挙に関する事務は、特別の定めがある場合を除くほか、衆議院(比例代表選出)議員又は参議院(比例代表選出)議員の選挙については中央選挙管理会が管理し、衆議院(小選挙区選出)議員、参議院(選挙区選出)議員、都道府県の議会の議員又は都道府県知事の選挙については都道府県の選挙管理委員会が管理し、市町村の議会の議員又は市町村長の選挙については市町村の選挙管理委員会が管理する。
解説:
- 中央選挙管理会: 衆議院の比例代表選出議員と参議院の比例代表選出議員の選挙事務を管理します。
- 都道府県の選挙管理委員会: 衆議院の小選挙区選出議員、参議院の選挙区選出議員、都道府県の議会議員および都道府県知事の選挙事務を管理します。
- 市町村の選挙管理委員会: 市町村の議会議員および市町村長の選挙事務を管理します。
これにより、選挙の公正性と適正な運営が確保されます。
公職選挙法 第5条の2(中央選挙管理会)
原文:
第五条の二 中央選挙管理会は、委員五人をもつて組織する。
2 委員は、国会議員以外の者で参議院議員の被選挙権を有する者の中から国会の議決による指名に基いて、内閣総理大臣が任命する。
3 前項の指名に当つては、同一の政党その他の政治団体に属する者が、三人以上とならないようにしなければならない。
4 内閣総理大臣は、委員が次の各号のいずれかに該当するに至つた場合は、その委員を罷免するものとする。ただし、第二号及び第三号の場合においては、国会の同意を得なければならない。
一 参議院議員の被選挙権を有しなくなつた場合
二 心身の故障のため、職務を執行することができない場合
三 職務上の義務に違反し、その他委員たるに適しない非行があつた場合
5 委員のうち同一の政党その他の政治団体に属する者が三人以上となつた場合においては、内閣総理大臣は、くじで定める二人以外の委員を罷免するものとする。
6 国会は、第二項の規定による委員の指名を行う場合においては、同時に委員と同数の予備委員の指名を行わなければならない。予備委員が欠けた場合においては、同時に委員の指名を行うときに限り、予備委員の指名を行う。
7 予備委員は、委員が欠けた場合又は故障のある場合に、その職務を行う。
8 第二項から第五項までの規定は、予備委員について準用する。
9 委員の任期は、三年とする。但し、補欠委員の任期は、その前任者の残任期間とする。
10 前項の規定にかかわらず、委員は、国会の閉会又は衆議院の解散の場合に任期が満了したときは、あらたに委員が、その後最初に召集された国会における指名に基いて任命されるまでの間、なお、在任するものとする。
11 委員は、非常勤とする。
12 委員長は、委員の中から互選しなければならない。
13 委員長は、中央選挙管理会を代表し、その事務を総理する。
14 中央選挙管理会の会議は、その委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
15 中央選挙管理会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。
16 中央選挙管理会の庶務は、総務省において行う。
17 前各項に定めるものの外、中央選挙管理会の運営に関し必要な事項は、中央選挙管理会が定める。
解説:
- 委員の構成: 国会議員以外の者で参議院議員の被選挙権を持つ者の中から選ばれます。内閣総理大臣が国会の指名に基づいて任命し、同じ政党の者が3人以上にならないようにします。
- 委員の解任: 委員が参議院議員の被選挙権を失った場合や心身の故障で職務ができなくなった場合、または職務上の義務に違反した場合、内閣総理大臣が解任します。特定の理由では国会の同意が必要です。
- 予備委員の指名: 委員と同数の予備委員が指名され、委員が欠けた場合や故障がある場合にその職務を代行します。
- 委員の任期: 委員の任期は3年で、補欠委員の任期は前任者の残りの期間です。国会の閉会や衆議院の解散時には、次の国会が召集されるまで在任します。
- 委員長の選出: 委員長は委員の中から選ばれ、会議の代表と事務の総理を務めます。会議は半数以上の出席で成立し、議事は出席委員の過半数で決定します。
- 庶務: 中央選挙管理会の庶務は総務省が担当し、その他の運営に関する事項は中央選挙管理会が定めます。
公職選挙法 第5条の3(中央選挙管理会の技術的な助言及び勧告並びに資料の提出の要求)
原文:
第五条の三 中央選挙管理会は、衆議院(比例代表選出)議員又は参議院(比例代表選出)議員の選挙に関する事務について、都道府県又は市町村に対し、都道府県又は市町村の事務の運営その他の事項について適切と認める技術的な助言若しくは勧告をし、又は当該助言若しくは勧告をするため若しくは都道府県又は市町村の事務の適正な処理に関する情報を提供するため必要な資料の提出を求めることができる。
2 中央選挙管理会は、衆議院(比例代表選出)議員又は参議院(比例代表選出)議員の選挙に関する事務について、都道府県の選挙管理委員会に対し、地方自治法第二百四十五条の四第一項の規定による市町村に対する助言若しくは勧告又は資料の提出の求めに関し、必要な指示をすることができる。
3 都道府県又は市町村の選挙管理委員会は、中央選挙管理会に対し、衆議院(比例代表選出)議員又は参議院(比例代表選出)議員の選挙に関する事務の管理及び執行について技術的な助言若しくは勧告又は必要な情報の提供を求めることができる。
解説:
- 都道府県や市町村への技術的助言や勧告: 衆議院や参議院の比例代表選挙に関する事務について、必要に応じて技術的なアドバイスや改善のための勧告を行います。
- 資料の提出要求: 助言や勧告を行うために必要な情報を都道府県や市町村から提出してもらうことができます。
- 指示の発行: 中央選挙管理会は都道府県の選挙管理委員会に対して、市町村が選挙事務を適切に処理するように指示を出すことができます。
- 情報提供の要求: 都道府県や市町村の選挙管理委員会は、中央選挙管理会に対して選挙事務の管理や執行について助言や情報提供を求めることができます。
公職選挙法 第5条の4(中央選挙管理会の是正の指示)
原文:
第五条の四 中央選挙管理会は、この法律又はこの法律に基づく政令に係る都道府県の地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙に関する事務に限る。以下この条及び次条において「第一号法定受託事務」という。)の処理が法令の規定に違反していると認めるとき、又は著しく適正を欠き、かつ、明らかに公益を害していると認めるときは、当該都道府県に対し、当該第一号法定受託事務の処理について違反の是正又は改善のため講ずべき措置に関し、必要な指示をすることができる。
2 中央選挙管理会は、この法律又はこの法律に基づく政令に係る市町村の第一号法定受託事務の処理について、都道府県の選挙管理委員会に対し、地方自治法第二百四十五条の七第二項の規定による市町村に対する指示に関し、必要な指示をすることができる。
3 中央選挙管理会は、前項の規定によるほか、この法律又はこの法律に基づく政令に係る市町村の第一号法定受託事務の処理が法令の規定に違反していると認める場合、又は著しく適正を欠き、かつ、明らかに公益を害していると認める場合において、緊急を要するときその他特に必要があると認めるときは、自ら当該市町村に対し、当該第一号法定受託事務の処理について違反の是正又は改善のため講ずべき措置に関し、必要な指示をすることができる。
解説:
中央選挙管理会は、選挙事務が法律に違反しているか、適切に行われていない場合に是正を指示します。この指示には以下のような対応が含まれます。
- 都道府県への是正指示:都道府県が選挙の事務を法律に違反して処理している場合、中央選挙管理会はその是正や改善のための具体的な指示を出します。これにより、都道府県が正しく選挙事務を行うようにします。
- 都道府県選挙管理委員会への指示:中央選挙管理会は、都道府県の選挙管理委員会に対して、市町村の選挙事務の適正な処理を確保するための指示を行います。
- 市町村への直接指示:市町村が選挙の事務を法律に違反して処理している場合、特に緊急の時には、中央選挙管理会が市町村に対して直接指示を出し、法令違反を是正し、事務を改善させます。これにより、選挙事務がすぐに正しく行われるようにします。
これらの指示は、選挙が公正に行われ、みんなにとって良い選挙になるようにするためのものです。
公職選挙法 第5条の5(中央選挙管理会の処理基準)
原文:
第五条の五 中央選挙管理会は、この法律又はこの法律に基づく政令に係る都道府県の第一号法定受託事務の処理について、都道府県が当該第一号法定受託事務を処理するに当たりよるべき基準を定めることができる。
2 都道府県の選挙管理委員会が、地方自治法第二百四十五条の九第二項の規定により、市町村の選挙管理委員会がこの法律の規定に基づき担任する第一号法定受託事務の処理について、市町村が当該第一号法定受託事務を処理するに当たりよるべき基準を定める場合において、当該都道府県の選挙管理委員会の定める基準は、次項の規定により中央選挙管理会の定める基準に抵触するものであつてはならない。
3 中央選挙管理会は、特に必要があると認めるときは、この法律又はこの法律に基づく政令に係る市町村の第一号法定受託事務の処理について、市町村が当該第一号法定受託事務を処理するに当たりよるべき基準を定めることができる。
4 中央選挙管理会は、この法律又はこの法律に基づく政令に係る市町村の第一号法定受託事務の処理について、都道府県の選挙管理委員会に対し、地方自治法第二百四十五条の九第二項の規定により定める基準に関し、必要な指示をすることができる。
5 第一項又は第三項の規定により定める基準は、その目的を達成するために必要な最小限度のものでなければならない。
解説:
- 基準の設定: 中央選挙管理会は、都道府県が選挙事務を処理する際に従うべき基準を設定します。
- 市町村の基準設定の監督: 都道府県の選挙管理委員会が市町村の選挙事務の基準を設定する場合、その基準が中央選挙管理会の基準と矛盾しないようにしなければなりません。
- 市町村の基準設定: 必要があると認められた場合、中央選挙管理会は市町村の選挙事務の基準を設定します。
- 都道府県への指示: 中央選挙管理会は、都道府県の選挙管理委員会に対して、市町村の選挙事務に関する基準について必要な指示を行います。
- 最小限の基準設定: 設定する基準は、その目的を達成するために必要最小限のものにします。
公職選挙法 第5条の6(参議院合同選挙区選挙管理委員会)
原文:
第五条の六 二の都道府県の区域を区域とする参議院(選挙区選出)議員の選挙区内の当該二の都道府県(以下「合同選挙区都道府県」という。)は、協議により規約を定め、共同して参議院合同選挙区選挙管理委員会を置くものとする。
2 参議院(選挙区選出)議員の選挙のうち二の都道府県の区域を区域とする選挙区において行われるもの(以下「参議院合同選挙区選挙」という。)に関する事務は、第五条の規定にかかわらず、参議院合同選挙区選挙管理委員会が管理する。この場合において、参議院合同選挙区選挙管理委員会が管理する事務は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とみなして、同法その他の法令の規定を適用する。
3 参議院合同選挙区選挙管理委員会は、委員八人をもつて組織する。
4 委員は、合同選挙区都道府県の選挙管理委員会の委員をもつて充てる。
5 委員は、合同選挙区都道府県の選挙管理委員会の委員でなくなつたときに限り、その職を失う。
6 委員の任期は、合同選挙区都道府県の選挙管理委員会の委員としての任期による。ただし、地方自治法第百八十三条第一項ただし書の規定により後任者が就任する時まで合同選挙区都道府県の選挙管理委員会の委員として在任する間は、委員として在任する。
7 委員は、非常勤とする。
8 委員は、合同選挙区都道府県に対しその職務に関し請負をする者及びその支配人又は主として同一の行為をする法人(当該合同選挙区都道府県が出資している法人で政令で定めるものを除く。)の無限責任社員、取締役、執行役若しくは監査役若しくはこれらに準ずべき者、支配人及び清算人たることができない。
9 参議院合同選挙区選挙管理委員会の委員長は、委員の中から互選しなければならない。
10 委員長は、参議院合同選挙区選挙管理委員会を代表し、その事務を総理する。
11 参議院合同選挙区選挙管理委員会の会議は、五人以上の委員の出席がなければ開くことができない。
12 参議院合同選挙区選挙管理委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。
13 参議院合同選挙区選挙管理委員会に職員を置く。
14 前項の職員は、合同選挙区都道府県の選挙管理委員会が協議して定めるところにより、合同選挙区都道府県の選挙管理委員会の職員をもつて充てるものとする。ただし、合同選挙区都道府県の知事が協議して定めるところにより、その補助機関である職員をもつて充てることを妨げない。
15 第十三項の職員は、委員長の命を受け、参議院合同選挙区選挙管理委員会に関する事務に従事する。
16 参議院合同選挙区選挙管理委員会の設置に関する規約には、次に掲げる事項につき規定を設けなければならない。
- 一 参議院合同選挙区選挙管理委員会の名称
- 二 参議院合同選挙区選挙管理委員会の経費の支弁の方法
- 三 参議院合同選挙区選挙管理委員会の執務場所
- 四 前三号に掲げるものを除くほか、参議院合同選挙区選挙管理委員会に関し必要な事項
17 参議院合同選挙区選挙管理委員会の処分又は裁決(行政事件訴訟法(昭和三十七年法律第百三十九号)第三条第二項に規定する処分又は同条第三項に規定する裁決をいう。)に係る同法第十一条第一項(同法第三十八条第一項(同法第四十三条第二項において準用する場合を含む。)又は同法第四十三条第一項において準用する場合を含む。)の規定による合同選挙区都道府県を被告とする訴訟については、参議院合同選挙区選挙管理委員会が当該合同選挙区都道府県を代表する。
18 この法律又はこれに基づく政令で特別の定めをするものを除くほか、参議院合同選挙区選挙管理委員会については、これを各合同選挙区都道府県の地方自治法第百三十八条の四第一項に規定する委員会とみなして、同法その他の法令の規定を適用する。
19 この法律及びこれに基づく政令並びに参議院合同選挙区選挙管理委員会の設置に関する規約に規定するものを除くほか、参議院合同選挙区選挙管理委員会に関し必要な事項は、参議院合同選挙区選挙管理委員会が定める。
解説:
- 設置と組織: 二つの都道府県が協力して規約を定め、参議院合同選挙区選挙管理委員会を設置します。委員会は、両都道府県の選挙管理委員会の委員で構成され、委員は合計八人です。委員の任期は都道府県の選挙管理委員会の任期と同じです。
- 委員の資格: 委員は、特定の職務を兼ねることができません。たとえば、契約業者やその管理者、あるいは一定の法人の役員などは委員になることができません。
- 委員長の選出と役割: 委員の中から互選で委員長を選びます。委員長は委員会を代表し、会議を主催します。会議は五人以上の出席が必要で、議事は過半数の賛成で決まります。
- 職員の配置: 職員は都道府県の選挙管理委員会の職員が担当しますが、知事が協議して補助機関の職員を配置することも可能です。職員は委員長の指示を受け、委員会の事務を遂行します。
- 規約に定める事項: 委員会の名称、経費の負担方法、執務場所など、運営に必要な事項は規約で定められます。
- 処分または裁決の代理: 行政事件訴訟法に基づく処分や裁決に関する訴訟では、委員会が都道府県を代表します。
- 法的適用: 特別な規定がない限り、地方自治法の委員会に関する規定が適用されます。
参議院合同選挙区選挙管理委員会は、法令に基づいて設置され、選挙の公正な運営を確保するために必要な機能を果たします。
公職選挙法 第5条の7(参議院合同選挙区選挙管理委員会の技術的な助言及び勧告並びに資料の提出の要求)
原文:
第五条の七 参議院合同選挙区選挙管理委員会は、参議院合同選挙区選挙に関する事務(合同選挙区都道府県の選挙管理委員会が担任する事務に係るものを除く。次項及び第三項並びに次条第一項において同じ。)について、市町村に対し、市町村の事務の運営その他の事項について適切と認める技術的な助言若しくは勧告をし、又は当該助言若しくは勧告をするため若しくは市町村の事務の適正な処理に関する情報を提供するため必要な資料の提出を求めることができる。
2 総務大臣は、参議院合同選挙区選挙に関する事務について、参議院合同選挙区選挙管理委員会に対し、前項の規定による市町村に対する助言若しくは勧告又は資料の提出の求めに関し、必要な指示をすることができる。
3 参議院合同選挙区選挙管理委員会は総務大臣に対し、市町村の選挙管理委員会は参議院合同選挙区選挙管理委員会に対し、参議院合同選挙区選挙に関する事務の管理及び執行について技術的な助言若しくは勧告又は必要な情報の提供を求めることができる。
解説:
- 市町村への助言と勧告:市町村が選挙事務を適切に行うために、技術的な助言や勧告を行います。また、必要に応じて、情報提供のための資料の提出を求めることができます。
- 総務大臣の指示:総務大臣は、参議院合同選挙区選挙管理委員会に対し、市町村に対する助言や勧告、資料の提出の求めに関して指示を出すことができます。
- 情報の提供要求:参議院合同選挙区選挙管理委員会は総務大臣に対して、市町村の選挙管理委員会は参議院合同選挙区選挙管理委員会に対して、選挙に関する事務の管理や執行に関する情報の提供を求めることができます。
公職選挙法 第5条の8(参議院合同選挙区選挙管理委員会の是正の指示)
原文:
第五条の八 参議院合同選挙区選挙管理委員会は、この法律又はこの法律に基づく政令に係る市町村の選挙管理委員会の担任する地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務(参議院合同選挙区選挙に関する事務に限る。以下この条及び次条において「第一号法定受託事務」という。)の処理が法令の規定に違反していると認めるとき、又は著しく適正を欠き、かつ、明らかに公益を害していると認めるときは、当該市町村に対し、当該第一号法定受託事務の処理について違反の是正又は改善のため講ずべき措置に関し、必要な指示をすることができる。
2 総務大臣は、この法律又はこの法律に基づく政令に係る市町村の第一号法定受託事務の処理について、参議院合同選挙区選挙管理委員会に対し、前項の規定による市町村に対する指示に関し、必要な指示をすることができる。
3 地方自治法第二百四十五条の七第二項及び第三項の規定は、この法律又はこの法律に基づく政令に係る市町村の第一号法定受託事務については、適用しない。
4 第一項の規定による指示を行つた参議院合同選挙区選挙管理委員会は地方自治法第二百四十五条の七第二項の規定による指示を行つた都道府県の執行機関と、第二項の指示を行つた総務大臣は同条第三項の指示を行つた各大臣とみなして、同法第二百五十二条第三項及び第四項の規定を適用する。
解説:
- 市町村への是正指示:選挙事務が法律に違反している、または適正でない場合に市町村に対して是正や改善を指示します。
- 総務大臣の指示権限:総務大臣は、市町村に対する是正や改善の指示を参議院合同選挙区選挙管理委員会に対して行うことができます。
- 地方自治法の適用除外:地方自治法の特定の規定は、この是正指示の過程には適用されません。
- 法的なみなし適用:参議院合同選挙区選挙管理委員会の指示を都道府県の執行機関、総務大臣の指示を各大臣とみなして適用されます。
公職選挙法 第5条の9(参議院合同選挙区選挙管理委員会の処理基準)
原文:
第五条の九 参議院合同選挙区選挙管理委員会は、この法律又はこの法律に基づく政令に係る市町村の選挙管理委員会の担任する第一号法定受託事務の処理について、市町村が当該第一号法定受託事務を処理するに当たりよるべき基準を定めることができる。この場合において、参議院合同選挙区選挙管理委員会の定める基準は、地方自治法第二百四十五条の九第三項の規定により総務大臣の定める基準に抵触するものであつてはならない。
2 総務大臣は、この法律又はこの法律に基づく政令に係る市町村の第一号法定受託事務の処理について、参議院合同選挙区選挙管理委員会に対し、前項の規定により定める基準に関し、必要な指示をすることができる。
3 第一項の規定により定める基準は、その目的を達成するために必要な最小限度のものでなければならない。
4 地方自治法第二百四十五条の九第二項及び第四項の規定は、この法律又はこの法律に基づく政令に係る市町村の第一号法定受託事務については、適用しない。
解説:
参議院合同選挙区選挙管理委員会は、市町村の選挙管理委員会が選挙事務を正しく処理するための基準を定めることができます。この基準は以下の条件に従います。
- 基準の設定:参議院合同選挙区選挙管理委員会は、市町村の選挙事務に関する基準を設定できます。
- 総務大臣との調整:この基準は総務大臣の定める基準と矛盾しないようにしなければなりません。
- 総務大臣の指示:総務大臣は、市町村の選挙事務に関する基準について必要な指示を行うことができます。
- 最小限の基準:設定する基準は、目的を達成するために必要な最小限度のものである必要があります。
- 適用除外:特定の地方自治法の規定は、この基準設定には適用されません。
公職選挙法 第5条の10(合同選挙区都道府県の選挙管理委員会の委員の失職の特例)
原文:
第五条の十 合同選挙区都道府県の選挙管理委員会の委員は、地方自治法第百八十四条第一項に定めるもののほか、参議院合同選挙区選挙管理委員会の委員として第五条の六第八項の規定に該当するときは、その職を失う。この場合において、同項の規定に該当するかどうかは、当該委員の属する合同選挙区都道府県の選挙管理委員会がこれを決定する。
2 地方自治法第百四十三条第二項から第四項までの規定は、前項の場合について準用する。
解説:
合同選挙区都道府県の選挙管理委員会の委員は、以下の場合に職を失います:
- 失職の条件:地方自治法第184条第1項の規定に加え、参議院合同選挙区選挙管理委員会の委員として第5条の6第8項の規定に該当する場合です。これは、委員が職務を遂行できない場合や不適格行為を行った場合を含みます。
- 判断の決定:委員が規定に該当するかどうかは、その委員が属する合同選挙区都道府県の選挙管理委員会が決定します。
- 準用規定:地方自治法第143条第2項から第4項までの規定は、前述の失職の条件に該当する場合に適用されます。これは、失職に関する具体的な手続きや詳細な規定を含みます。
公職選挙法 第6条(選挙に関する啓発、周知等)
原文:
第六条 総務大臣、中央選挙管理会、参議院合同選挙区選挙管理委員会、都道府県の選挙管理委員会及び市町村の選挙管理委員会は、選挙が公明かつ適正に行われるように、常にあらゆる機会を通じて選挙人の政治常識の向上に努めるとともに、特に選挙に際しては投票の方法、選挙違反その他選挙に関し必要と認める事項を選挙人に周知させなければならない。
2 中央選挙管理会、参議院合同選挙区選挙管理委員会、都道府県の選挙管理委員会及び市町村の選挙管理委員会は、選挙の結果を選挙人に対して速やかに知らせるように努めなければならない。
3 選挙人に対しては、特別の事情がない限り、選挙の当日、その選挙権を行使するために必要な時間を与えるよう措置されなければならない。
解説:
総務大臣や各級選挙管理委員会は、選挙が公平かつ適正に行われるように努力します。そのために、以下のような活動を行います。
- 選挙の教育と周知:選挙が公正に行われるよう、常に選挙人の政治知識を高める努力をします。特に選挙時には、投票方法や選挙違反などの重要事項を周知します。
- 選挙結果の速やかな通知:選挙が終わったら、速やかに選挙結果を選挙人に知らせるよう努めます。
- 選挙日の配慮:特別な事情がない限り、選挙人が投票できるように選挙当日に必要な時間を確保する措置を講じます。
公職選挙法 第7条(選挙取締の公正確保)
原文:
第七条 検察官、都道府県公安委員会の委員及び警察官は、選挙の取締に関する規定を公正に執行しなければならない。
解説:
選挙が公正に行われるために、以下の役割を担う人々が公平な取り締まりを行う必要があります:
- 検察官:選挙違反があった場合、法律に基づいて厳正に捜査し、必要に応じて起訴します。
- 都道府県公安委員会の委員:選挙違反の防止と取り締まりを監督し、警察の活動を指導します。
- 警察官:選挙期間中に不正や違反行為を防止し、発見した場合には直ちに対処します。
これにより、選挙が公平で自由に行われることが保障されます。
公職選挙法 第8条(特定地域に関する特例)
原文:
第八条 交通至難の島その他の地において、この法律の規定を適用し難い事項については、政令で特別の定をすることができる。
解説:
第8条は、交通が非常に不便な離島や僻地などで、公職選挙法の通常の規定を適用するのが難しい場合に、特別なルールを設けることができるとしています。この特例は、選挙の公平性を保つための措置であり、例えば次のような状況に対応します:
- 交通困難地域:離島や山間部など、投票所へのアクセスが難しい場所。
- 特別な措置:郵便投票、移動投票所の設置、投票期間の延長など。
これにより、すべての国民が平等に投票できる環境を整えています。
第二章 選挙権及び被選挙権
公職選挙法 第9条(選挙権)
原文:
第九条 日本国民で年齢満十八年以上の者は、衆議院議員及び参議院議員の選挙権を有する。
2 日本国民たる年齢満十八年以上の者で引き続き三箇月以上市町村の区域内に住所を有する者は、その属する地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権を有する。
3 日本国民たる年齢満十八年以上の者でその属する市町村を包括する都道府県の区域内の一の市町村の区域内に引き続き三箇月以上住所を有していたことがあり、かつ、その後も引き続き当該都道府県の区域内に住所を有するものは、前項に規定する住所に関する要件にかかわらず、当該都道府県の議会の議員及び長の選挙権を有する。
4 前二項の市町村には、その区域の全部又は一部が廃置分合により当該市町村の区域の全部又は一部となつた市町村であつて、当該廃置分合により消滅した市町村(この項の規定により当該消滅した市町村に含むものとされた市町村を含む。)を含むものとする。
5 第二項及び第三項の三箇月の期間は、市町村の廃置分合又は境界変更のため中断されることがない。
解説:
第9条では、日本国民が選挙権を持つ条件について説明しています。
- 基本条件:日本国民で18歳以上の者は、衆議院議員および参議院議員の選挙権を持ちます。
- 地方選挙の条件:18歳以上の日本国民で、3ヶ月以上市町村に住所がある者は、その市町村の地方公共団体の議員や長の選挙権を持ちます。
- 都道府県選挙の特例:市町村の区域内に3ヶ月以上住所があった後、同じ都道府県内に住所がある者は、住所要件に関係なく、都道府県の議員および長の選挙権を持ちます。
- 廃置分合の場合:市町村の廃置分合で消滅した市町村の住民も、引き続き選挙権を持ちます。
- 住所期間の中断:市町村の廃置分合や境界変更によっても、3ヶ月の住所要件期間は中断されません。
公職選挙法 第10条(被選挙権)
原文:
第十条 日本国民は、左の各号の区分に従い、それぞれ当該議員又は長の被選挙権を有する。
一 衆議院議員については年齢満二十五年以上の者
二 参議院議員については年齢満三十年以上の者
三 都道府県の議会の議員についてはその選挙権を有する者で年齢満二十五年以上のもの
四 都道府県知事については年齢満三十年以上の者
五 市町村の議会の議員についてはその選挙権を有する者で年齢満二十五年以上のもの
六 市町村長については年齢満二十五年以上の者
2 前項各号の年齢は、選挙の期日により算定する。
解説:
日本国民が選挙に立候補できる条件について説明しています。
- 衆議院議員:25歳以上の日本国民。
- 参議院議員:30歳以上の日本国民。
- 都道府県議会の議員:その選挙権を持つ25歳以上の日本国民。
- 都道府県知事:30歳以上の日本国民。
- 市町村議会の議員:その選挙権を持つ25歳以上の日本国民。
- 市町村長:25歳以上の日本国民。
- 年齢の算定:選挙の日を基準に年齢を計算します。
公職選挙法 第11条(選挙権及び被選挙権を有しない者)
原文:
第十一条 次に掲げる者は、選挙権及び被選挙権を有しない。
一 削除
二 禁錮以上の刑に処せられその執行を終わるまでの者
三 禁錮以上の刑に処せられその執行を受けることがなくなるまでの者(刑の執行猶予中の者を除く。)
四 公職にある間に犯した刑法(明治四十年法律第四十五号)第百九十七条から第百九十七条の四までの罪又は公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律(平成十二年法律第百三十号)第一条の罪により刑に処せられ、その執行を終わり若しくはその執行の免除を受けた者でその執行を終わり若しくはその執行の免除を受けた日から五年を経過しないもの又はその刑の執行猶予中の者
五 法律で定めるところにより行われる選挙、投票及び国民審査に関する犯罪により禁錮以上の刑に処せられその刑の執行猶予中の者
2 この法律の定める選挙に関する犯罪に因り選挙権及び被選挙権を有しない者については、第二百五十二条の定めるところによる。
3 市町村長は、その市町村に本籍を有する者で他の市町村に住所を有するもの又は他の市町村において第三十条の六の規定による在外選挙人名簿の登録がされているものについて、第一項又は第二百五十二条の規定により選挙権及び被選挙権を有しなくなるべき事由が生じたこと又はその事由がなくなつたことを知つたときは、遅滞なくその旨を当該他の市町村の選挙管理委員会に通知しなければならない。
解説:
次のような人たちは選挙権と被選挙権がありません。
- 禁錮以上の刑を受けている人:刑の執行が終わるまで。
- 刑の執行猶予がない人:刑の執行を受けることがなくなるまで。ただし、執行猶予中は除く。
- 公職中の犯罪で有罪となった人:刑法第197条から第197条の4の罪や公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律第1条の罪で刑に処せられ、執行が終わった日から5年以内、または刑の執行猶予中の人。
- 選挙や投票に関する犯罪で有罪となった人:禁錮以上の刑を受け、その刑の執行猶予中の人。
さらに、市町村長は、自分の市町村に本籍がある人で、他の市町村に住所がある人について、選挙権や被選挙権を持たなくなった理由が生じたとき、またはその理由がなくなったときに、他の市町村の選挙管理委員会に通知する必要があります。
公職選挙法 第11条の2(被選挙権を有しない者)
原文:
第十一条の二 公職にある間に犯した前条第一項第四号に規定する罪により刑に処せられ、その執行を終わり又はその執行の免除を受けた者でその執行を終わり又はその執行の免除を受けた日から五年を経過したものは、当該五年を経過した日から五年間、被選挙権を有しない。
解説:
公職にある間に特定の罪を犯して有罪判決を受けた人は、その刑が終わった日または免除された日から5年間、選挙に立候補する権利(被選挙権)がありません。さらに、その5年が経過した後も、さらに5年間は被選挙権がありません。
第三章 選挙に関する区域
公職選挙法 第12条(選挙の単位)
原文:
第十二条 衆議院(小選挙区選出)議員、衆議院(比例代表選出)議員、参議院(選挙区選出)議員及び都道府県の議会の議員は、それぞれ各選挙区において、選挙する。
2 参議院(比例代表選出)議員は、全都道府県の区域を通じて、選挙する。
3 都道府県知事及び市町村長は、当該地方公共団体の区域において、選挙する。
4 市町村の議会の議員は、選挙区がある場合にあつては、各選挙区において、選挙区がない場合にあつてはその市町村の区域において、選挙する。
解説:
衆議院議員:
- 小選挙区選出議員:それぞれの小選挙区で選ばれます。
- 比例代表選出議員:全国をいくつかのブロックに分けて、そのブロックごとに選ばれます。
参議院議員:
- 選挙区選出議員:それぞれの選挙区で選ばれます。
- 比例代表選出議員:全都道府県を通じて選ばれます。
地方公共団体の長と議員:
- 都道府県知事、市町村長:その地方公共団体の区域で選ばれます。
- 市町村議会の議員:選挙区がある場合はその選挙区で、ない場合はその市町村の区域で選ばれます。
公職選挙法 第13条(衆議院議員の選挙区)
原文:
第十三条 衆議院(小選挙区選出)議員の選挙区は、別表第一で定め、各選挙区において選挙すべき議員の数は、一人とする。
2 衆議院(比例代表選出)議員の選挙区及び各選挙区において選挙すべき議員の数は、別表第二で定める。
3 別表第一に掲げる行政区画その他の区域に変更があつても、衆議院(小選挙区選出)議員の選挙区は、なお従前の区域による。ただし、二以上の選挙区にわたつて市町村の境界変更があつたときは、この限りでない。
4 前項ただし書の場合において、当該市町村の境界変更に係る区域の新たに属することとなつた市町村が二以上の選挙区に分かれているときは、当該区域の選挙区の所属については、政令で定める。
5 衆議院(比例代表選出)議員の二以上の選挙区にわたつて市町村の廃置分合が行われたときは、第二項の規定にかかわらず、別表第一が最初に更正されるまでの間は、衆議院(比例代表選出)議員の選挙区は、なお従前の区域による。
6 地方自治法第六条の二第一項の規定による都道府県の廃置分合があつても、衆議院(比例代表選出)議員の選挙区は、なお従前の区域による。
7 別表第二は、国勢調査(統計法(平成十九年法律第五十三号)第五条第二項本文の規定により十年ごとに行われる国勢調査に限る。以下この項において同じ。)の結果によつて、更正することを例とする。この場合において、各選挙区の議員数は、各選挙区の人口(最近の国勢調査の結果による日本国民の人口をいう。以下この項において同じ。)を比例代表基準除数(その除数で各選挙区の人口を除して得た数(一未満の端数が生じたときは、これを一に切り上げるものとする。)の合計数が第四条第一項に規定する衆議院比例代表選出議員の定数に相当する数と合致することとなる除数をいう。)で除して得た数(一未満の端数が生じたときは、これを一に切り上げるものとする。)とする。
解説:
衆議院議員の選挙区:
- 衆議院の小選挙区選出議員は「別表第一」に基づいて選挙区が決まっており、各選挙区から一人が選ばれます。
- 衆議院の比例代表選出議員は「別表第二」に基づいて選挙区が決まり、各選挙区からの議員数もそこで定められています。
行政区画の変更:
- 行政区画の変更があっても、小選挙区選出議員の選挙区は基本的に従前の区域のままです。ただし、市町村の境界変更が複数の選挙区にわたる場合は例外です。
比例代表選出議員の選挙区:
- 比例代表選出議員の選挙区は、市町村の廃置分合があっても「別表第一」が改訂されるまで従前の区域のままです。
- 都道府県の廃置分合があっても比例代表選出議員の選挙区は従前の区域のままです。
国勢調査の影響:
- 「別表第二」は、10年ごとの国勢調査の結果に基づいて改訂されます。この際、各選挙区の議員数は、各選挙区の人口を基準に算定されます。
公職選挙法 第14条(参議院選挙区選出議員の選挙区)
原文:
第十四条 参議院(選挙区選出)議員の選挙区及び各選挙区において選挙すべき議員の数は、別表第三で定める。
2 地方自治法第六条の二第一項の規定による都道府県の廃置分合があつても、参議院(選挙区選出)議員の選挙区及び各選挙区において選挙すべき議員の数は、なお従前の例による。
解説:
参議院選挙区選出議員の選挙区:
- 参議院の選挙区選出議員の選挙区と各選挙区から選ばれる議員の数は、「別表第三」に定められています。
行政区画の変更:
- 都道府県の廃置分合(統合や分割)があっても、参議院の選挙区と選ばれる議員の数は変更前のまま維持されます。
公職選挙法 第15条(地方公共団体の議会の議員の選挙区)
原文:
第十五条 都道府県の議会の議員の選挙区は、一の市の区域、一の市の区域と隣接する町村の区域を合わせた区域又は隣接する町村の区域を合わせた区域のいずれかによることを基本とし、条例で定める。
2 前項の選挙区は、その人口が当該都道府県の人口を当該都道府県の議会の議員の定数をもつて除して得た数(以下この条において「議員一人当たりの人口」という。)の半数以上になるようにしなければならない。この場合において、一の市の区域の人口が議員一人当たりの人口の半数に達しないときは、隣接する他の市町村の区域と合わせて一選挙区を設けるものとする。
3 一の市の区域の人口が議員一人当たりの人口の半数以上であつても議員一人当たりの人口に達しないときは、隣接する他の市町村の区域と合わせて一選挙区を設けることができる。
4 一の町村の区域の人口が議員一人当たりの人口の半数以上であるときは、当該町村の区域をもつて一選挙区とすることができる。
5 一の市町村(地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)にあつては、区(総合区を含む。第六項及び第九項において同じ。)。以下この項において同じ。)の区域が二以上の衆議院(小選挙区選出)議員の選挙区に属する区域に分かれている場合における前各項の規定の適用については、当該各区域を市町村の区域とみなすことができる。
6 市町村は、特に必要があるときは、その議会の議員の選挙につき、条例で選挙区を設けることができる。ただし、指定都市については、区の区域をもつて選挙区とする。
7 第一項から第四項まで又は前項の規定により選挙区を設ける場合においては、行政区画、衆議院(小選挙区選出)議員の選挙区、地勢、交通等の事情を総合的に考慮して合理的に行わなければならない。
8 各選挙区において選挙すべき地方公共団体の議会の議員の数は、人口に比例して、条例で定めなければならない。ただし、特別の事情があるときは、おおむね人口を基準とし、地域間の均衡を考慮して定めることができる。
9 指定都市に対し第一項から第三項までの規定を適用する場合における市の区域(市町村の区域に係るものを含む。)は、当該指定都市の区域を二以上の区域に分けた区域とする。この場合において、当該指定都市の区域を分けるに当たつては、第五項の場合を除き、区の区域を分割しないものとする。
10 前各項に定めるもののほか、地方公共団体の議会の議員の選挙区及び各選挙区において選挙すべき議員の数に関し必要な事項は、政令で定める。
解説:
- 第1項の解説:都道府県議会の議員選挙区は、基本的に一つの市、または一つの市と隣接する町村、または隣接する町村を合わせた区域で構成され、条例で定められます。
- 第2項の解説:選挙区の人口は、都道府県の総人口を議員の総数で割った「議員一人当たりの人口」の半数以上である必要があります。もし一つの市の人口がこの基準に達しない場合、隣接する市町村と合わせて一つの選挙区にします。
- 第3項の解説:一つの市の人口が「議員一人当たりの人口」の半数以上であるが、それでも基準に達しない場合、その市は隣接する他の市町村と合わせて選挙区を形成できます。
- 第4項の解説:一つの町村の人口が「議員一人当たりの人口」の半数以上である場合、その町村を一つの選挙区として認めることができます。
- 第5項の解説:指定都市の区域が複数の衆議院小選挙区にまたがる場合、その区域を市町村の区域とみなして選挙区を設定できます。
- 第6項の解説:市町村は特に必要がある場合、条例で独自に選挙区を設定できます。ただし、指定都市については区の区域をもって選挙区とします。
- 第7項の解説:選挙区を設ける際には、行政区画、衆議院小選挙区、地勢、交通などの事情を総合的に考慮して合理的に行わなければなりません。
- 第8項の解説:選挙区ごとの議員数は人口に比例して条例で定められますが、特別な事情がある場合は、地域間の均衡を考慮して定めることができます。
- 第9項の解説:指定都市にこの規定を適用する場合、指定都市の区域を複数の区域に分けることができます。ただし、区の区域を分割しないことが原則です。
- 第10項の解説:地方公共団体の議会の議員の選挙区や議員数に関する詳細な事項は、政令で定められます。
公職選挙法 第15条の2(選挙区の選挙期間中の特例)
原文:
第一項 衆議院(小選挙区選出)議員の選挙の期日の公示又は告示がなされた日からその選挙の期日までの間において二以上の選挙区にわたつて市町村の境界変更があつても、当該選挙区は、第十三条第三項ただし書の規定にかかわらず、当該選挙については、変更しないものとする。
第二項 衆議院(比例代表選出)議員の選挙の期日の公示又は告示がなされた日からその選挙の期日までの間において二以上の選挙区にわたつて都道府県の境界の変更があつても、当該選挙区は、第十三条第二項の規定にかかわらず、当該選挙については、変更しないものとする。
第三項 参議院(選挙区選出)議員の選挙の期日の公示又は告示がなされた日からその選挙の期日までの間において二以上の選挙区にわたつて都道府県の境界の変更があつても、当該選挙区は、第十四条第一項の規定にかかわらず、当該選挙については、変更しないものとする。
第四項 都道府県の議会の議員の選挙の期日の告示がなされた日からその選挙の期日までの間において市町村の区域の変更(都道府県の境界にわたるものを除く。)があつても、当該選挙区は、前条第一項から第五項までの規定にかかわらず、当該選挙については、変更しないものとする。
解説:
- 第1項の解説:衆議院(小選挙区選出)議員の選挙期間中に市町村の境界が変更されても、その選挙に関しては選挙区の変更を行いません。
- 第2項の解説:衆議院(比例代表選出)議員の選挙期間中に都道府県の境界が変更されても、その選挙に関しては選挙区の変更を行いません。
- 第3項の解説:参議院(選挙区選出)議員の選挙期間中に都道府県の境界が変更されても、その選挙に関しては選挙区の変更を行いません。
- 第4項の解説:都道府県議会議員の選挙期間中に市町村の区域が変更されても、その選挙に関しては選挙区の変更を行いません。ただし、都道府県の境界にわたる変更は含まれません。
公職選挙法 第16条(選挙区の異動と現任者の地位)
原文:
現任の衆議院議員、参議院(選挙区選出)議員、都道府県の議会の議員及び市町村の議会の議員は、行政区画その他の区域の変更によりその選挙区に異動があつても、その職を失うことはない。
解説:
- この条文の解説:現職の議員(衆議院議員、参議院議員、都道府県議会議員、市町村議会議員)は、選挙区が行政区画やその他の区域の変更により異動しても、職を失うことはありません。つまり、選挙区が変わっても現職の議員としての地位はそのまま維持されます。
公職選挙法 第17条(投票区)
原文:
投票区は、市町村の区域による。
2 市町村の選挙管理委員会は、必要があると認めるときは、市町村の区域を分けて数投票区を設けることができる。
3 前項の規定により、投票区を設けたときは、市町村の選挙管理委員会は、直ちに告示しなければならない。
解説:
- 投票区の基本:投票区は、市町村の区域に基づいて設定されます。
- 複数の投票区の設定:市町村の選挙管理委員会は、必要に応じて市町村の区域を分割し、複数の投票区を設けることができます。
- 告示の義務:複数の投票区を設けた場合、市町村の選挙管理委員会はその決定を直ちに告示する義務があります。
公職選挙法 第18条(開票区)
原文:
開票区は、市町村の区域による。ただし、衆議院(小選挙区選出)議員の選挙若しくは都道府県の議会の議員の選挙において市町村が二以上の選挙区に分かれているとき、又は第十五条第六項の規定による選挙区があるときは、当該選挙区の区域により市町村の区域を分けて数開票区を設けるものとする。
2 都道府県の選挙管理委員会は、政令で定めるところにより、特別の事情があると認めるときに限り、前項の規定にかかわらず、市町村の区域を分けて、又は数市町村の区域の全部若しくは一部を合わせて、開票区を設けることができる。
3 前項の規定により開票区を設けたときは、都道府県の選挙管理委員会は、直ちに告示しなければならない。
解説:
- 開票区の基本:開票区は基本的に市町村の区域に基づきます。
- 特例:市町村が複数の選挙区に分かれている場合や、第十五条第六項の規定に基づく選挙区がある場合は、その選挙区ごとに開票区を設けます。
- 特別な事情:都道府県の選挙管理委員会は、特別な事情があると認めた場合、市町村の区域を分割したり、複数の市町村の区域を合わせて開票区を設けることができます。
- 告示の義務:特別な開票区を設けた場合、都道府県の選挙管理委員会は直ちに告示する必要があります。
第四章 選挙人名簿
公職選挙法 第19条(永久選挙人名簿)
原文:
選挙人名簿は、永久に据え置くものとし、かつ、各選挙を通じて一の名簿とする。
2 市町村の選挙管理委員会は、選挙人名簿の調製及び保管の任に当たるものとし、毎年三月、六月、九月及び十二月(第二十二条及び第二十四条第一項において「登録月」という。)並びに選挙を行う場合に、選挙人名簿の登録を行うものとする。
3 選挙人名簿は、政令で定めるところにより、磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)をもつて調製することができる。
4 選挙を行う場合において必要があるときは、選挙人名簿の抄本(前項の規定により磁気ディスクをもつて選挙人名簿を調製している市町村の選挙管理委員会にあつては、当該選挙人名簿に記録されている全部若しくは一部の事項又は当該事項を記載した書類。以下同じ。)を用いることができる。
解説:
- 永久保存:選挙人名簿は永久に保存され、すべての選挙で一つの名簿を使用します。
- 登録月:市町村の選挙管理委員会は、毎年3月、6月、9月、12月、そして選挙が行われる際に選挙人名簿の登録を行います。
- 磁気ディスクの使用:選挙人名簿は、政令で定められた方法に従い、磁気ディスクなどの方法で作成できます。
- 抄本の利用:選挙が行われる際に必要なら、選挙人名簿の抄本を使用できます。
公職選挙法 第20条(選挙人名簿の記載事項等)
原文:
選挙人名簿には、選挙人の氏名、住所(次条第二項に規定する者にあつては、その者が当該市町村の区域内から住所を移す直前に住民票に記載されていた住所)、性別及び生年月日等の記載(前条第三項の規定により磁気ディスクをもつて調製する選挙人名簿にあつては、記録)をしなければならない。
2 選挙人名簿は、市町村の区域を分けて数投票区を設けた場合には、その投票区ごとに編製しなければならない。
3 前二項に規定するもののほか、選挙人名簿の様式その他必要な事項は、政令で定める。
解説:
- 選挙人名簿の内容:選挙人名簿には、選挙人の氏名、住所、性別、生年月日などが記載されます。住所については、特定の条件に該当する場合は過去の住所が記載されます。
- 投票区ごとの編製:市町村が区域を分けて複数の投票区を設けた場合、その投票区ごとに選挙人名簿を作成します。
- 様式とその他の事項:選挙人名簿の形式やその他必要な事項は、政令で定められます。
公職選挙法 第21条(被登録資格等)
原文:
選挙人名簿の登録は、当該市町村の区域内に住所を有する年齢満十八年以上の日本国民(第十一条第一項若しくは第二百五十二条又は政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)第二十八条の規定により選挙権を有しない者を除く。次項において同じ。)で、その者に係る登録市町村等(当該市町村及び消滅市町村(その区域の全部又は一部が廃置分合により当該市町村の区域の全部又は一部となつた市町村であつて、当該廃置分合により消滅した市町村をいう。第三項において同じ。)をいう。以下この項及び次項において同じ。)の住民票が作成された日(他の市町村から登録市町村等の区域内に住所を移した者で住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第二十二条の規定により届出をしたものについては、当該届出をした日。次項において同じ。)から引き続き三箇月以上登録市町村等の住民基本台帳に記録されている者について行う。
2 選挙人名簿の登録は、前項の規定によるほか、当該市町村の区域内から住所を移した年齢満十八年以上の日本国民のうち、その者に係る登録市町村等の住民票が作成された日から引き続き三箇月以上登録市町村等の住民基本台帳に記録されていた者であつて、登録市町村等の区域内に住所を有しなくなつた日後四箇月を経過しないものについて行う。
3 第一項の消滅市町村には、その区域の全部又は一部が廃置分合により当該消滅市町村の区域の全部又は一部となつた市町村であつて、当該廃置分合により消滅した市町村(この項の規定により当該消滅した市町村に含むものとされた市町村を含む。)を含むものとする。
4 第一項及び第二項の住民基本台帳に記録されている期間は、市町村の廃置分合又は境界変更のため中断されることがない。
5 市町村の選挙管理委員会は、政令で定めるところにより、当該市町村の選挙人名簿に登録される資格を有する者を調査し、その者を選挙人名簿に登録するための整理をしておかなければならない。
解説:
- 選挙人名簿の登録資格:18歳以上の日本国民で、その市町村に住んでいる人が対象です。ただし、選挙権を持たない人(例えば刑に服している人など)は除かれます。
- 引っ越しの場合の登録:市町村から引っ越しても、前の市町村で3か月以上住んでいた人は、引っ越し後4か月以内であれば選挙人名簿に登録されます。
- 消滅市町村:市町村が合併して消滅しても、合併前の市町村での住所記録は有効です。
- 期間の中断なし:市町村の合併や境界変更があっても、住民基本台帳の記録期間は中断されません。
- 調査と整理:市町村の選挙管理委員会は、選挙人名簿に登録される資格を持つ人を調査し、整理しておく必要があります。
- 登録基準日:市町村の選挙管理委員会は、登録月の1日に18歳以上の選挙人資格を持つ住民を名簿に登録します。ただし、地方公共団体の休日に当たる場合や特別な事情がある場合には、登録日は変更できます。
- 選挙実施時の特例:選挙が行われる期間においては、登録月の1日が選挙の公示または告示の日から選挙日の前日までにあたる場合、選挙人名簿への登録はその選挙日における年齢に基づきます。
- 選挙時登録の基準日:選挙の際には、選挙管理委員会が定める基準日現在で登録します。これにより、選挙の実施に向けて適切な選挙人名簿が準備されます。
- 重複登録の防止:登録月の1日と選挙時登録の基準日が同じ場合には、重複を避けるため登録は行われません。
- 異議申出の方法:選挙人は、自分が選挙人名簿に正しく登録されていないと感じた場合、市町村の選挙管理委員会に文書で異議を申し出ることができます。
- 異議申出の期間:異議申出は、選挙人名簿の登録が行われた日の翌日から5日以内に行う必要があります。選挙が近い場合は、登録の翌日に異議を申し出ることが求められます。
- 異議の審査:選挙管理委員会は、異議を受けてから3日以内にその正当性を決定し、結果を申出人に通知します。異議が正当と認められた場合は、名簿の訂正を行います。
- 準用規定:行政不服審査法の一部規定を異議の申し出に適用し、手続きの公平性と透明性を確保します。
- 訴訟の対象:選挙人名簿の登録に関する市町村選挙管理委員会の決定に不服がある場合、その決定に対して訴訟を起こすことができます。
- 訴訟の期限:異議申出人または関係人は、決定の通知を受けた日から7日以内に訴訟を提起する必要があります。
- 訴訟の場所:訴訟は、市町村選挙管理委員会の所在地を管轄する地方裁判所で行われます。
- 上訴の制限:地方裁判所の判決に不服がある場合、控訴はできませんが、最高裁判所に上告することができます。
- 準用規定:特定の行政不服審査法の規定が、この訴訟手続きにも適用されます。
- 補正登録の義務:市町村の選挙管理委員会は、選挙人名簿に登録される資格があり、その資格を引き続き持つ者が登録されていないと判明した場合、その人を直ちに選挙人名簿に登録しなければなりません。
- 告示の必要:その登録が行われたことを、速やかに告示する必要があります。
- 選挙権の喪失や住所変更の表示:選挙管理委員会は、選挙人が選挙権を失ったり、市町村の区域内に住所を持たなくなった場合、その旨を選挙人名簿に直ちに表示しなければなりません。
- 特定の者の登録時の表示:選挙管理委員会は、特定の基準に該当する者を選挙人名簿に登録する際、その者がその基準に該当することを明示する必要があります。
- 名簿記載内容の修正:選挙人名簿の記載内容に変更や誤りがある場合、選挙管理委員会は速やかにその内容を修正または訂正しなければなりません。
- 死亡または国籍喪失:選挙管理委員会は、選挙人が死亡したり日本の国籍を失ったことを知った場合、直ちにその者を選挙人名簿から抹消します。
- 住所変更後の抹消:選挙人が市町村内に住所を有しなくなってから4ヶ月が経過した場合、その者を選挙人名簿から抹消します。
- 在外選挙人名簿への登録移転:在外選挙人名簿への登録移転が行われる場合、その者を選挙人名簿から抹消します。
- 登録誤りの抹消:登録時に登録されるべきでなかったことが判明した場合、その旨を告示して直ちに抹消します。
- 選挙人名簿の抄本の閲覧期間:選挙の公示または告示の日から選挙後5日までの間は閲覧できませんが、それ以外の期間は特定の活動のために閲覧が可能です。
- 確認活動:特定の選挙人が名簿に登録されているかを確認するため、選挙人自身が申請すれば名簿を閲覧できます。
- 政治活動:政治活動や選挙運動のために、公職候補者や政党などが申請し、必要な範囲で名簿を閲覧できます。
- 申請内容:申請時には、申請者の氏名住所、閲覧目的、名簿を閲覧する者の情報などを明示する必要があります。
- 閲覧拒否の条件:不当な目的や適切に管理されない恐れがある場合、市町村選挙管理委員会は閲覧を拒否できます。
- 閲覧事項の管理:閲覧事項を第三者に取り扱わせる場合、その者の情報を申請し、承認を得る必要があります。
- 管理措置:申請者や閲覧者は、閲覧事項の漏洩防止など適切な管理措置を講じる必要があります。
- 選挙人名簿の抄本の閲覧: 政治や選挙に関する公益性の高い調査研究のために名簿を閲覧できます。
- 閲覧の申出: 閲覧を希望する者は、申請書に氏名、住所、利用目的、閲覧者の情報などを明示する必要があります。
- 閲覧の対象者:
- 国や地方公共団体の機関:指定された職員。
- 法人:法人の役職員や構成員。
- 個人:本人またはその指定する者。
- 閲覧の管理: 閲覧者や指定された者は、情報漏洩防止など適切な管理措置を講じる必要があります。
- 閲覧の拒否: 市町村の選挙管理委員会は、不当な利用目的や適切な管理ができないと判断した場合、閲覧を拒否することができます。
- その他: 必要に応じて、追加の管理方法や取り扱い者の範囲を申請し、承認を受ける必要があります。
- 同意なしの使用禁止: 閲覧者や申出者は、本人の同意なく、選挙人名簿の情報を利用目的以外で使用したり、第三者に提供してはなりません。
- 勧告と命令: 不正な手段で情報を閲覧したり、同意なしに情報を使用した場合、市町村の選挙管理委員会は是正措置を勧告し、従わない場合は命令できます。
- 報告義務: 市町村の選挙管理委員会は、必要に応じて申出者に報告を求めることができます。
- 公表義務: 市町村の選挙管理委員会は、毎年一回以上、閲覧状況について公表しなければなりません。
- 国の機関の例外: 申出者が国の機関である場合には、これらの規定は適用されません。
- 通報義務: 市町村長と市町村の選挙管理委員会は、選挙人の住所確認や選挙資格の確認に必要な情報をお互いに通報しなければなりません。
- 調査の請求: 選挙人は、選挙人名簿に漏れ、誤り、または記載ミスがあると認識した場合、市町村の選挙管理委員会に修正のための調査を依頼することができます。
- 再調製の必要性: 天災や事故などで選挙人名簿が影響を受けた場合、市町村の選挙管理委員会は新たに選挙人名簿を作成しなければなりません。
- 調製の詳細: 新しい選挙人名簿の作成に関する期日や異議の申出期間などの詳細は政令で決められます。
- 在外選挙人名簿の調製と保管: 市町村の選挙管理委員会は、通常の選挙人名簿に加えて、在外選挙人名簿も作成し、保管します。
- 在外選挙人名簿の永久据え置き: この名簿は永続的に保管され、衆議院議員と参議院議員の選挙において使用されます。
- 在外選挙人名簿の登録と移転: 市町村の選挙管理委員会は、申請に基づいて在外選挙人名簿の登録および選挙人名簿から在外選挙人名簿への登録の移転を行います。
- 磁気ディスクの使用: 在外選挙人名簿は、政令に従って磁気ディスクを使用して作成することができます。
- 抄本の利用: 選挙の際には、必要に応じて在外選挙人名簿の抄本を使用することができます。
- 在外選挙人名簿の記載事項: 在外選挙人名簿には、選挙人の氏名、国外移住前の住所、申請時の本籍、性別、生年月日などが記載されます。
- 投票区の指定: 市町村の選挙管理委員会は、区域を分けて複数の投票区を設ける場合、在外選挙人名簿を編成するための投票区を指定します。
- 政令による規定: 在外選挙人名簿の形式やその他必要な事項は、政令で定められます。
- 在外選挙人名簿の登録資格: 在外選挙人名簿への登録は、18歳以上の日本国民で、国外に3か月以上住所を持つ人が対象です。ただし、選挙権を失った人は除外されます。
- 領事官の管轄: 登録には、その住所を管轄する領事官の管轄区域内で3か月以上住所を有する必要があります。
- 在外選挙人名簿の移転: 在外選挙人名簿への登録の移転は、最終住所地の市町村選挙人名簿に登録されている18歳以上の日本国民が対象です。
- 在外選挙人名簿の登録申請: 18歳以上の日本国民で、在外選挙人名簿に登録されていない者が対象です。登録には、最終住所地の市町村の選挙管理委員会へ文書で申請します。
- 領事官経由の申請: 在外選挙人名簿に関する事務についてその者の住所を管轄する領事官を経由して申請しなければなりません。
- 領事官の役割: 領事官は、申請書を受け取った後、速やかに意見を付して市町村の選挙管理委員会に送付します。
- 国外転出者の申請: 国外転出届を提出した者は、在外選挙人名簿への登録の移転を申請できます。この場合、市町村の選挙管理委員会は外務大臣に意見を求めます。
- 外務大臣の役割: 外務大臣は、国外における住所に関する意見を市町村の選挙管理委員会に述べます。
- 登録手続き: 在外選挙人名簿の登録申請を行った者が登録資格を持っている場合、市町村の選挙管理委員会は速やかにその者を登録します。
- 登録の移転: 移転申請がされた場合も、資格を満たしていれば速やかに登録の移転を行います。
- 選挙期間中の制限: 衆議院や参議院の選挙期間中は、新規登録や登録の移転は行いません。
- 在外選挙人証の交付: 登録や移転が完了した場合、申請者に対して在外選挙人証が交付されます。
- 異議申出の方法: 在外選挙人名簿の登録や登録の移転に不服がある場合、処分の直後から5日間以内に、文書で市町村の選挙管理委員会に異議を申し出ることができます。
- 異議の判断期間: 市町村の選挙管理委員会は、異議申出を受けてから3日以内に、その異議の正当性を判断しなければなりません。
- 結果の通知: 異議が正当と認められた場合、速やかに登録を行うか抹消し、その結果を通知・告示します。不正当と認められた場合は、その旨を異議申出人に通知します。
- 法令準用: 行政不服審査法の一部規定を準用し、適切な手続きが行われるようにしています。
- 訴訟の準用: 在外選挙人名簿の登録や登録の移転に関する訴訟には、第25条の1項から3項までの規定が適用されます。
- 条文の読み替え: 第25条の規定を適用する際に、「前条第2項」は「第30条の8第2項」と読み替え、「7日」は郵便による日数を除く旨に読み替えます。
- その他準用条文: 第213条、第214条、および第219条第1項の規定も適用されます。
- 在外選挙人名簿の表示: 市町村の選挙管理委員会は、在外選挙人名簿に登録されている人が選挙権を失った場合や、国内で新しい住民票が作成された場合、その旨を名簿に表示します。
- 記載内容の修正・訂正: 名簿の記載内容に変更や誤りがあった場合、市町村の選挙管理委員会は直ちに修正・訂正を行います。
- 死亡または国籍喪失: 登録されている人が死亡したり日本国籍を失った場合、すぐに名簿から抹消します。
- 住所変更後の抹消: 国内の市町村に住所を定めた日から4か月経過した場合、その人を名簿から抹消します。
- 誤った登録の抹消: 登録や登録移転が誤りであると判明した場合、その旨を告示し、名簿から抹消します。
- 在外選挙人名簿の閲覧: 在外選挙人名簿の閲覧に関しては、国内の選挙人名簿の規定をそのまま適用します。
- 規定の読み替え: 閲覧に関する具体的な手続きについては、第28条の規定を在外選挙人名簿に準用し、必要な箇所は第30条の規定に読み替えます。
- 他市町村の在外選挙人: 市町村長は、他の市町村の在外選挙人名簿に登録されている人の戸籍情報に変更があった場合、その情報を遅滞なく当該市町村の選挙管理委員会に通知する義務があります。
- 準用規定: 在外選挙人名簿に関しても、第29条の通報及び調査の請求に関する規定が適用されます。
- 在外選挙人証交付記録簿の閲覧: 選挙人が特定の人が在外選挙人名簿に登録されているか確認したい場合、領事官に申請して確認できます。
- 申出の方法: 申請は、申請者の氏名や住所などを明示して行います。
- 閲覧の制限: 不適切な目的に利用される恐れがある場合、領事官は閲覧を拒否できます。
- 情報の取り扱い: 閲覧者は、閲覧事項を目的以外に利用したり、第三者に提供してはなりません。
- 制限事項: 規定外の閲覧は認められません。
- 基本規定の適用: 第三十条の規定は在外選挙人名簿の再調製にも適用されます。
- 状況の適用: 必要に応じて在外選挙人名簿を再調製する際も、第三十条に準じた手続きが行われます。
- 政令で定める事項: 在外選挙人名簿の登録や登録の移転に関する細かいルールや手続きは、政令で定めることになります。
- 対象範囲: 第30条の4から第30条の6、および第30条の8から第30条の15までの規定に関する詳細な手続きをカバーします。
- 総選挙のタイミング: 衆議院議員の任期満了による総選挙は、議員の任期が終わる前の30日以内に行います。
- 特別な場合: 国会開会中や閉会後23日以内に総選挙の期間が重なる場合は、国会閉会の日から24日以降30日以内に実施されます。
- 解散による総選挙: 衆議院の解散による総選挙は、解散の日から40日以内に行います。
- 公示期間: 総選挙の期日は少なくとも12日前に公示される必要があります。
- 解散後の公示無効: 任期満了に因る総選挙の公示後に衆議院が解散された場合、その公示は無効となります。
- 通常選挙のタイミング: 参議院議員の任期満了による通常選挙は、議員の任期が終わる前の30日以内に行います。
- 特別な場合: 参議院開会中や閉会後23日以内に通常選挙の期間が重なる場合は、参議院閉会の日から24日以降30日以内に実施されます。
- 公示期間: 通常選挙の期日は少なくとも17日前に公示される必要があります。
- 一般選挙と任期満了の選挙: 地方公共団体の議会の議員や長の任期が満了する前の30日以内に行われます。
- 議会の解散による選挙: 解散から40日以内に行われます。
- 地方公共団体の設置による選挙: 設置の日から50日以内に行われます。
- 例外規定: 任期満了前に議員が全員欠けたり、長が欠けたりした場合、任期満了の選挙告示は行いませんが、解散や不信任の場合は効力を失います。
- 告示期間: 選挙の種類によって、選挙期日の少なくとも5日から17日前に告示されます。
- 再選挙の時期: 再選挙は、事由が生じた日から40日以内に行われます。
- 特定事由による再選挙: 特定の事由が生じた場合、選挙管理委員会の通知を受けた日から40日以内に実施されます。
- 統一対象再選挙・補欠選挙: 9月16日から翌年の3月15日までの間に事由が生じた場合、4月の第4日曜日に行います。3月16日から9月15日までの間に事由が生じた場合、10月の第4日曜日に行います。
- 衆議院議員の再選挙・補欠選挙: 参議院議員の任期が終わる年に特定の期間内で事由が生じた場合、参議院議員の通常選挙の期日に行います。
- 参議院議員の再選挙・補欠選挙: 在任期間を異にする参議院議員の任期が終わる年に特定の期間内で事由が生じた場合、通常選挙の期日に行います。
- 再選挙の実施条件: 衆議院議員及び参議院議員の再選挙は、任期終了前6か月以内に事由が生じた場合は行わず、統一対象再選挙・補欠選挙は、任期終了日の6か月前の日が属する期間内で事由が生じた場合は行いません。
- 再選挙・補欠選挙の期日告示: 衆議院議員の選挙は少なくとも12日前に、参議院議員の選挙は少なくとも17日前に告示されます。
- 再選挙と補欠選挙の期日: 地方公共団体の議会の議員や長の再選挙、補欠選挙は、事由が生じた日から50日以内に行われます。
- 特定の状況における選挙の除外: 一部の再選挙や補欠選挙は、議員の任期満了の6か月以内に事由が生じた場合は行われません。ただし、議員の定数が3分の2未満になった場合を除きます。
- 争訟係属等期間中の選挙実施: 争訟が係属している期間中は選挙を実施できません。
- 再選挙の特定日: 争訟係属等期間後の特定の日に基づいて再選挙が行われます。
- 選挙期日の告示: 選挙期日は選挙の種類によって、少なくとも5日前から17日前までの間に告示される必要があります。
- 同時選挙の特例: 地方公共団体の議会の議員と長の任期が近い場合、特例として同時に選挙を行うことができます。
- 選挙実施の告示: 同時選挙を行う場合、選挙期日の60日前までに告示が必要です。
- 議員全員の欠員: 同時選挙の告示後、議員全員が欠けた場合、長の選挙期日は議員の任期満了の日から50日以内に実施されます。
- 投票による選挙: 全ての選挙は投票によって行われます。
- 一人一票の原則: 投票は各選挙ごとに一人一票に限られます。
- 衆議院議員の選挙: 小選挙区選出議員と比例代表選出議員それぞれに対して一人一票です。
- 参議院議員の選挙: 選挙区選出議員と比例代表選出議員それぞれに対して一人一票です。
- 投票管理者の設置: 各選挙ごとに投票管理者が設置されます。
- 選任方法: 投票管理者は選挙権を有する者から市町村の選挙管理委員会が選任します。
- 同時選挙の投票管理者: 衆議院および参議院の選挙で、小選挙区と比例代表の選挙が同時に行われる場合、同じ投票管理者を任命することができます。
- 業務内容: 投票管理者は投票に関する事務を担当します。
- 職の喪失: 投票管理者が選挙権を失うと、その職も失います。
- 特定投票区の指定: 市町村の選挙管理委員会は、政令で定めるところにより特定の投票区を指定し、その管理者に他の投票区の事務を行わせることができます。
- 投票立会人の選任: 市町村の選挙管理委員会は、各選挙ごとに選挙権を有する者の中から、本人の承諾を得て二人以上五人以下の投票立会人を選任します。
- 人数不足時の対応: 投票立会人が二人に達しない場合、投票管理者が選挙権を有する者の中から補充します。
- 候補者の制限: 選挙の公職候補者は投票立会人になれません。
- 政党制限: 同一の政党に属する者は、一つの投票区で二人以上選任できません。
- 辞職の制限: 正当な理由がなければ投票立会人は辞職できません。
- 投票所の設置場所: 投票所は、市役所、町村役場、または市町村の選挙管理委員会が指定した場所に設けられます。
- 投票所の開閉時間: 投票所は通常、午前7時に開き、午後8時に閉じます。
- 例外の対応: 市町村の選挙管理委員会は特別な事情がある場合、投票所の開閉時間を変更することができます。開く時刻は2時間以内、閉じる時刻は4時間以内で繰り上げることが可能です。
- 告示と通知: 開閉時間を変更する場合、市町村の選挙管理委員会は直ちにその旨を告示し、投票管理者に通知しなければなりません。また、地方選挙以外では都道府県の選挙管理委員会にも届け出る必要があります。
- 投票所の告示: 市町村の選挙管理委員会は、選挙の期日の少なくとも5日前に投票所を告示する必要があります。
- 変更時の対応: 天災や避けられない事故で投票所が変更された場合、選挙当日を除いてすぐに告示する必要があります。
- 共通投票所の設置: 市町村の選挙管理委員会は、選挙人の便宜のため、複数の投票区を設けた場合に限り、どの投票区の選挙人も投票できる共通投票所を設けることができます。
- 投票の重複防止: 投票所や共通投票所での二重投票を防止するための措置を講じる必要があります。
- 事故時の対応: 天災など避けられない事故で共通投票所が使用できない場合、その共通投票所は閉鎖され、すぐに告示されます。
- 共通投票所に関する特例: 投票時間や投票期日の設定において、特定の規定の字句を読み替えて適用することができます。
- 投票資格の確認: 選挙人名簿または在外選挙人名簿に登録されていない者は投票できません。ただし、登録されるべき旨の決定書または確定判決書を持っている者は投票が認められます。
- 登録後の制限: 名簿に登録されていても、登録の資格を失った者は投票することができません。
- 選挙権のない者: 選挙の当日に選挙権を持たない者は投票することができません。
- 特別な投票方法: 第四十八条の二の規定による投票でも同様に、当日に選挙権を持たない者は投票できません。
- 自ら投票: 選挙人は選挙当日に自ら投票所に行って投票しなければなりません。
- 名簿の対照: 投票前に選挙人名簿またはその抄本と対照する必要があります。
- 住所証明: 都道府県の議員および長の選挙で従前の住所がある市町村で投票する場合、引き続きその都道府県内に住所があることを証明する文書を提示する必要があります。
- 投票用紙の交付: 投票用紙は選挙当日に投票所で選挙人に交付されます。
- 様式の決定: 投票用紙の様式は、国政選挙の場合は総務省令で、地方選挙の場合は各選挙管理委員会が定めます。
- 投票の方法: 衆議院・参議院の比例代表選出議員以外の選挙では、選挙人は候補者一人の氏名を投票用紙に自書して投票します。
- 衆議院比例代表選挙: 投票用紙に政党の名称または略称を自書して投票します。
- 参議院比例代表選挙: 候補者の氏名または政党の名称または略称を自書して投票します。
- 記名禁止: 投票用紙に選挙人の氏名を記載してはいけません。
- この条文は、地方公共団体の議会の議員または長の選挙において、投票方式を記号式投票にすることを定めています。
- 選挙人は、投票用紙に候補者の名前が印刷されている場合、その候補者の名前の横に〇を記入して投票します。
- 〇の記号を使って投票する際の方法や印刷順序などの詳細は、政令で定められます。
- この条文は、点字を用いて投票する場合に、その点字の記載を正式な文字と同様に認めることを定めています。
- 点字による投票の詳細な方法や形式は、政令によって定められます。
- この条文は、心身の故障などで自ら投票用紙に記載できない選挙人が、代理投票を申請できることを定めています。
- 代理投票の申請があった場合、投票管理者は投票立会人の意見を聞き、投票を補助する者二人を選びます。
- 一人が選挙人の指示に基づいて投票用紙に記載し、もう一人がそれに立ち会います。
- 必要な事項については政令で定められます。
- この条文は、選挙当日に投票が困難な選挙人が期日前投票を行うことができる場合について定めています。
- 期日前投票は、選挙の公示または告示の翌日から選挙の前日まで行うことができます。
- 対象となる事由には、職務、旅行、疾病、交通の困難、住所の問題、天災などがあります。
- 市町村の選挙管理委員会は、期日前投票所の設置に関する必要な措置を講じなければなりません。
- 不在者投票の方法: 投票用紙に投票の記載をし、これを封筒に入れて不在者投票管理者に提出する方法で行います。
- 重度の障害者の投票: 身体に重度の障害がある選挙人は、その現在する場所で投票用紙に記載し、郵便等で送付できます。
- 国外派遣組織の選挙人: 国外派遣組織に属する選挙人は、国外の不在者投票管理者の管理する場所で投票できます。
- 特定国外派遣組織: 特定の国外施設や区域に滞在する組織で、法令に基づき管理されるもの。
- 船員や南極地域調査組織の選挙人: 指定船舶や南極地域調査組織に属する選挙人は、ファクシミリ装置を使用して投票を送信する方法が利用可能です。
- 在外選挙人の投票方法: 在外選挙人名簿に登録されている選挙人は、衆議院議員および参議院議員の選挙において、次のいずれかの方法で投票できます。
- 在外公館の投票所で投票する。
- 郵便で投票する。
- 国内での投票: 在外選挙人が国内で投票する場合は、共通投票所で投票することができます。
- 規定の適用: 在外選挙人の投票に関しては、一部の規定が適用されません。
- 本人確認: 投票管理者は、投票者が本人であるか確認できない場合、その旨の宣言を求める。
- 投票の拒否: 投票を拒否する場合は、投票立会人の意見を聴いて投票管理者が決定する。
- 仮投票の実施: 拒否決定に不服がある場合、仮に投票させる。
- 封筒に入れる: 仮投票は封筒に入れて封をし、氏名を記載して投票箱に入れる。
- 異議のある場合: 投票立会人に異議がある場合も同様に対応する。
- 退出した者の投票: 第六十条に基づき投票所外に退出させられた者は、最後に投票することが認められます。
- 秩序維持の判断: 投票管理者が投票所の秩序を乱す恐れがないと判断した場合、退出した者の投票を妨げないことができます。
- 投票の秘密保護: 誰も選挙人が投票した候補者の名前や政党の名称、略称を述べる義務はありません。これは投票の秘密を守るための規定です。
- 投票箱の閉鎖: 投票所の閉鎖時間が来たら、投票管理者は投票所を閉鎖し、内部の投票を終えた後、投票箱を閉鎖します。
- 閉鎖後の投票: 投票箱の閉鎖後は、誰も投票を行うことができません。
- 投票録の作成: 投票管理者は、投票の進行状況や内容を記録した投票録を作成します。
- 署名の必要性: 作成された投票録には、投票管理者と投票立会人が署名しなければなりません。
- 投票箱等の送致: 投票管理者は、投票箱や投票録、選挙人名簿などを開票管理者に送致しなければならない。
- 例外規定: 投票管理者が開票管理者を兼任する場合や、選挙人名簿が磁気ディスクで調製されている場合には、送致を省略することができます。
- 送致の同伴: 送致には、一人または複数の投票立会人が同行します。
- 繰上投票の対象: 島や交通の不便な地域が対象です。
- 繰上投票の理由: 選挙期日に投票箱を送致できない状況があると認められる場合です。
- 投票期日の設定: 都道府県の選挙管理委員会(市町村の選挙の場合は市町村の選挙管理委員会)が適宜に投票期日を定めます。
- 送致の要件: 開票期日までに投票箱、投票録、選挙人名簿等を送致させることができます。
- 繰延投票の対象: 天災や避けることのできない事故により、投票を行えない場合や更に投票が必要な場合です。
- 繰延投票の期日設定: 都道府県または市町村の選挙管理委員会が新たな期日を定め、直ちに告示し、その期日を少なくとも二日前に告示する必要があります。
- 届け出の義務: 衆議院議員、参議院議員、都道府県議会の議員や長の選挙において、該当する事由が生じた場合、市町村の選挙管理委員会は選挙長を経て都道府県の選挙管理委員会に報告しなければなりません。
- 入場可能な者: 投票所に入ることができるのは、選挙人、投票所の事務に従事する者、監視権限を持つ者、及び警察官のみです。
- 同伴する子供: 選挙人が連れている18歳未満の子供も投票所に入れますが、混雑や秩序保持が困難になる場合は、投票管理者の判断で入場が制限されます。
- 介護者等の入場: 選挙人を介護する者や特別な事情で必要な者も、投票管理者の認定があれば入場可能です。
- 秩序保持の権限: 投票管理者は、投票所の秩序を保つために必要と判断した場合、警察官に処分を求める権限を持ちます。
- 警察官の介入: この規定により、投票所でのトラブルや混乱を速やかに解決するために警察官の助けを求めることができます。
- 秩序の維持: 投票所での演説、討論、騒動、協議、勧誘など、秩序を乱す行為は禁止されています。
- 投票管理者の権限: 投票管理者は、秩序を乱す者を制止し、従わない場合は投票所から退出させる権限を持ちます。
- 開票管理者の設置: 各選挙ごとに開票管理者を任命します。
- 選任基準: 開票管理者は、選挙権を持つ者から市町村の選挙管理委員会が選任します。
- 同時選挙の場合: 衆議院および参議院の同時選挙では、一人の開票管理者が複数の役割を兼任できます。
- 役割: 開票管理者は、開票に関する全ての事務を担当します。
- 選挙権の喪失: 選挙権を失うと、自動的に開票管理者の職も失います。
- 第1項: 開票立会人の設置: 各選挙の開票区ごとに、公職の候補者や政党が開票立会人を指定し、市町村の選挙管理委員会に届け出ます。
- 第2項: 開票立会人の選定: 開票立会人の届け出が10人を超える場合、選挙管理委員会がくじで10人を選びます。10人以内なら全員が開票立会人となります。
- 第3項: 政党の制限: 同一政党に属する公職候補者の立会人は、一つの開票区において3人以上選出されることはできません。
- 第4項: くじの制限: 同一政党からの立会人が3人以上の場合、選挙管理委員会はくじで2人に減らします。
- 第5項: 立会人の辞退と喪失: 正当な理由がない限り、立会人は職を辞することができず、特定の事由により職を失うことがあります。
- 第6項: くじの手続きの告示: くじを行う日時と場所は事前に告示されます。
- 第7項: 職の喪失: 特定の事由が生じた場合、該当する開票立会人は職を失います。
- 第8項: 選定手続き: 都道府県の選挙管理委員会が選定した場合、市町村の選挙管理委員会が開票立会人を選びます。
- 第9項: 補充選定: 開票立会人が不足する場合、選挙管理委員会は必要人数を選定します。
- 第10項: 公職の候補者の制限: 公職の候補者は開票立会人になることはできません。
- 第11項: 辞職の制限: 開票立会人は、正当な理由がない限り職を辞することができません。
- 開票所の設置場所: 開票所は、市役所、町村役場、または市町村の選挙管理委員会が指定した場所に設けられます。この規定は、開票作業が適切に行われるようにするため、一定の基準を持った場所での開票を求めています。
- 告示義務: 市町村の選挙管理委員会は、開票が行われる場所と日時を事前に告示する義務があります。この告示により、有権者や関係者が開票の状況を把握し、透明性のある選挙運営が確保されます。
- 開票のタイミング: 開票作業は、すべての投票箱が集められた日、またはその翌日に実施されます。この規定により、開票が迅速かつ効率的に行われることが求められています。
- 投票箱の開封: 開票管理者は、開票立会人の立会のもとで投票箱を開封し、まず特定の投票(第五十条第三項及び第五項の規定によるもの)を調査します。
- 受理の決定: 開票管理者は開票立会人の意見を聞き、その投票を受理するかどうかを決定します。
- 投票の混合と点検: 各投票所及び期日前投票所の投票を混合し、点検します。
- 結果の報告: 投票の点検が終わったら、開票管理者はその結果を選挙長に直ちに報告します。
- 投票の効力の決定: 投票の有効性は、開票立会人の意見を聞いた上で、開票管理者が決定します。
- 選挙人の意思の尊重: 決定においては、第六十八条に反しない限り、選挙人の意思が明確である場合、その投票を有効とするよう努めなければなりません。
- 所定の用紙を用いない投票: 指定された用紙以外を使用した投票は無効です。
- 不適格な候補者への投票: 候補者資格を持たない者の名前を記載した投票は無効です。
- 不適切な政党の候補者への投票: 正式に届け出されていない政党や違反政党の候補者の名前を記載した投票は無効です。
- 複数の候補者への投票: 一枚の投票用紙に複数の候補者の名前を記載した投票は無効です。
- 被選挙権のない候補者への投票: 被選挙権を持たない候補者の名前を記載した投票は無効です。
- 他の事項を記載した投票: 候補者の名前以外の事項を記載した投票は無効です。ただし、職業、住所、敬称の記載は例外です。
- 氏名を自書しない投票: 候補者の名前を自書しない投票は無効です。
- 識別困難な投票: 記載内容が不明瞭で、誰に投票したかが判断できない投票は無効です。
- 衆議院比例代表選出議員選挙の無効投票条件: 指定された用紙を用いない投票や、正式に届け出されていない政党の名称を記載した投票などが無効です。
- 参議院比例代表選出議員選挙の無効投票条件: 指定された用紙を用いない投票、公職の候補者たる参議院名簿登載者でない者の名前を記載した投票などが無効です。
- 同一氏名の候補者: 同一の氏名、氏、または名の候補者が複数いる場合、その名前だけを記載した投票は有効です。
- 政党名の重複: 同じ名称または略称の政党が複数ある場合、その名称または略称だけを記載した投票も有効です。
- 参議院名簿: 同一氏名の参議院名簿登載者や同一名称の政党が複数ある場合も、有効とされます。
- 按分の方法: 有効とされた投票は開票区ごとに按分され、他の有効投票数に加算されます。
- 按分の適用: 参議院名簿登載者についても同様に、按分された有効投票数が加算されます。
- 参議院名簿登載者の有効投票: 優先的に当選人となるべき候補者の有効投票は、その候補者が属する参議院名簿届出政党等の有効投票とみなされます。
- 前条の適用除外: 第六十八条の第三項及び第五項の規定の適用を除く場合について言及しています。
- 按分して加えられた有効投票: 前条の第五項により按分して加えられた有効投票も含まれます。
- 参観の権利: 選挙人は、開票所での開票作業を見学する権利があります。
- 開票録の作成: 開票管理者は、開票の手順や結果を記録した開票録を作成します。
- 署名の必要性: 開票録には、開票管理者と開票立会人が署名する必要があります。
- 保存の対象: 投票は、有効票と無効票を区別して保存します。
- 保存の内容: 投票録と開票録も併せて保存されます。
- 保存期間: 保存期間は、当該選挙に関する議員または長の任期中です。
- 保存場所: すべての保存は、市町村の選挙管理委員会が行います。
- 一部無効の選挙: 選挙の一部が無効となった場合、その部分について再選挙が行われます。
- 再選挙の開票: 再選挙における開票は、その投票の効力を決定する必要があります。
- 規定の準用: 第五十七条第一項前段および第二項の規定が開票に適用されます。
- 繰延開票の適用: 天災や事故など避けられない理由で開票が行えない場合や、さらに開票を行う必要がある場合に、適用される規定です。
- 規定の準用: 第五十八条第一項(投票所に出入し得る者)、第五十九条(投票所の秩序保持のための処分の請求)、および第六十条(投票所における秩序保持)の規定が、開票所の取締りにも適用されます。
- 適用範囲: これらの規定により、開票所においても投票所と同様に秩序を保ち、必要な処分を請求することができます。
- 選挙長の設置: 各選挙ごとに選挙長を任命します。
- 選挙分会長の設置: 衆議院比例代表選出議員、参議院比例代表選出議員、または参議院合同選挙区選挙においては、都道府県ごとに選挙分会長も任命します。
- 選任基準: 選挙長と選挙分会長は、選挙権を持つ者から選挙管理委員会が選任します。
- 役割: 選挙長は選挙会に関する事務、選挙分会長は選挙分会に関する事務を担当します。
- 職の喪失: 選挙権を失うと、選挙長および選挙分会長の職も失います。
- 準用規定: 第六十二条の規定は、選挙会および選挙分会の選挙立会人にも適用されます。
- 選挙権のある者: 選挙立会人は、選挙権を有する者から選ばれます。
- 期日前の届け出: 選挙立会人の届け出は、選挙の期日前三日までに行う必要があります。
- 選挙長の役割: 選挙立会人に関する決定は、選挙長が行います。
- 辞任と選任: 選挙立会人が辞任した場合、選挙長は新たな選挙立会人を選任します。
- 選挙会の開催場所: 選挙会は、都道府県庁または選挙管理委員会の指定した場所で行われます。
- 管理者の種類: 衆議院比例代表選挙や参議院比例代表選挙では、中央選挙管理会が場所を指定します。参議院合同選挙区選挙では、参議院合同選挙区選挙管理委員会が指定します。
- 選挙分会の開催場所: 選挙分会は、都道府県庁または都道府県の選挙管理委員会が指定した場所で行われます。
- 選挙会の告示: 衆議院比例代表選挙や参議院比例代表選挙では、中央選挙管理会が選挙会の場所と日時を告示します。参議院合同選挙区選挙では、該当する選挙管理委員会が告示します。
- 選挙分会の告示: 都道府県の選挙管理委員会が選挙分会の場所と日時を告示します。
- 合同の条件: 衆議院小選挙区選出議員や地方公共団体の議会の議員、長の選挙で選挙会区域と開票区が同じ場合、開票事務を選挙会の事務と合同で行うことができます。
- 告示の義務: 選挙管理委員会は、選挙の期日公示または告示の日に、開票事務を選挙会事務と併せて行うかどうかを告示しなければなりません。
- 役割の兼任: 開票管理者や開票立会人の役割は、選挙長や選挙立会人が兼任します。また、開票に関する事項は選挙録に併せて記載されます。
- 選挙会・選挙分会の開催: 選挙長または選挙分会長は、全開票管理者から報告を受けた日または翌日に選挙会または選挙分会を開催します。
- 報告の調査と得票総数の計算: 選挙立会人立会いの下、報告を調査し、各候補者および政党の得票総数を計算します。
- 投票点検結果の使用: 選挙長は投票点検結果を基に得票総数を計算します。
- 再選挙の場合: 一部無効選挙後の再選挙では、他の部分の報告と共に再調査し、得票総数を計算します。
- 選挙分会長の報告: 衆議院比例代表選出議員選挙では、選挙分会長は調査終了後、選挙録の写しを添えて選挙長に結果を報告します。
- 選挙長の調査と計算: 選挙長はすべての報告を受けた後、選挙会を開き、得票総数を計算します。
- 再選挙の場合: 無効選挙が再選挙を必要とする場合、選挙長は他の部分の報告とともに調査し、得票総数を計算します。
- 参議院選挙への適用: 同様の手続きが参議院比例代表選挙にも適用され、必要な部分は読み替えられます。
- 合同選挙区への適用: 参議院合同選挙区選挙についても同様の手続きが準用されます。
- 参観権: 選挙人は、選挙会や選挙分会の運営を参観する権利を持っています。
- 透明性の確保: 参観は選挙の透明性と公正性を確保するための重要な手段です。
- 選挙録の作成: 選挙長または選挙分会長は、選挙会または選挙分会に関する記録(選挙録)を作成し、選挙立会人と共に署名する必要があります。
- 選挙録の保存: 選挙録と関連書類は、議員または長の任期間中、選挙管理委員会に保存されます。これには、報告に関する書類も含まれます。
- 第七十九条の場合: 投票の有効無効を区別し、投票録と選挙録を併せて、選挙管理委員会に保存します。
- 準用規定: 第五十七条第一項の規定を選挙会及び選挙分会にも適用します。
- 選挙管理委員会の読み替え: 選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会について、衆議院比例代表選出議員及び参議院比例代表選出議員の選挙会は中央選挙管理会、参議院合同選挙区選挙の選挙会は当該選挙管理委員会、選挙分会は都道府県の選挙管理委員会と読み替えます。
- 準用規定: 第五十八条第一項(投票所への出入りに関する規定)、第五十九条(投票所の秩序保持のための警察官の処分の請求)、第六十条(投票所内の秩序保持)を選挙会場および選挙分会場にも適用します。
- 対象の政党や団体: 衆議院(小選挙区選出)議員の選挙で候補者を立てる場合、以下のいずれかに該当する政党や政治団体が届出を行えます。
- 5人以上の衆議院または参議院議員を有すること。
- 直近の選挙で得票率が2%以上であること。
- 届出の方法: 選挙期日の公示または告示日に、郵便等を使用せずに文書で届出を行います。
- 必要な記載事項: 届出文書には、政党名、本部所在地、代表者の氏名、候補者の氏名や住所、生年月日、職業などを記載します。
- 添付文書: 政党の綱領や党則、候補者の同意書、候補者が公職に就ける資格があることを証明する文書などが必要です。
- 再届出の条件: 届出後に候補者が死亡した場合などは、再度の届出が認められています。
- 無効の届出: 条件を満たさない場合や、違反があった場合は、届出が却下されることがあります。
- 参議院名簿登載者の届出: 政党や政治団体は、特定の条件を満たす場合に、名簿に記載された者を候補者として届け出ることができます。条件としては、所属する国会議員が5人以上いること、直近の選挙で得票率が2%以上であること、または参議院名簿登載者が10人以上いることが必要です。
- 届出の内容: 名簿には、政党や政治団体の名称、所属する者の氏名、生年月日、住所、職業などが記載されます。また、優先的に当選するべき候補者とその順位を記載することが可能です。
- 必要書類: 届出には、政党の綱領、党則、規約、候補者の同意書、資格証明書などの文書が必要です。これにより、提出された候補者が適格であることを証明します。
- 不適格者の排除: 選挙長は、候補者が死亡したり、資格を喪失した場合、名簿から抹消し、その旨を政党に通知します。また、除名や離党などによって政党に所属しなくなった場合も同様です。
- 名簿の補充と取り下げ: 名簿登載者が欠けた場合、政党は補充の届出を行うことができます。また、選挙長に文書で届け出ることにより、名簿を取り下げることも可能です。
- 告示義務: 届出や名簿の抹消があった場合、選挙長は速やかに告示し、中央選挙管理会に報告する義務があります。
- 政令の適用: 議員数や得票総数の算定方法など、届出に必要な詳細な事項は政令で定められます。
- 立候補の届出: 衆議院議員や参議院比例代表選出議員以外の選挙で立候補する場合、選挙の日に郵便等を使わず文書で届出を行う必要があります。
- 他人の推薦: 他人を候補者として推薦する場合は、本人の承諾を得て同様に届出を行います。
- 届出の内容: 届出には、候補者の氏名、本籍、住所、生年月日、職業、所属政党などを記載する必要があります。
- 必要書類: 届出には、各選挙の区分に応じた宣誓書や政党の証明書を添付する必要があります。
- 追加の届出期間: 参議院選挙区選出議員や地方議会の議員選挙では、特定の状況下で追加の届出期間が設けられています。
- 届出の却下: 候補者が資格を失った場合、選挙長は届出を却下します。
- 辞退の手続き: 候補者は特定の日までに辞退を届け出る必要があります。
- 告示義務: 届出や却下があった場合、選挙長は速やかに告示し、選挙管理委員会に報告する義務があります。
- 届け出義務: 政党や政治団体は、候補者選定手続きを定めた際に総務大臣に文書で届け出る必要があります。
- 記載事項: 届け出文書には政党名、所在地、代表者名、候補者選定機関の名称と選出方法などを記載する必要があります。
- 綱領や党則の添付: 綱領、党則、規約なども文書に添付する必要があります。
- 異動の届け出: 届け出た事項に変更があった場合も、7日以内に届け出なければなりません。
- 告示義務: 総務大臣は、届出があった場合に速やかに告示を行います。
- 解散や資格喪失の届け出: 政党が解散した場合や資格を失った場合も7日以内に届け出る必要があります。
- 名称と略称の届出: 衆議院比例代表選挙に参加する政党は、選挙後30日以内にその名称と略称を中央選挙管理会に届け出る必要があります。名称や略称に候補者の氏名を含めることはできません。
- 届出の内容: 文書には政党名、所在地、代表者の氏名、党則や綱領などを記載し、必要な書類を添付します。
- 変更の届出: 届け出た内容に変更が生じた場合は、7日以内に変更を届け出る義務があります。
- 解散や資格喪失の届出: 政党が解散したり、資格を失った場合も、7日以内に届け出る必要があります。
- 中央選挙管理会の告示: 届出があった場合、中央選挙管理会は速やかにその内容を告示します。
- 名称と略称の届出: 参議院比例代表選挙に参加する政党は、任期満了日前90日から7日間の間にその名称と略称を中央選挙管理会に届け出る必要があります。名称や略称に候補者の氏名を含めることはできません。
- 届出の内容: 文書には政党名、所在地、代表者の氏名、党則や綱領などを記載し、必要な書類を添付します。
- 変更の届出: 届け出た内容に変更が生じた場合は、7日以内に変更を届け出る義務があります。
- 撤回の届出: 届出後も文書で撤回でき、中央選挙管理会はその旨を告示します。
- 告示の義務: 中央選挙管理会は、届出があった場合、速やかにその内容を告示します。
- 被選挙権の制限: 第十一条第一項、第十一条の二、第二百五十二条、政治資金規正法第二十八条の規定により被選挙権を有しない者は、公職の候補者にはなれません。
- 選挙犯罪の影響: 第二百五十一条の二、第二百五十一条の三に規定される選挙に関する犯罪によって被選挙権を失った者も、公職の候補者にはなれません。
- 重複立候補の禁止: 一つの選挙に候補者として立候補した者は、同時に他の選挙に立候補できません。
- 政党の制限: 一つの政党に属する候補者は、同時に他の政党の候補者になることはできません。
- 選挙区の制限: 一つの選挙区で同じ政党が複数の候補者を立てることはできません。
- 名簿の制限: 一つの衆議院名簿登載者は、同時に他の名簿の登載者になることはできません。
- 比例代表制限: 衆議院および参議院の比例代表選挙で、政党は一つの選挙区に複数の名簿を提出できません。
- 立候補制限: 国会法第107条や第90条に基づいて辞職した衆議院小選挙区選出議員や参議院選挙区選出議員は、辞職により生じた欠員を埋める補欠選挙に立候補できません。
- 除外事項: 補欠選挙が通常選挙と合併して行われる場合はこの制限の対象外です。
- 立候補制限: 指定された選挙事務関係者は在職中、選挙の関係区域内で公職の候補者になれません。
- 対象者: 投票管理者、開票管理者、選挙長、および選挙分会長が含まれます。
- 立候補制限: 国や地方公共団体の公務員、行政執行法人や特定地方独立行政法人の役員や職員は、在職中は公職の候補者になれません。
- 例外: 内閣総理大臣や国務大臣など特定の役職の者や、政令で指定された技術者や非常勤の委員などは例外とされます。
- 選挙時の特例: 衆議院議員や参議院議員、地方議会の議員や長が任期満了選挙で公職候補者となる場合はこの制限が適用されません。
- 職務兼任の影響: 一部の公務員が兼任している地位にはこの制限が影響しません。
- 退職の見なされ方: 公務員が公職の候補者として届け出た場合、その届け出の日に自動的に公務員の職を辞したとみなされます。
- 適用範囲: この規定は、第八十六条、第八十六条の二、第八十六条の三、第八十六条の四の各項に基づく届け出に適用されます。
- 法令の優先: 退職に関する他の法令にかかわらず、届出の日に辞職が成立します。
- 届出の取り下げ: 候補者届出政党の候補者が公職の候補者となる資格を失った場合、その届出は取り下げられたとみなされます。
- 辞任の扱い: 個人で公職の候補者として届出した者が資格を失った場合、その候補者たることを辞任したとみなされます。
- 名簿登載者の扱い: 衆議院や参議院の比例代表選出議員の選挙で名簿に載っている候補者が資格を失った場合、その者は名簿から外されます。
- 供託の目的: 公職の候補者が適切な資格を持って立候補することを保証するために供託金が必要です。
- 金額の区分: 供託金の額は選挙の種類によって異なり、例えば衆議院(小選挙区)議員選挙は300万円、町村議会議員選挙は15万円など。
- 政党の供託: 政党が比例代表選出議員の候補者を届け出る場合、一人につき600万円を供託する必要があります。
- 国債証書: 供託金は現金だけでなく、国債証書でも供託することが可能です。
- 供託物の没収条件: 公職の候補者の得票数が次の基準に達しない場合、供託物は没収されます。
- 基準:
- 衆議院(小選挙区)議員選挙:有効投票の総数の十分の一
- 参議院(選挙区)議員選挙:有効投票の総数の八分の一
- 地方公共団体の議会議員選挙:有効投票の総数の十分の一
- 地方公共団体の長の選挙:有効投票の総数の十分の一
- 供託物の帰属先: 国庫または地方公共団体に帰属します。
- 取り下げや辞退の場合: 供託物没収の規定は、候補者の届出が取り下げられた場合や辞退した場合にも適用されます。
- 供託物の没収条件: 衆議院比例代表選挙で名簿届出政党の供託物が一定の基準に達しない場合、供託物が没収され、国庫に帰属します。
- 基準:
- 当選者の数を基に計算されます。
- 衆議院選挙では、小選挙区の当選者数と比例代表の当選者数を考慮します。
- 参議院選挙でも同様に、名簿登載者の当選者数が基準となります。
- 取り下げや却下の場合: 名簿が取り下げられた場合や却下された場合も、供託物は国庫に帰属します。
- 最多得票者の当選: 衆議院や参議院の比例代表選出議員以外の選挙では、有効投票の最多数を得た者が当選します。
- 最低得票基準:
- 衆議院小選挙区選出議員の選挙では、有効投票の総数の六分の一以上の得票が必要です。
- 参議院選挙区選出議員の選挙では、有効投票の総数の六分の一以上の得票が必要です。
- 地方公共団体の議会の議員の選挙では、有効投票の総数の四分の一以上の得票が必要です。
- 地方公共団体の長の選挙では、有効投票の総数の四分の一以上の得票が必要です。
- 同票の場合: 得票数が同じ場合は、選挙長がくじ引きで当選人を決定します。
- 当選人の数の計算: 衆議院比例代表選出議員の選挙では、各政党の得票数を1から順に各整数で除し、その商の中から大きい順に当選人数を決定します。
- 同数の場合: 商が同じ場合、くじ引きで当選人数を決定します。
- 順位が同じ場合: 同じ順位の場合、小選挙区選出議員の選挙の得票割合で順位を決定し、同じ場合はくじ引きで決定します。
- 当選人の決定: 名簿に記載された者のうち、順位に従い当選人数を決定します。
- 重複当選者の処理: 小選挙区選出議員の選挙で当選した者は比例代表名簿から除外されます。
- 有効票未達の場合: 小選挙区選出議員の選挙で一定数に達しなかった者も比例代表名簿から除外されます。
- 当選人の数の計算: 参議院比例代表選出議員の選挙では、各政党の得票数を1から順に各整数で除し、その商の中から大きい順に当選人数を決定します。
- 同数の場合: 商が同じ場合、くじ引きで当選人数を決定します。
- 順位が同じ場合: 同じ順位の場合、得票数の多い順に当選順位を決定し、得票数が同じ場合はくじ引きで決定します。
- 優先的候補者: 優先的に当選する候補者が名簿に記載されている場合、その候補者は他の候補者よりも上位に位置付けられます。
- 当選人の決定: 名簿に記載された者のうち、順位に従い当選人数を決定します。
- 異議や訴訟の結果: 異議の申出や訴訟の結果、再選挙を行わずに当選人を決定できる場合がある。
- 当選人の決定: 異議や訴訟の結果によっては、再選挙を行わずに当選人を定めるための選挙会が直ちに開かれる。
- 適用範囲: この規定は衆議院比例代表選出議員および参議院比例代表選出議員の選挙に関しても適用される。
- 当選人の繰上補充: 衆議院・参議院(比例代表選出)議員以外の選挙で当選人が死亡または当選を失った場合、次点の得票者から当選人を補充します。
- 適用条件: 参議院や地方議会の選挙で、選挙後3ヶ月以内に当選人が欠けた場合も同様に次点者から補充します。
- 地方公共団体の選挙: 地方公共団体の長の選挙でも次点者から当選人を補充します。
- 繰上補充の条件: 衆議院(比例代表選出)議員の選挙で当選人が死亡、当選無効または当選を失った場合に、次点者を当選人として補充します。
- 適用範囲: 参議院(比例代表選出)議員の選挙にも準用され、同様の条件で次点者から当選人を補充します。
- 手続き: 次点者の当選人は選挙会を開いて定め、衆議院名簿や参議院名簿の順位に基づいて決定します。
- 被選挙権の喪失: 選挙の期日後に被選挙権を失った場合、その者は当選人とすることができません。
- 犯罪による立候補資格の喪失: 組織的選挙運動管理者等の犯罪によって立候補資格を失った場合も、当選人とすることができません。
- 除名・離党の影響: 除名や離党などで政党に所属しなくなった場合、その者を当選人とすることができません。
- 届出の重要性: 当選無効や当選資格の喪失は、届出のタイミングが重要で、規定の事由が生じた日の前日までに届け出る必要があります。
- 当選後の資格喪失: 当選人が選挙の期日後に被選挙権を失った場合、その当選は無効となります。
- 被選挙権の喪失原因: 具体的な被選挙権の喪失原因は法律で定められており、例えば犯罪行為や重大な規則違反などが該当します。
- 公職の適格性の維持: この規定は、公職に就く者が適格性を維持するための重要な制度です。
- 政党移動による失格: 衆議院比例代表選出議員が選挙後に他の政党に所属した場合、当選が無効となります。
- 届け出義務: 所属政党の変更や離党があった場合、政党は直ちに選挙長に届け出る必要があります。
- 証明書類の添付: 除名や離党の場合、それを証明する書類を添付しなければなりません。
- 宣誓書の提出: 通知を受けた当選者は、他の政党に所属していないことを誓う宣誓書を提出する必要があります。
- 準用規定: 同様の規定が参議院比例代表選出議員の選挙にも適用されます。
- 無投票当選の条件: 一人しか候補者がいない場合や候補者数が議員定数を超えない場合、投票は行われません。
- 選挙管理委員会の対応: 投票が行われない場合、選挙長は通知と告示を行い、選挙管理委員会に報告します。
- 当選人の決定: 投票が行われない場合、選挙会を開き当選人を定めます。被選挙権の有無は選挙立会人の意見を聴いて決定されます。
- 報告義務: 当選人が決まった場合、選挙長は直ちに当選者の情報を都道府県の選挙管理委員会に報告します。
- 告知と告示: 都道府県の選挙管理委員会は当選者に当選の旨を告知し、当選者の情報を告示します。
- 比例代表選出議員の場合: 小選挙区選出議員と比例代表選出議員の選挙が同時に行われた場合、都道府県の選挙管理委員会は中央選挙管理会にも報告します。
- 中央選挙管理会の通知: 中央選挙管理会は直ちに比例代表選出議員の選挙区ごとの選挙長に報告内容を通知します。
- 報告義務: 衆議院比例代表選出議員の選挙で当選人が決まった場合、選挙長は中央選挙管理会に報告します。
- 告知と告示: 中央選挙管理会は直ちに当選者や政党に当選の旨を告知し、得票数や当選者の情報を告示します。
- 特別な場合: 第九十七条の二または第百十二条第二項に該当する場合、報告内容は当選者のみとなります。
- 報告義務: 参議院比例代表選出議員の選挙で当選者が決まった場合、選挙長は中央選挙管理会に報告します。
- 告知と告示: 中央選挙管理会は直ちに当選者や政党に当選の旨を告知し、得票数や当選者の情報を告示します。
- 特別な場合: 第九十七条の二または第百十二条第四項に該当する場合、報告内容は当選者のみとなります。
- 報告義務: 衆議院議員や参議院比例代表以外の選挙で当選者が決まった場合、選挙長は直ちに選挙管理委員会に報告します。
- 告知と告示: 選挙管理委員会は直ちに当選者に当選の旨を告知し、当選者の住所・氏名を告示します。
- 効力の発生: 当選人の当選の効力は、告示があった日から生じます。
- 比例代表選出議員の場合: 衆議院比例代表選出議員や参議院比例代表選出議員の選挙では、当選人数の決定の効力も含まれます。
- 適用規定: 第百一条第二項、第百一条の二第二項、第百一条の二の二第二項、及び前条第二項の規定による告示が該当します。
- 兼職禁止の職にある者: 当選人が兼職禁止の職にある場合、当選の告知を受けた日にその職を辞したとみなされます。
- 特例: 選挙管理委員会に5日以内に辞職を届け出なければ当選を失う特例もあります。
- 公務員の退職: 退職の申出をした公務員は、その申出の日に公務員を辞したとみなされます。
- 他の選挙への影響: 他の選挙で候補者となっている場合、当選の告知から5日以内に当選を辞する旨を届け出ないと、他の選挙の候補者資格も失うことになります。
- 関係を有する者: 地方自治法第九十二条の二または第百四十二条に規定する関係を有する者が該当します。
- 届出の義務: 当選の告知を受けた日から五日以内に、地方自治法に規定する関係を有しなくなった旨を届け出る必要があります。
- 失格の条件: 指定された期間内に届出をしない場合、当選が無効となります。
- 当選証書の付与: 当選の効力が生じた時点で、選挙管理委員会は当選人に対して当選証書を付与する義務があります。
- 例外規定: 第百三条第二項及び第四項、並びに第百四条に規定された場合を除きます。
- 特例の場合: 当選を失わなかった当選人には、必要な届出があった場合に当選証書を付与します。
- 当選人がいない場合: 当選人がいない場合、または当選人が議員の定数に満たない場合、選挙長はすぐに選挙管理委員会に報告しなければなりません。
- 告示の義務: 選挙管理委員会は、報告を受けた後、直ちにその旨を告示しなければなりません。
- 無効の告示: 選挙や当選が無効となった場合、選挙管理委員会はその旨を直ちに告示しなければなりません。
- 無効の事由: 第十五章の争訟、訴訟が提起されなかったこと、訴えや訴状が却下されたこと、訴訟の取り下げ、第二百五十一条の規定に基づく場合などが該当します。
- 報告対象: 選挙の結果について、選挙管理委員会は直ちに報告する必要があります。
- 報告先の区分:
- 衆議院議員、参議院議員、都道府県知事の選挙:総務大臣に報告。
- 都道府県議会の議員選挙:都道府県知事に報告。
- 市町村長の選挙:都道府県知事と都道府県選挙管理委員会に報告。
- 市町村議会の議員選挙:都道府県知事、都道府県選挙管理委員会、市町村長に報告。
- 総務大臣の義務: 衆議院議員または参議院議員の選挙に関する報告を受けた場合、内閣総理大臣に報告し、総理大臣は直ちに衆議院議長または参議院議長に報告する義務があります。
- 当選者がいない場合: 選挙結果で当選者がいないか、当選者数が議席の定数に満たない場合に再選挙が実施されます。
- 当選者が死亡した場合: 当選者が死亡した場合、その選挙区では再選挙が行われます。
- 当選資格喪失: 当選者が法律違反などにより当選資格を失った場合にも、再選挙が行われます。
- 異議や訴訟の結果: 異議申し立てや訴訟の結果、当選者が無効となり、定数に満たない場合は再選挙を実施します。
- 裁判による無効: 訴訟の結果、当選が無効とされた場合、再選挙が行われます。
- 比例代表選出議員の欠員が発生した場合: 欠員が定数の一定割合を超える場合、再選挙が行われます。
- 当選人が失職した場合: 当選した議員が訴訟や異議申し立ての結果、当選を失った場合にも再選挙が実施されます。
- 同時選挙が行われる場合: 比例代表選出議員や地方議会議員に関して、欠員が一定割合に満たない場合でも、他の選挙と同時に再選挙が行われることがあります。
- 国会議員の欠員通知: 衆議院・参議院の選挙区選出議員に欠員が生じた場合、内閣総理大臣が総務大臣を通じて、選挙管理委員会へ通知します。
- 比例代表選出議員の欠員通知: 衆議院・参議院の比例代表選出議員に欠員が生じた場合、同様に内閣総理大臣から通知が行われますが、中央選挙管理会へ通知されます。
- 地方議会議員の欠員通知: 地方議会議員に欠員が生じた場合、その地方議会の議長が選挙管理委員会に通知します。
- 地方公共団体の長の欠員通知: 地方公共団体の長が欠けた場合、その代理人が通知を行い、退職の申立てがあった場合も議長が通知します。
- 小選挙区選出議員の欠員: 欠員が生じた場合、当選に至らなかった候補者から繰上補充を行います。
- 比例代表選出議員の欠員: 名簿登載者から、順位に従って繰上補充を行います。
- 参議院や地方議会の欠員: 欠員が選挙後3ヶ月以内に発生した場合も同様に繰上補充を行います。
- 地方公共団体の長の欠員: 得票者から繰上補充が行われます。
- 小選挙区選出議員の補欠選挙: 欠員が1人に達した場合、補欠選挙を実施します。
- 比例代表選出議員の補欠選挙: 議員の欠員がその選挙区の定数の4分の1を超えた場合に補欠選挙を行います。
- 地方議会の補欠選挙: 欠員が特定数を超えた場合、補欠選挙が行われます。都道府県議会では2人以上、市町村議会では定数の6分の1を超えた場合です。
- 通知の受領: 第111条第三項に基づき、議会の定数が増加したことを通知された場合、都道府県や市町村の選挙管理委員会が対応します。
- 選挙期日の告示: 選挙管理委員会は、選挙の期日を決定し、増員選挙を実施することを義務づけられています。
- 参議院比例代表選出議員: 在任期間が異なる比例代表選出議員の選挙が行われる際、補欠選挙も同時に実施されます。
- 参議院選挙区選出議員: 同じ選挙区での再選挙や異なる在任期間の選挙が行われる際、補欠選挙が同時に実施されます。
- 地方公共団体の議会の議員: 同じ選挙区または区域で他の選挙が行われる場合、補欠選挙も同時に実施されます。
- 補欠選挙の期日: 第4項では、補欠選挙の期日は、同時に行われる選挙の期日に合わせて実施されることが定められています。これにより、選挙が効率的に行われ、追加の手続きが不要となります。
- 規定の準用: 第5項では、第110条第6項の規定が、地方公共団体の議会における補欠選挙にも適用されることが明記されています。これにより、地方選挙においても、欠員が生じた場合の対応が同様に行われることが保証されています。
- 欠員や退職の申立て: 地方公共団体の長が欠けた場合、またはその退職申立てがあった場合、選挙管理委員会は通知を受けて選挙の期日を告示し、選挙を行う義務があります。
- 例外規定: ただし、同一人に関して他の規定(第109条)に基づきすでに選挙の期日が告示されている場合は、再度の選挙実施は不要とされています。
- 参議院議員の選挙: 通常選挙、再選挙、補欠選挙を同時に行う場合は、これらの選挙を合併して一つの選挙として実施できます。
- 地方公共団体の議会の議員選挙: 同じ地方公共団体の再選挙、補欠選挙、増員選挙も合併して実施することが可能です。
- 在任期間の長い議員の優先: 当選者数を決める際、「選挙すべき議員の数」という表現は「在任期間の長い議員の数」と読み替えられます。つまり、比例代表選出議員の選挙においては、まず在任期間の長い議員の数を優先して決定します。
- 政党ごとの当選者数: 政党ごとに割り当てられた当選者数が、まず在任期間の長い議員の枠に適用されます。
- くじ引きによる決定: 第100条第3項の規定が適用される場合、くじ引きで各政党が割り当てられる在任期間の長い議員の当選者数や順位を決定します。
- 名簿に基づく順位決定: 政党ごとの名簿に記載された候補者の中から、くじ引きによって当選するべき順位が決まります。第95条の3第4項に基づく特定の名簿には例外があります。
- 優先的当選者の扱い: 第95条の3第4項に基づく参議院名簿届出政党等が提出した名簿において、優先的に当選者となるべき候補者は、他の候補者よりも上位の当選順位に設定されます。
- その他の候補者の順位決定: 優先順位が明確に定められていないその他の候補者については、くじ引きによって当選順位が決定されます。
- 当選順位に従った決定: 各政党の名簿に基づいて、当選者は名簿に記載された当選順位に従って決定されます。
- 在任期間の長い議員: 選挙結果に基づいて、在任期間が長い議員の当選者数をまず決定します。これらの議員は、名簿の中で上位に位置する候補者から順次選出されます。
- 得票数に基づく当選者決定: 得票者の中で最も多くの票を獲得した候補者から順に、在任期間の長い議員の当選者を決定します。
- 順次選出: 得票数の多い順に従い、在任期間が長い議員の当選者を選出していきます。
- くじ引きによる当選者決定: 第100条第4項の規定が適用される場合、得票数が同じで当選者を決定できない場合には、くじ引きによってどの候補者が在任期間の長い議員として当選するかを決定します。
- 準用規定: 第100条第9項で定められた規定は、在任期間の長い議員の選挙において、特に第3項と第7項に関連する当選者決定に適用されます。
- 公平な選挙手続き: この準用により、当選者の決定における公平性や手続きの一貫性が確保されます。
- 比例代表選出議員の場合: 在任期間の短い議員が繰上補充の対象となる場合、その者は名簿に基づいて、当選人となるべき順位に従って決定されます。
- 選挙区選出議員の場合: 在任期間の短い議員が繰上補充の対象となる場合、その者は選挙で選出された候補者の中から決定されます。
- 全ての議員や当選人が不在の場合: 第110条や第113条で規定される事由により、議会の全ての議員や当選人がいなくなった場合、選挙管理委員会は一般選挙を行うことが義務付けられています。
- 一般選挙の実施: 通常の補欠選挙では対応できない状況で、選挙の期日が告示され、議会を構成するための一般選挙が実施されます。
- 地方公共団体の設置: 新たに地方公共団体(都道府県や市町村)が設置された際に適用されます。
- 選挙の実施: 当該地方公共団体の議会の議員および長(市長や知事など)について、選挙管理委員会が選挙の期日を告示し、一般選挙と長の選挙を実施します。
- 同時選挙の実施: 都道府県議会議員の選挙と知事の選挙、または市町村議会議員の選挙と市町村長の選挙は、同時に実施できることが可能とされています。
- 選挙の同時実施の決定: 都道府県選挙管理委員会は、市町村選挙を都道府県選挙と同時に行うことを決定できます。これは、関連する届出や報告に基づいて決定されます。
- 選挙期日の告示: 同時選挙が行われる場合、その期日は都道府県選挙管理委員会によって正式に告示されます。
- 市町村の選挙管理委員会の届け出義務: 市町村の議会や長の選挙を実施する場合、市町村の選挙管理委員会は、任期満了による選挙では満了の60日前までに、任期満了以外の理由で選挙が必要な場合は、その事由が発生してから3日以内に都道府県の選挙管理委員会に届け出る必要があります。
- 告示の報告: 市町村が選挙の告示をした場合も、直ちに都道府県の選挙管理委員会に届け出なければなりません。
- 同時選挙の決定通知: 都道府県の選挙管理委員会は、届出や報告を受けてから3日以内に、市町村の選挙を都道府県の選挙と同時に行うかどうかを決定し、市町村に通知します。
- 施行の停止: 市町村の選挙は、都道府県との同時選挙に関する決定が通知されるまで、一時的に施行を停止されます。
- 例外規定: ただし、通知が指定の期間内(前条第3項の規定による3日間)にない場合には、選挙の施行が可能となります。
- 選挙管理委員会が決定: 同時選挙が行われる場合、どの順序で投票および開票を行うかは、選挙を管理する選挙管理委員会が決定します。
- 都道府県選挙管理委員会の権限: 第119条第2項に基づく場合は、都道府県の選挙管理委員会が投票および開票の順序を定めます。
- 投票・開票の適用: 同時に選挙が行われる場合、投票や開票に関する規定は、基本的に全ての選挙に通じて適用されます。ただし、第36条及び第62条に規定される事項は除かれます。
- 選挙会の規定の適用: 同一の選挙区域で同時に選挙が行われる場合、選挙会に関する規定も適用されますが、第76条に規定される事項は除かれます。
- 投票期日の決定: 通常、第56条に基づいて投票日が決定されますが、都道府県と市町村の選挙が同時に行われる場合は、その規定にかかわらず、都道府県の選挙管理委員会が投票日を定めることができます。
- 繰延投票の実施: 第57条第1項に基づく事由(災害や事故など)が発生した場合、都道府県の選挙管理委員会は、その規定に従い、さらに投票を行う必要があります。
- 市町村選挙管理委員会の義務: この場合、市町村の選挙管理委員会は、都道府県の選挙の選挙長を通じて、都道府県の選挙管理委員会に繰延投票が必要である旨を報告しなければなりません。
- 市町村長選挙の報告義務: 市町村長選挙で候補者が一人になった場合、市町村の選挙管理委員会は直ちに都道府県の選挙管理委員会に報告しなければなりません。
- 都道府県知事選挙との同時選挙: 都道府県知事選挙と市町村長選挙が同時に行われる場合、どちらかで候補者が一人になった場合、都道府県選挙管理委員会は選挙期日を延期し、7日以内に同時に選挙を行う必要があります。
- 政令で定める事項: 必要な詳細事項については政令により定められます。
- 無投票当選: 同時に選挙が行われる場合において、無投票当選となる条件(第100条第4項に規定する事由)が発生した場合、投票は行われません。
- 投票の省略: 候補者が定数を超えない場合など、無投票当選が確定した選挙については、実際に投票が行われることなく、当選者が決まります。
- 選挙運動の開始日: 選挙運動は、候補者や政党の名簿届出が行われた日から開始されます。具体的には、公職候補者の届出や名簿の届出が行われた日が基準となります。
- 選挙運動の終了日: 選挙運動は、選挙の期日の前日までしか行うことができません。当日や期日前投票の最中に選挙運動を行うことは禁止されています。
- 衆議院(小選挙区選出)議員の選挙: 公職の候補者またはその推薦届出者、および候補者届出政党に限り、選挙事務所を設置することができます。
- 衆議院(比例代表選出)議員の選挙: 衆議院名簿届出政党等のみが選挙事務所を設置できます。
- 参議院(比例代表選出)議員の選挙: 参議院名簿届出政党等および公職の候補者たる参議院名簿登載者が選挙事務所を設置できます。ただし、優先的に当選する候補者は除外されます。
- その他の選挙: 公職の候補者またはその推薦届出者が選挙事務所を設置可能です。
- 選挙事務所の設置届出: 選挙事務所を設置した際は、速やかにその旨を選挙管理委員会に届け出る必要があります。市町村の選挙以外の場合は、当該選挙事務所が設置された都道府県の選挙管理委員会にも届け出が必要です。
- 異動の際の届出: 事務所に変更や異動があった場合も、同様に届け出が求められます。
- 選挙事務所の数: 各候補者や政党が設置できる選挙事務所の数には上限があり、候補者一人または政党ごとに規定された数しか設置できません。
- 交通困難区域での例外: 交通が不便な地域では、特定の選挙では複数の選挙事務所を設置でき、衆議院小選挙区選出議員の場合は最大3箇所、参議院合同選挙区では最大10箇所まで設置可能です。
- 選挙ごとの制限:
- 衆議院小選挙区選出議員選挙:候補者1人につき1箇所、政党ごとに1選挙区につき1箇所
- 衆議院比例代表選出議員選挙:各都道府県ごとに1箇所
- 参議院比例代表選出議員選挙:各都道府県ごとに1箇所、候補者1人につき1箇所
- 参議院選挙区選出議員および都道府県知事選挙:候補者1人につき1箇所
- 地方議会議員や市町村長選挙:候補者1人につき1箇所
- 移動回数の制限: 各選挙事務所は、一日に一回以上移動(廃止して新しく設置することを含む)することができません。
- 公平性の維持: 選挙事務所の頻繁な移動を防ぐことで、選挙活動の公平性や一貫性を保つことが目的です。
- 標札の掲示義務: 衆議院や参議院の選挙事務所を設置した場合、その事務所の入口に選挙管理委員会が交付する標札を掲示する必要があります。
- 対象の選挙: 衆議院比例代表選出議員、参議院比例代表選出議員、参議院合同選挙区選挙などが対象となります。これらの選挙の事務所には、中央選挙管理会や選挙管理委員会が発行する標札を掲示します。
- 選挙当日の制限: 通常の選挙運動規定にかかわらず、選挙当日でも選挙事務所を設置することが許されます。
- 設置場所の制限: ただし、選挙事務所を設置できる場所は、投票所の入口から300メートル以上離れた場所に限られます。
- 休憩所の禁止: 選挙運動のために休憩所やそれに似た設備を設置することは一切許されていません。
- 公正な選挙環境の維持: これは、選挙運動において特定の候補者や政党が不正な利益を得ないようにするための措置です。
- 選挙事務所の違反設置: 第130条第1項や第131条第3項、第132条に違反する選挙事務所の設置が確認された場合、選挙管理委員会は直ちに閉鎖を命じる必要があります。
- 閉鎖命令の対象: 対象となる選挙は、衆議院比例代表選出議員、参議院比例代表選出議員、参議院合同選挙区などの選挙です。選挙管理委員会は、中央選挙管理会や都道府県の選挙管理委員会と連携して対処します。
- 定数超過の事務所: 第131条第1項に定められた数を超えて事務所が設置されている場合も、同様にその超過分の事務所に対して閉鎖命令が下されます。
- 選挙事務関係者の選挙運動禁止: 第88条に掲げられている選挙事務に関わる者は、在職中に自分の管轄区域内で選挙運動を行うことはできません。これにより、選挙事務に携わる立場を利用した不正が防止されます。
- 不在者投票管理者の選挙運動禁止: 不在者投票に関与する管理者は、その業務上の地位を使って選挙運動を行うことが禁じられています。これも、公正な選挙運営を確保するための措置です。
- 中央選挙管理会や選挙管理委員会の職員: 選挙に直接関与する職務を持つ公務員が選挙運動を行うことは禁止されています。
- 司法・捜査機関の職員: 裁判官、検察官、警察官など、司法や捜査に関わる職務を持つ者も、選挙運動を行うことができません。
- 会計・税務の公務員: 会計検査官や税務関連の公務員も、選挙運動を行うことが禁じられています。
- 公務員や特定の役職者の選挙運動禁止: 国や地方公共団体の公務員、行政執行法人、特定地方独立行政法人の役員や職員、沖縄振興開発金融公庫の役職員は、その地位を利用して選挙運動を行うことが禁止されています。
- 地位を利用した選挙運動の具体例:
- 候補者の推薦に関与すること、他者を推薦に関与させること
- 投票勧誘や選挙運動の計画に関与すること
- 新聞や刊行物を発行して選挙運動を行うこと
- 選挙運動に対する代償として利益を提供すること
- 対象となる教育者: 学校教育法に規定されている学校の教員や、幼保連携型認定こども園の長および教員が対象となります。
- 禁止事項: これらの教育者は、学校における教育的立場を利用して、児童や生徒、学生に対して選挙運動を行うことは禁じられています。
- 選挙運動の公平性を守る目的: 教育者がその地位を利用して特定の選挙活動を行うことを防ぎ、公正な選挙環境を確保することが目的です。
- 18歳未満の選挙運動の禁止: 18歳未満の者は、いかなる選挙運動にも参加することができません。
- 18歳未満の者の使用禁止: 他人が18歳未満の者を選挙運動に使用することも禁じられています。
- 例外: 労務に限っては、18歳未満の者を選挙運動のために使用することが認められています。ここでの労務とは、ビラ配りなどの単純作業が該当しますが、選挙運動そのものに関与することは認められません。
- 選挙権及び被選挙権を有しない者: 公職選挙法第252条や政治資金規正法第28条の規定に基づいて、選挙権や被選挙権を持たない者は、選挙運動に参加することができません。
- 対象者: 具体的には、刑事罰を受けて選挙権を失った者や、政治資金規正法に違反して権利を失った者などが該当します。
- 戸別訪問の禁止: 誰も、投票を得るために家々を訪問して選挙運動を行うことは許されていません。
- 演説会や特定候補者の告知も禁止: 戸別に訪問して、演説会の告知や特定の候補者や政党の名前を広めることも、この禁止行為に含まれます。
- 署名運動の禁止: 選挙に関して、誰も選挙人(有権者)に対して投票を得る、あるいは得させない目的で署名運動を行うことはできません。
- 選挙の公平性の確保: この規定は、署名活動によって特定の候補者や政党を支持する圧力をかけることを防ぎ、公正な選挙運動を維持するためのものです。
- 人気投票の禁止: 選挙に関連して、誰もが候補者や政党の人気投票の経過や結果を公表することは禁じられています。
- 対象となる人気投票: 衆議院比例代表選出議員選挙における政党やその人数、参議院比例代表選出議員選挙における政党の人数や公職に就くべき順位も対象です。
- 選挙への影響防止: 人気投票が選挙結果に不当な影響を与えないようにするための措置です。
- 飲食物提供の原則的禁止: 選挙運動の場で、どのような名目であっても飲食物を提供することは禁止されています。ただし、例外として湯茶や軽い菓子は許可されています。
- 特定の例外: 衆議院比例代表選出議員選挙を除く選挙において、選挙運動に従事する者や労務者には、政令で定められた額と数量の範囲内で弁当を提供することが認められています。この弁当提供は、選挙運動期間中に限られます。
- 提供できる範囲: 1候補者につき、選挙事務所での弁当提供は、日数や事務所数に応じた食数の上限が定められています。
- 気勢を張る行為の禁止: 自動車を連ねたり、隊伍を組んで街中を行進するなどの目立つ行動によって、選挙運動の場で「気勢を張る」(威勢を示す)行為を行うことは禁じられています。
- 選挙運動の公平性を保つための規制: この規定は、選挙運動が過度に目立ち、他者の選挙活動に不公平な影響を与えることを防ぐためのものです。
- 連呼行為の原則的禁止: 一般的に、候補者や政党名を連続して呼びかける「連呼行為」は選挙運動で禁止されています。
- 例外条件: 演説会場や街頭演説の場所で、または午前8時から午後8時の間に選挙運動用の自動車や船舶の上で行う連呼は許可されています。
- 特定施設周辺の静穏保持義務: 許可された場所でも、学校や病院の周辺では静かに配慮する義務があります。
- 使用できる車両や拡声機の制限: 各候補者が使用できる自動車や船舶、拡声機の数は選挙の種類に応じて制限されています。衆議院小選挙区選出議員や地方公共団体の選挙では、通常自動車1台、船舶1隻、拡声機1セットまでです。
- 参議院選挙の特例: 参議院比例代表選出議員の選挙では、自動車2台、船舶2隻、拡声機2セットまで使用が認められています。
- 個人演説会の例外: 個人演説会中の拡声機の追加使用は、会場に限り許可されています。
- 候補者数に応じた追加使用: 衆議院小選挙区選出議員選挙において、候補者届出政党が届け出た候補者が3人を超える場合、10人増えるごとに1台の自動車や1隻の船舶、および1そろいの拡声機を追加で使用することができます。
- 政党演説会における拡声機の使用: 政党演説会の会場に限っては、別に1そろいの拡声機を追加で使用することが可能です。
- 衆議院名簿登載者の数に応じた追加使用: 衆議院比例代表選出議員選挙では、衆議院名簿登載者が5人を超える場合、10人増すごとに自動車1台、船舶1隻、拡声機1そろいを追加で使用できます。
- 政党演説会の例外: 政党演説会に限り、会場内では別途1そろいの拡声機を使用することが認められています。
- 使用制限: 衆議院比例代表選出議員の選挙運動に使用できる自動車、船舶、拡声機は、第三項の規定に基づいて衆議院名簿届出政党等が使用するものに限られています。
- 他の機材の使用禁止: これ以外の車両や船舶、拡声機を使用することはできません。
- 表示義務: 選挙運動に使用される自動車や船舶、拡声機には、選挙管理委員会(中央選挙管理会や参議院合同選挙区選挙管理委員会が該当する場合もある)が定めた表示をしなければなりません。
- 表示の共通性: 自動車と船舶に関しては、共通の表示が用いられることが求められています。
- 使用可能な自動車の種類: 町村議会の議員や長の選挙以外では、政令で定める乗用車が選挙運動に使用できるとされています。
- 町村の選挙における例外: 町村の議会議員や町村長の選挙では、乗用車だけでなく、小型貨物車(小型自動車の規定に該当するもの)も使用することができます。
- 無料使用の範囲: 衆議院(小選挙区)や参議院議員の選挙で、公職候補者は政令で定める額内で自動車を無料で使用できます。
- 無料使用の条件: 衆議院(小選挙区)または参議院(選挙区)では、候補者が供託物を国庫に帰属しない場合に限り、無料利用が認められます。
- 比例代表選挙での制限: 参議院(比例代表選出)では、候補者が一定の当選順位にある場合のみ無料で利用できます。
- 地方公共団体の裁量: 地方公共団体は、自ら定めた条例に基づいて、公職候補者が選挙運動で使用する自動車を無料で利用できるようにすることが可能です。
- 範囲の制限: 参議院比例代表選出議員の選挙に関連する部分を除外しています。
公職選挙法 第22条(登録)
原文:
市町村の選挙管理委員会は、政令で定めるところにより、登録月の一日現在により、当該市町村の選挙人名簿に登録される資格を有する者を同日(同日が地方自治法第四条の二第一項の規定に基づき条例で定められた地方公共団体の休日(以下この項及び第二百七十条第一項において「地方公共団体の休日」という。)に当たる場合(当該市町村の区域の全部又は一部を含む区域において選挙が行われる場合において、登録月の一日が当該選挙の期日の公示又は告示の日から当該選挙の期日の前日までの間にあるときを除く。)には、登録月の一日又は同日の直後の地方公共団体の休日以外の日。以下この項において「通常の登録日」という。)に選挙人名簿に登録しなければならない。ただし、市町村の選挙管理委員会は、天災その他特別の事情がある場合には、政令で定めるところにより、登録の日を通常の登録日後に変更することができる。
2 前項の規定による登録は、当該市町村の区域の全部又は一部を含む区域において選挙が行われる場合において、登録月の一日が当該選挙の期日の公示又は告示の日から当該選挙の期日の前日までの間にあるとき(同項ただし書の規定により登録の日を当該選挙の期日後に変更する場合を除く。)には、同項本文の規定にかかわらず、登録月の一日現在(当該市町村の選挙人名簿に登録される資格のうち選挙人の年齢については、当該選挙の期日現在)により、行わなければならない。
3 市町村の選挙管理委員会は、選挙を行う場合には、政令で定めるところにより、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙については中央選挙管理会、参議院合同選挙区選挙については当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会)が定める日(以下この条において「選挙時登録の基準日」という。)現在(当該市町村の選挙人名簿に登録される資格のうち選挙人の年齢については、当該選挙の期日現在)により、当該市町村の選挙人名簿に登録される資格を有する者を当該選挙時登録の基準日に選挙人名簿に登録しなければならない。
4 第一項の規定による登録は、選挙時登録の基準日と登録月の一日とが同一の日となる場合には、行わない。
解説:
原文:
選挙人は、選挙人名簿の登録に関し不服があるときは、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める期間又は期日に、文書で当該市町村の選挙管理委員会に異議を申し出ることができる。
一 第二十二条第一項の規定による選挙人名簿の登録(当該市町村の区域の全部又は一部を含む区域において選挙が行われる場合において、登録月の一日が当該選挙の期日の公示又は告示の日から当該選挙の期日の前々日までの間にあるとき(同項ただし書の規定により登録の日を当該選挙の期日後に変更する場合を除く。)を除く。) 当該登録が行われた日の翌日から五日間
二 第二十二条第一項の規定による選挙人名簿の登録(当該市町村の区域の全部又は一部を含む区域において選挙が行われる場合において、登録月の一日が当該選挙の期日の公示又は告示の日から当該選挙の期日の前々日までの間にあるとき(同項ただし書の規定により登録の日を当該選挙の期日後に変更する場合を除く。)に限る。)及び同条第三項の規定による選挙人名簿の登録 当該登録が行われた日の翌日
2 市町村の選挙管理委員会は、前項の異議の申出を受けたときは、その異議の申出を受けた日から三日以内に、その異議の申出が正当であるかないかを決定しなければならない。その異議の申出を正当であると決定したときは、その異議の申出に係る者を直ちに選挙人名簿に登録し、又は選挙人名簿から抹消し、その旨を異議申出人及び関係人に通知し、併せてこれを告示しなければならない。その異議の申出を正当でないと決定したときは、直ちにその旨を異議申出人に通知しなければならない。
3 行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第九条第四項、第十九条第二項(第三号及び第五号を除く。)、第二十三条、第二十四条、第二十七条、第三十一条(第五項を除く。)、第三十二条第一項及び第三項、第三十九条、第四十一条第一項及び第二項、第四十四条並びに第五十三条の規定は、第一項の異議の申出について準用する。この場合において、これらの規定(同法第四十四条の規定を除く。)中「審理員」とあるのは「審査庁」と、同法第九条第四項中「審査庁」とあるのは「公職選挙法第二十四条第一項の異議の申出を受けた選挙管理委員会(以下「審査庁」という。)」と、同法第二十四条第一項中「第四十五条第一項又は第四十九条第一項の規定に基づき、裁決で」とあるのは「決定で」と、同法第三十一条第二項中「審理関係人」とあるのは「異議申出人」と、同法第四十四条中「行政不服審査会等から諮問に対する答申を受けたとき(前条第一項の規定による諮問を要しない場合(同項第二号又は第三号に該当する場合を除く。)にあっては審理員意見書が提出されたとき、同項第二号又は第三号に該当する場合にあっては同項第二号又は第三号に規定する議を経たとき)」とあるのは「審理手続を終結したとき」と読み替えるものとする。
4 第二百十四条の規定は、第一項の異議の申出について準用する。
解説:
公職選挙法 第25条(訴訟)
原文:
第二十五条 前条第二項の規定による決定に不服がある異議申出人又は関係人は、当該市町村の選挙管理委員会を被告として、決定の通知を受けた日から七日以内に出訴することができる。
2 前項の訴訟は、当該市町村の選挙管理委員会の所在地を管轄する地方裁判所の専属管轄とする。
3 前項の裁判所の判決に不服がある者は、控訴することはできないが、最高裁判所に上告することができる。
4 第二百十三条、第二百十四条及び第二百十九条第一項の規定は、第一項及び前項の訴訟について準用する。この場合において、同条第一項中「一の選挙の効力を争う数個の請求、第二百七条若しくは第二百八条の規定により一の選挙における当選の効力を争う数個の請求、第二百十条第二項の規定により公職の候補者であつた者の当選の効力を争う数個の請求、第二百十一条の規定により公職の候補者等であつた者の当選の効力若しくは立候補の資格を争う数個の請求又は選挙の効力を争う請求とその選挙における当選の効力に関し第二百七条若しくは第二百八条の規定によりこれを争う請求と」とあるのは、「一の第二十四条第一項各号に定める期間又は期日に異議の申出を行うことができる一の市町村の選挙管理委員会が行う選挙人名簿の登録に関し争う数個の請求」と読み替えるものとする。
解説:
公職選挙法 第26条(補正登録)
原文:
第二十六条 市町村の選挙管理委員会は、第二十二条第一項又は第三項の規定により選挙人名簿の登録をした日後、当該登録の際に選挙人名簿に登録される資格を有し、かつ、引き続きその資格を有する者が選挙人名簿に登録されていないことを知つた場合には、その者を直ちに選挙人名簿に登録し、その旨を告示しなければならない。
解説:
公職選挙法 第27条(表示及び訂正等)
原文:
第二十七条 市町村の選挙管理委員会は、選挙人名簿に登録されている者が第十一条第一項若しくは第二百五十二条若しくは政治資金規正法第二十八条の規定により選挙権を有しなくなつたこと又は当該市町村の区域内に住所を有しなくなつたことを知つた場合には、直ちに選挙人名簿にその旨の表示をしなければならない。
2 市町村の選挙管理委員会は、第二十一条第二項に規定する者を選挙人名簿に登録する場合には、同時に、選挙人名簿に同項の規定に該当する者である旨の表示をしなければならない。
3 市町村の選挙管理委員会は、選挙人名簿に登録されている者の記載内容(第十九条第三項の規定により磁気ディスクをもつて調製する選挙人名簿にあつては、記録内容)に変更があつたこと又は誤りがあることを知つた場合には、直ちにその記載(同項の規定により磁気ディスクをもつて調製する選挙人名簿にあつては、記録)の修正又は訂正をしなければならない。
解説:
公職選挙法 第28条(登録の抹消)
原文:
第二十八条 市町村の選挙管理委員会は、当該市町村の選挙人名簿に登録されている者について次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、これらの者を直ちに選挙人名簿から抹消しなければならない。この場合において、第四号に該当するに至つたときは、その旨を告示しなければならない。
一 死亡したこと又は日本の国籍を失つたことを知つたとき。
二 前条第一項又は第二項の表示をされた者が当該市町村の区域内に住所を有しなくなつた日後四箇月を経過するに至つたとき。
三 第三十条の六第二項の規定による第三十条の二第三項に規定する在外選挙人名簿への登録の移転をすることとするとき。
四 登録の際に登録されるべきでなかつたことを知つたとき。
解説:
公職選挙法 第28条の2(登録の確認及び政治活動を目的とした選挙人名簿の抄本の閲覧)
原文:
第二十八条の二 市町村の選挙管理委員会は、選挙の期日の公示又は告示の日から当該選挙の期日後五日に当たる日までの間を除き、次の表の上欄に掲げる活動を行うために、同表の中欄に掲げる者から選挙人名簿の抄本を閲覧することが必要である旨の申出があつた場合には、その活動に必要な限度において、それぞれ同表の下欄に掲げる者に選挙人名簿の抄本を閲覧させなければならない。この項前段に規定する期間(第二十四条第一項各号に定める期間又は期日に限る。)においても、特定の者が選挙人名簿に登録された者であるかどうかの確認を行うために、選挙人から当該申出があつた場合には、当該確認に必要な限度において、当該申出をした選挙人に選挙人名簿の抄本を閲覧させなければならない。
選挙人名簿の抄本の閲覧の申出をした政党その他の政治団体の役職員又は構成員で、当該政党その他の政治団体が指定するもの
2 前項の申出は、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を明らかにしてしなければならない。ただし、総務省令で定める場合には、第四号イに定める事項については、この限りでない。
一 選挙人名簿の抄本の閲覧の申出をする者(以下この条から第二十八条の四までにおいて「申出者」という。)の氏名及び住所(申出者が政党その他の政治団体である場合には、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
二 選挙人名簿の抄本の閲覧により知り得た事項(以下この条から第二十八条の四までにおいて「閲覧事項」という。)の利用の目的
三 選挙人名簿の抄本を閲覧する者(以下この条から第二十八条の四までにおいて「閲覧者」という。)の氏名及び住所
四 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める事項
イ 申出者が選挙人又は公職の候補者等である場合 閲覧事項の管理の方法
ロ 申出者が政党その他の政治団体である場合 閲覧事項の管理の方法及び当該政党その他の政治団体の役職員又は構成員のうち、閲覧事項を取り扱う者の範囲
五 前各号に掲げるもののほか、総務省令で定める事項
3 第一項の規定にかかわらず、市町村の選挙管理委員会は、閲覧事項を不当な目的に利用されるおそれがあること、閲覧事項を適切に管理することができないおそれがあることその他同項の申出に係る閲覧を拒むに足りる相当な理由があると認めるときは、当該申出に係る閲覧を拒むことができる。
4 公職の候補者等である申出者は、第二項第二号に掲げる利用の目的(以下この条から第二十八条の四までにおいて「利用目的」という。)を達成するために当該申出者及び閲覧者以外の者(当該申出者に使用される者に限る。)に閲覧事項を取り扱わせることが必要な場合には、第一項の申出をする際に、その旨並びに閲覧事項を取り扱う者として当該申出者が指定する者の氏名及び住所をその市町村の選挙管理委員会に申し出ることができる。
5 前項の規定による申出を受けた市町村の選挙管理委員会は、当該申出に相当な理由があると認めるときは、その申出を承認するものとする。この場合において、当該承認を受けた申出者は、当該申出者が指定した者(当該承認を受けた者に限る。第十二項及び第二十八条の四において「候補者閲覧事項取扱者」という。)にその閲覧事項を取り扱わせることができる。
6 政党その他の政治団体である申出者は、閲覧者及び第二項第四号ロに規定する範囲に属する者のうち当該申出者が指定するもの(第十二項及び第二十八条の四において「政治団体閲覧事項取扱者」という。)以外の者にその閲覧事項を取り扱わせてはならない。
7 政党その他の政治団体である申出者は、利用目的を達成するために当該申出者以外の法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この条から第二十八条の四までにおいて同じ。)に閲覧事項を取り扱わせることが必要な場合には、第一項の申出をする際に、当該法人についての次に掲げる事項を明らかにして、その旨をその市町村の選挙管理委員会に申し出ることができる。
一 法人の名称、代表者又は管理人の氏名及び主たる事務所の所在地
二 法人に閲覧事項を取り扱わせる事由
三 法人の役職員又は構成員のうち、閲覧事項を取り扱う者の範囲
四 法人の閲覧事項の管理の方法
五 前各号に掲げるもののほか、総務省令で定める事項
8 前項の規定による申出を受けた市町村の選挙管理委員会は、当該申出に相当な理由があると認めるときは、その申出を承認するものとする。この場合において、当該承認を受けた申出者は、第六項の規定にかかわらず、当該承認に係る法人(第十項から第十二項まで及び第二十八条の四において「承認法人」という。)にその閲覧事項を取り扱わせることができる。
9 前項の規定による承認を受けた政党その他の政治団体に対する第一項の規定の適用については、同項の表の下欄中「構成員」とあるのは、「構成員(第十項に規定する承認法人閲覧事項取扱者を含む。)」とする。
10 承認法人は、第七項第三号に掲げる範囲に属する者のうち当該承認法人が指定するもの(次項及び第二十八条の四において「承認法人閲覧事項取扱者」という。)以外の者にその閲覧事項を取り扱わせてはならない。
11 承認法人は、承認法人閲覧事項取扱者による閲覧事項の漏えいの防止その他の閲覧事項の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
12 申出者は、閲覧者、候補者閲覧事項取扱者、政治団体閲覧事項取扱者又は承認法人による閲覧事項の漏えいの防止その他の閲覧事項の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
解説:
公職選挙法 第28条の3(政治又は選挙に関する調査研究を目的とした選挙人名簿の抄本の閲覧)
原文:
第二十八条の三 市町村の選挙管理委員会は、前条第一項に定めるもののほか、統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究で公益性が高いと認められるもののうち政治又は選挙に関するものを実施するために選挙人名簿の抄本を閲覧することが必要である旨の申出があつた場合には、同項前段に規定する期間を除き、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者に、当該調査研究を実施するために必要な限度において、選挙人名簿の抄本を閲覧させなければならない。
一 申出者が国又は地方公共団体(以下この条及び次条において「国等」という。)の機関である場合 選挙人名簿の抄本の閲覧の申出をした国等の機関の職員で、当該国等の機関が指定するもの
二 申出者が法人である場合 選挙人名簿の抄本の閲覧の申出をした法人の役職員又は構成員(他の法人と共同して申出をする場合にあつては、当該他の法人の役職員又は構成員を含む。)で、当該法人が指定するもの
三 申出者が個人である場合 選挙人名簿の抄本の閲覧の申出をした個人又はその指定する者
2 前項の申出は、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を明らかにしてしなければならない。
一 申出者の氏名及び住所(申出者が国等の機関である場合にはその名称、申出者が法人である場合にはその名称、代表者又は管理人の氏名及び主たる事務所の所在地)
二 利用目的
三 閲覧者の氏名及び住所(申出者が国等の機関である場合には、その職名及び氏名)
四 閲覧事項を利用して実施する調査研究の成果の取扱い
五 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める事項
イ 申出者が法人である場合 閲覧事項の管理の方法及び当該法人の役職員又は構成員のうち、閲覧事項を取り扱う者の範囲
ロ 申出者が個人である場合 閲覧事項の管理の方法
六 前各号に掲げるもののほか、総務省令で定める事項
3 第一項の規定にかかわらず、市町村の選挙管理委員会は、閲覧事項を不当な目的に利用されるおそれがあること、閲覧事項を適切に管理することができないおそれがあることその他同項の申出に係る閲覧を拒むに足りる相当な理由があると認めるときは、当該申出に係る閲覧を拒むことができる。
4 法人である申出者は、閲覧者及び第二項第五号イに規定する範囲に属する者のうち当該申出者が指定するもの(第七項及び次条において「法人閲覧事項取扱者」という。)以外の者にその閲覧事項を取り扱わせてはならない。
5 個人である申出者は、利用目的を達成するために当該申出者及び閲覧者以外の者に閲覧事項を取り扱わせることが必要な場合には、第一項の申出をする際に、その旨並びに閲覧事項を取り扱う者として当該申出者が指定する者の氏名及び住所をその市町村の選挙管理委員会に申し出ることができる。
6 前項の規定による申出を受けた市町村の選挙管理委員会は、当該申出に相当な理由があると認めるときは、その申出を承認するものとする。この場合において、当該承認を受けた申出者は、当該申出者が指定した者(当該承認を受けた者に限る。次項及び次条において「個人閲覧事項取扱者」という。)にその閲覧事項を取り扱わせることができる。
7 申出者(国等の機関である申出者を除く。)は、閲覧者、法人閲覧事項取扱者又は個人閲覧事項取扱者による閲覧事項の漏えいの防止その他の閲覧事項の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
解説:
公職選挙法 第28条の4(選挙人名簿の抄本の閲覧に係る勧告及び命令等)
原文:
第二十八条の四 申出者、閲覧者、候補者閲覧事項取扱者、政治団体閲覧事項取扱者、承認法人、承認法人閲覧事項取扱者、法人閲覧事項取扱者又は個人閲覧事項取扱者は、本人の事前の同意を得ないで、当該閲覧事項を利用目的以外の目的のために利用し、又は当該閲覧事項に係る申出者、閲覧者、候補者閲覧事項取扱者、政治団体閲覧事項取扱者、承認法人、承認法人閲覧事項取扱者、法人閲覧事項取扱者及び個人閲覧事項取扱者以外の者に提供してはならない。
2 市町村の選挙管理委員会は、閲覧者若しくは申出者が偽りその他不正の手段により第二十八条の二第一項(同条第九項において読み替えて適用される場合を含む。第四項、第七項及び第八項において同じ。)若しくは前条第一項の規定による選挙人名簿の抄本の閲覧をし、若しくはさせた場合又は申出者、閲覧者、候補者閲覧事項取扱者、政治団体閲覧事項取扱者、承認法人、承認法人閲覧事項取扱者、法人閲覧事項取扱者若しくは個人閲覧事項取扱者が前項の規定に違反した場合において、個人の権利利益を保護するため必要があると認めるときは、当該閲覧事項に係る申出者、当該閲覧をし、若しくはさせた者又は当該違反行為をした者に対し、当該閲覧事項が利用目的以外の目的で利用され、又は当該閲覧事項に係る申出者、閲覧者、候補者閲覧事項取扱者、政治団体閲覧事項取扱者、承認法人、承認法人閲覧事項取扱者、法人閲覧事項取扱者及び個人閲覧事項取扱者以外の者に提供されないようにするための措置を講ずることを勧告することができる。
3 市町村の選挙管理委員会は、前項の規定による勧告を受けた者が正当な理由がなくてその勧告に係る措置を講じなかつた場合において、個人の権利利益が不当に侵害されるおそれがあると認めるときは、その者に対し、その勧告に係る措置を講ずることを命ずることができる。
4 市町村の選挙管理委員会は、前二項の規定にかかわらず、閲覧者若しくは申出者が偽りその他不正の手段により第二十八条の二第一項若しくは前条第一項の規定による選挙人名簿の抄本の閲覧をし、若しくはさせた場合又は申出者、閲覧者、候補者閲覧事項取扱者、政治団体閲覧事項取扱者、承認法人、承認法人閲覧事項取扱者、法人閲覧事項取扱者若しくは個人閲覧事項取扱者が第一項の規定に違反した場合において、個人の権利利益が不当に侵害されることを防止するため特に措置を講ずる必要があると認めるときは、当該閲覧事項に係る申出者、当該閲覧をし、若しくはさせた者又は当該違反行為をした者に対し、当該閲覧事項が利用目的以外の目的で利用され、又は当該閲覧事項に係る申出者、閲覧者、候補者閲覧事項取扱者、政治団体閲覧事項取扱者、承認法人、承認法人閲覧事項取扱者、法人閲覧事項取扱者及び個人閲覧事項取扱者以外の者に提供されないようにするための措置を講ずることを命ずることができる。
5 市町村の選挙管理委員会は、第二十八条の二からこの条までの規定の施行に必要な限度において、申出者に対し、必要な報告をさせることができる。
6 前各項の規定は、申出者が国等の機関である場合には、適用しない。
7 市町村の選挙管理委員会は、その定めるところにより、毎年少なくとも一回、第二十八条の二第一項及び前条第一項の申出に係る選挙人名簿の抄本の閲覧(総務省令で定めるものを除く。)の状況について、申出者の氏名(申出者が国等の機関である場合にあつてはその名称、申出者が法人である場合にあつてはその名称及び代表者又は管理人の氏名)及び利用目的の概要その他総務省令で定める事項を公表するものとする。
8 市町村の選挙管理委員会は、第二十八条の二第一項又は前条第一項の規定により閲覧させる場合を除いては、選挙人名簿の抄本を閲覧させてはならない。
解説:
公職選挙法 第29条(通報及び調査の請求)
原文:
第二十九条 市町村長及び市町村の選挙管理委員会は、選挙人の住所の有無その他選挙資格の確認に関し、その有している資料について相互に通報しなければならない。
2 選挙人は、選挙人名簿に脱漏、誤載又は誤記があると認めるときは、市町村の選挙管理委員会に選挙人名簿の修正に関し、調査の請求をすることができる。
解説:
これは、市町村長と選挙管理委員会が協力して正確な選挙人名簿を維持し、選挙人が誤りを修正する機会を提供することを目的としています。
公職選挙法 第30条(選挙人名簿の再調製)
原文:
第三十条 天災事変その他の事故により必要があるときは、市町村の選挙管理委員会は、更に選挙人名簿を調製しなければならない。
2 前項の選挙人名簿の調製の期日及び異議の申出期間その他その調製について必要な事項は、政令で定める。
解説:
この規定は、選挙人名簿が災害や事故で損なわれた場合でも、正確で最新の情報を保つための対策を確保することを目的としています。
第四章の二 在外選挙人名簿
公職選挙法 第30条の2(在外選挙人名簿)
原文:
第三十条の二 市町村の選挙管理委員会は、選挙人名簿のほか、在外選挙人名簿の調製及び保管を行う。
2 在外選挙人名簿は、永久に据え置くものとし、かつ、衆議院議員及び参議院議員の選挙を通じて一の名簿とする。
3 市町村の選挙管理委員会は、第三十条の五第一項の規定による申請に基づき在外選挙人名簿の登録を行い、及び同条第四項の規定による申請に基づき在外選挙人名簿への登録の移転(選挙人名簿から抹消すると同時に在外選挙人名簿の登録を行うことをいう。以下同じ。)を行うものとする。
4 在外選挙人名簿は、政令で定めるところにより、磁気ディスクをもつて調製することができる。
5 選挙を行う場合において必要があるときは、在外選挙人名簿の抄本(前項の規定により磁気ディスクをもつて在外選挙人名簿を調製している市町村の選挙管理委員会にあつては、当該在外選挙人名簿に記録されている全部若しくは一部の事項又は当該事項を記載した書類。第二百五十五条の四第一項第一号及び第二百七十条第一項第三号において同じ。)を用いることができる。
解説:
公職選挙法 第30条の3(在外選挙人名簿の記載事項等)
原文:
第三十条の三 在外選挙人名簿には、選挙人の氏名、最終住所(選挙人が国外へ住所を移す直前に住民票に記載されていた住所をいう。以下同じ。)又は申請の時(選挙人が第三十条の五第一項の規定による申請書を同条第二項に規定する領事官又は同項に規定する総務省令・外務省令で定める者に提出した時をいう。同条第一項及び第三項において同じ。)における本籍、性別及び生年月日等の記載(前条第四項の規定により磁気ディスクをもつて調製する在外選挙人名簿にあつては、記録)をしなければならない。
2 市町村の選挙管理委員会は、市町村の区域を分けて数投票区を設けた場合には、政令で定めるところにより、在外選挙人名簿を編製する一以上の投票区(以下「指定在外選挙投票区」という。)を指定しなければならない。
3 前二項に規定するもののほか、在外選挙人名簿の様式その他必要な事項は、政令で定める。
解説:
この条文は、在外選挙人が適切に選挙に参加できるようにするための手続きと方法を規定しています。
公職選挙法 第30条の4(在外選挙人名簿の被登録資格等)
原文:
第三十条の四 在外選挙人名簿の登録(在外選挙人名簿への登録の移転に係るものを除く。以下同じ。)は、在外選挙人名簿に登録されていない年齢満十八年以上の日本国民(第十一条第一項若しくは第二百五十二条又は政治資金規正法第二十八条の規定により選挙権を有しない者を除く。次項及び次条において同じ。)で、同条第一項の規定による申請がされ、かつ、在外選挙人名簿に関する事務についてその者の住所を管轄する領事官(領事官の職務を行う大使館若しくは公使館の長又はその事務を代理する者を含む。以下同じ。)の管轄区域(在外選挙人名簿に関する事務についての領事官の管轄区域として総務省令・外務省令で定める区域をいう。同項及び同条第三項第二号において同じ。)内に引き続き三箇月以上住所を有するものについて行う。
2 在外選挙人名簿への登録の移転は、在外選挙人名簿に登録されていない年齢満十八年以上の日本国民で最終住所の所在地の市町村の選挙人名簿に登録されている者のうち、次条第四項の規定による申請がされ、かつ、国外に住所を有するものについて行う。
解説:
この条文は、在外選挙人が適切に選挙に参加できるための条件と手続きを規定しています。
公職選挙法 第30条の5(在外選挙人名簿の登録の申請等)
原文:
第三十条の五 年齢満十八年以上の日本国民で、在外選挙人名簿に関する事務についてその者の住所を管轄する領事官の管轄区域内に住所を有するものは、政令で定めるところにより、文書で、最終住所の所在地の市町村の選挙管理委員会(その者が、いずれの市町村の住民基本台帳にも記録されたことがない者である場合には、申請の時におけるその者の本籍地の市町村の選挙管理委員会)に在外選挙人名簿の登録の申請をすることができる。
2 前項の規定による申請は、政令で定めるところにより、在外選挙人名簿に関する事務について当該申請をする者の住所を管轄する領事官(当該領事官を経由して当該申請をすることが著しく困難である地域として総務省令・外務省令で定める地域にあつては、総務省令・外務省令で定める者。以下この章において同じ。)を経由してしなければならない。
3 前項の場合において、領事官は、政令で定めるところにより、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める日以後速やかに、第一項の規定による申請書にその申請をした者に係る前条第一項に定める在外選挙人名簿に登録される資格(次条第一項及び第三十条の十三第二項において「在外選挙人名簿の被登録資格」という。)に関する意見を付して、当該申請をした者の最終住所の所在地の市町村の選挙管理委員会(当該申請をした者が、いずれの市町村の住民基本台帳にも記録されたことがない者である場合には、申請の時におけるその者の本籍地の市町村の選挙管理委員会)に送付しなければならない。
一 次号に掲げる場合以外の場合 当該申請の時の属する日
二 当該申請の時の属する日が当該申請書に当該領事官の管轄区域内に住所を有することとなつた日として記載された日から三箇月を経過していない場合 当該記載された日から三箇月を経過した日
4 年齢満十八年以上の日本国民で国外に転出をする旨の住民基本台帳法第二十四条の規定による届出(以下この項において「国外転出届」という。)がされた者のうち、当該国外転出届がされた市町村の選挙人名簿に登録されているもの(当該市町村の選挙人名簿に登録されていない者で、当該国外転出届に転出の予定年月日として記載された日までに、当該市町村の選挙人名簿に登録される資格を有することとなるものを含む。)は、政令で定めるところにより、同日までに、文書で、当該市町村の選挙管理委員会に在外選挙人名簿への登録の移転の申請をすることができる。
5 市町村の選挙管理委員会は、前項の規定による申請があつた場合には、政令で定めるところにより、外務大臣に対し、当該申請をした者(当該市町村の選挙人名簿から抹消された者を除く。次項において同じ。)の国外における住所に関する意見を求めなければならない。
6 外務大臣は、前項の規定により第四項の規定による申請をした者の国外における住所に関する意見を求められたときは、政令で定めるところにより、市町村の選挙管理委員会に対し、当該申請をした者の国外における住所に関する意見を述べなければならない。
解説:
この条文は、在外選挙人が選挙に参加するための申請手続きや必要な手続きを詳細に規定しています。
公職選挙法 第30条の6(在外選挙人名簿の登録等)
原文:
第三十条の六 市町村の選挙管理委員会は、前条第一項の規定による申請をした者が当該市町村における在外選挙人名簿の被登録資格を有する者である場合には、遅滞なく、当該申請をした者を在外選挙人名簿に登録しなければならない。
2 市町村の選挙管理委員会は、前条第四項の規定による申請をした者が当該市町村における第三十条の四第二項に定める在外選挙人名簿への登録の移転をされる資格(第三十条の十三第二項において「在外選挙人名簿の被登録移転資格」という。)を有する者である場合には、遅滞なく、当該申請をした者について在外選挙人名簿への登録の移転をしなければならない。
3 市町村の選挙管理委員会は、衆議院議員又は参議院議員の選挙の期日の公示又は告示の日から選挙の期日までの期間においては、前二項の規定にかかわらず、在外選挙人名簿の登録又は在外選挙人名簿への登録の移転を行わない。
4 市町村の選挙管理委員会は、第一項の規定による登録をしたときは、前条第三項の規定により同条第一項の規定による申請書を送付した領事官を経由して、同項の規定による申請をした者に、在外選挙人名簿に登録されている者であることの証明書(以下「在外選挙人証」という。)を交付しなければならない。
5 市町村の選挙管理委員会は、第二項の規定による在外選挙人名簿への登録の移転をしたときは、在外選挙人名簿に関する事務について前条第四項の規定による申請をした者の住所を管轄する領事官を経由して、当該申請をした者に、在外選挙人証を交付しなければならない。
解説:
この条文は、在外選挙人名簿に登録するための具体的な手続きや制約を定めています。
第三十条の七 削除
第三十条の七は削除されました。
公職選挙法 第30条の8(在外選挙人名簿の登録等に関する異議の申出)
原文:
第三十条の八 選挙人は、在外選挙人名簿の登録又は在外選挙人名簿への登録の移転に関し不服があるときは、これらに関する処分の直後に到来する次に掲げる期間又は期日に、文書で当該市町村の選挙管理委員会に異議を申し出ることができる。
一 第二十二条第一項の規定による選挙人名簿の登録が行われた日の翌日から五日間
二 衆議院議員又は参議院議員の選挙に係る第二十二条第三項の規定による選挙人名簿の登録が行われた日の翌日
2 市町村の選挙管理委員会は、前項の異議の申出を受けたときは、その異議の申出を受けた日から三日以内に、その異議の申出が正当であるかないかを決定しなければならない。その異議の申出を正当であると決定したときは、その異議の申出に係る者を直ちに在外選挙人名簿に登録し、若しくは在外選挙人名簿から抹消し、又はその者について在外選挙人名簿への登録の移転をし、若しくは在外選挙人名簿からの抹消と同時に選挙人名簿の登録(選挙人名簿の登録については、当該市町村の選挙人名簿に登録される資格を有する場合に限る。)をし、その旨を異議申出人及び関係人に通知し、併せてこれを告示しなければならない。その異議の申出を正当でないと決定したときは、直ちにその旨を異議申出人に通知しなければならない。
3 行政不服審査法第九条第四項、第十九条第二項(第三号及び第五号を除く。)、第二十三条、第二十四条、第二十七条、第三十一条(第五項を除く。)、第三十二条第一項及び第三項、第三十九条、第四十一条第一項及び第二項、第四十四条並びに第五十三条の規定は、第一項の異議の申出について準用する。この場合において、これらの規定(同法第四十四条の規定を除く。)中「審理員」とあるのは「審査庁」と、同法第九条第四項中「審査庁」とあるのは「公職選挙法第三十条の八第一項の異議の申出を受けた選挙管理委員会(以下「審査庁」という。)」と、同法第二十四条第一項中「第四十五条第一項又は第四十九条第一項の規定に基づき、裁決で」とあるのは「決定で」と、同法第三十一条第二項中「審理関係人」とあるのは「異議申出人」と、同法第四十四条中「行政不服審査会等から諮問に対する答申を受けたとき(前条第一項の規定による諮問を要しない場合(同項第二号又は第三号に該当する場合を除く。)にあっては審理員意見書が提出されたとき、同項第二号又は第三号に該当する場合にあっては同項第二号又は第三号に規定する議を経たとき)」とあるのは「審理手続を終結したとき」と読み替えるものとする。
4 第二百十四条の規定は、第一項の異議の申出について準用する。
解説:
この条文は、在外選挙人名簿の登録やその移転に関する異議申出の手続きや、申出後の対応方法を規定しています。
公職選挙法 第30条の9(在外選挙人名簿の登録等に関する訴訟)
原文:
第三十条の九 第二十五条第一項から第三項までの規定は、在外選挙人名簿の登録及び在外選挙人名簿への登録の移転に関する訴訟について準用する。この場合において、同条第一項中「前条第二項」とあるのは「第三十条の八第二項において準用する前条第二項」と、「七日」とあるのは「七日(政令で定める場合には、郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者、同条第九項に規定する特定信書便事業者若しくは同法第三条第四号に規定する外国信書便事業者による同法第二条第二項に規定する信書便による送付に要した日数を除く。)」と読み替えるものとする。
2 第二百十三条、第二百十四条及び第二百十九条第一項の規定は、前項において準用する第二十五条第一項及び第三項の訴訟について準用する。この場合において、第二百十九条第一項中「一の選挙の効力を争う数個の請求、第二百七条若しくは第二百八条の規定により一の選挙における当選の効力を争う数個の請求、第二百十条第二項の規定により公職の候補者であつた者の当選の効力を争う数個の請求、第二百十一条の規定により公職の候補者等であつた者の当選の効力若しくは立候補の資格を争う数個の請求又は選挙の効力を争う請求とその選挙における当選の効力に関し第二百七条若しくは第二百八条の規定によりこれを争う請求と」とあるのは、「一の第三十条の八第一項各号に掲げる期間又は期日に異議の申出を行うことができる一の市町村の選挙管理委員会が行う在外選挙人名簿の登録又は在外選挙人名簿への登録の移転に関し争う数個の請求」と読み替えるものとする。
解説:
この条文は、在外選挙人名簿の登録やその移転に関する訴訟の手続きを規定しています。
公職選挙法 第30条の10(在外選挙人名簿の表示及び訂正等)
原文:
第三十条の十 市町村の選挙管理委員会は、在外選挙人名簿に登録されている者が第十一条第一項若しくは第二百五十二条若しくは政治資金規正法第二十八条の規定により選挙権を有しなくなつたこと又は在外選挙人名簿に登録されている者に係る住民票が国内の市町村において新たに作成されたことを知つた場合には、直ちに在外選挙人名簿にその旨を表示しなければならない。
2 市町村の選挙管理委員会は、在外選挙人名簿に登録されている者の記載内容(第三十条の二第四項の規定により磁気ディスクをもつて調製する在外選挙人名簿にあつては、記録内容。第三十条の十四第一項において同じ。)に変更があつたこと又は誤りがあることを知つた場合には、直ちにその記載(第三十条の二第四項の規定により磁気ディスクをもつて調製する在外選挙人名簿にあつては、記録)の修正又は訂正をしなければならない。
解説:
この条文は、在外選挙人名簿の情報が常に正確で最新であることを保証するための規定です。
公職選挙法 第30条の11(在外選挙人名簿の登録の抹消)
原文:
第三十条の十一 市町村の選挙管理委員会は、当該市町村の在外選挙人名簿に登録されている者について次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、これらの者を直ちに在外選挙人名簿から抹消しなければならない。この場合において、第三号に該当するに至つたときは、その旨を告示しなければならない。
一 死亡したこと又は日本の国籍を失つたことを知つたとき。
二 前条第一項の表示をされた者について国内の市町村の区域内に住所を定めた年月日として戸籍の附票に記載された日後四箇月を経過するに至つたとき。
三 在外選挙人名簿の登録又は在外選挙人名簿への登録の移転の際に在外選挙人名簿の登録又は在外選挙人名簿への登録の移転をされるべきでなかつたことを知つたとき。
解説:
この規定は、在外選挙人名簿の正確性を保つための措置です。
公職選挙法 第30条の12(在外選挙人名簿の抄本の閲覧等)
原文:
第三十条の十二 第二十八条の二から第二十八条の四までの規定は、在外選挙人名簿について準用する。この場合において、第二十八条の二第一項中「第二十四条第一項各号に定める」とあるのは、「第三十条の八第一項各号に掲げる」と読み替えるものとする。
解説:
この規定により、在外選挙人名簿の管理が国内選挙人名簿と同じ基準で行われます。
公職選挙法 第30条の13(在外選挙人名簿の修正等に関する通知等)
原文:
第三十条の十三 市町村長は、その市町村に本籍を有する者で他の市町村の在外選挙人名簿に登録されているもの(以下この項において「他市町村在外選挙人名簿登録者」という。)について戸籍に関する届書、申請書その他の書類を受理し、若しくは職権で戸籍の記載をした場合又は戸籍の附票の記載、消除若しくは記載の修正をした場合において、当該他の市町村の選挙管理委員会において在外選挙人名簿の修正若しくは訂正をすべきこと若しくは当該他市町村在外選挙人名簿登録者を在外選挙人名簿から抹消すべきこと又は当該他市町村在外選挙人名簿登録者に係る住民票が国内の市町村において新たに作成されたことを知つたときは、遅滞なく、その旨を当該他の市町村の選挙管理委員会に通知しなければならない。
2 第二十九条の規定は、在外選挙人名簿の被登録資格及び在外選挙人名簿の被登録移転資格の確認に関する通報並びに在外選挙人名簿の修正に関する調査の請求について準用する。
解説:
この規定により、在外選挙人名簿の情報の正確性と最新性が保たれます。
公職選挙法 第30条の14(在外選挙人証交付記録簿の閲覧)
原文:
第三十条の十四 領事官は、特定の者が在外選挙人名簿に登録された者であるかどうかの確認をするために、選挙人から、当該領事官を経由して在外選挙人証を交付された者についてその登録されている在外選挙人名簿の属する市町村名及び当該登録されている者の氏名その他の在外選挙人名簿の記載内容に関する事項を記載した政令で定める文書(以下この条において「在外選挙人証交付記録簿」という。)を閲覧することが必要である旨の申出があつた場合には、当該申出をした選挙人に、その確認に必要な限度において、在外選挙人証交付記録簿を閲覧させなければならない。
2 前項の申出は、総務省令で定めるところにより、当該申出をする者の氏名及び住所その他総務省令で定める事項を明らかにしてしなければならない。
3 第一項の規定にかかわらず、領事官は、同項の規定による在外選挙人証交付記録簿の閲覧により知り得た事項(次項において「閲覧事項」という。)を不当な目的に利用されるおそれがあることその他第一項の申出に係る閲覧を拒むに足りる相当な理由があると認めるときは、当該申出に係る閲覧を拒むことができる。
4 第一項の規定により在外選挙人証交付記録簿を閲覧した者は、本人の事前の同意を得ないで、当該閲覧事項を特定の者が在外選挙人名簿に登録された者であるかどうかの確認をする目的以外の目的のために利用し、又は第三者に提供してはならない。
5 領事官は、第一項の規定により閲覧させる場合を除いては、在外選挙人証交付記録簿を閲覧させてはならない。
解説:
この規定により、在外選挙人証の確認が適正に行われるようになります。
公職選挙法 第30条の15(在外選挙人名簿の再調製)
原文:
第三十条の十五 第三十条の規定は、在外選挙人名簿の再調製について準用する。
解説:
この規定により、在外選挙人名簿の再調製についても国内の選挙人名簿の再調製と同様の手続きが適用されます。
公職選挙法 第30条の16(在外選挙人名簿の登録等に関する政令への委任)
原文:
第三十条の十六 第三十条の四から第三十条の六まで及び第三十条の八から前条までに規定するもののほか、在外選挙人名簿の登録及び在外選挙人名簿への登録の移転に関し必要な事項は、政令で定める。
解説:
この規定により、在外選挙人名簿の具体的な運用や手続きの詳細は、政府の政令によって定められることが明示されています。
第五章 選挙期日
公職選挙法 第31条(総選挙)
原文:
第三十一条 衆議院議員の任期満了に因る総選挙は、議員の任期が終る日の前三十日以内に行う。
2 前項の規定により総選挙を行うべき期間が国会開会中又は国会閉会の日から二十三日以内にかかる場合においては、その総選挙は、国会閉会の日から二十四日以後三十日以内に行う。
3 衆議院の解散に因る衆議院議員の総選挙は、解散の日から四十日以内に行う。
4 総選挙の期日は、少なくとも十二日前に公示しなければならない。
5 衆議院議員の任期満了に因る総選挙の期日の公示がなされた後その期日前に衆議院が解散されたときは、任期満了に因る総選挙の公示は、その効力を失う。
解説:
公職選挙法 第32条(通常選挙)
原文:
第三十二条 参議院議員の通常選挙は、議員の任期が終る日の前三十日以内に行う。
2 前項の規定により通常選挙を行うべき期間が参議院開会中又は参議院閉会の日から二十三日以内にかかる場合においては、通常選挙は、参議院閉会の日から二十四日以後三十日以内に行う。
3 通常選挙の期日は、少なくとも十七日前に公示しなければならない。
解説:
公職選挙法 第33条(一般選挙、長の任期満了に因る選挙及び設置選挙)
原文:
第三十三条 地方公共団体の議会の議員の任期満了に因る一般選挙又は長の任期満了に因る選挙は、その任期が終る日の前三十日以内に行う。
2 地方公共団体の議会の解散に因る一般選挙は、解散の日から四十日以内に行う。
3 地方公共団体の設置による議会の議員の一般選挙及び長の選挙は、地方自治法第六条の二第四項又は第七条第七項の告示による当該地方公共団体の設置の日から五十日以内に行う。
4 地方公共団体の議会の議員の任期満了に因る一般選挙の期日の告示がなされた後その任期の満了すべき日前に当該地方公共団体の議会の議員がすべてなくなつたとき、又は地方公共団体の長の任期満了に因る選挙の期日の告示がなされた後その任期の満了すべき日前に当該地方公共団体の長が欠け、若しくは退職を申し出たときは、更にこれらの事由に因る選挙の告示は、行わない。但し、任期満了に因る選挙の期日前に当該地方公共団体の議会が解散されたとき、又は長が解職され、若しくは不信任の議決に因りその職を失つたときは、任期満了に因る選挙の告示は、その効力を失う。
5 第一項から第三項までの選挙の期日は、次の各号の区分により、告示しなければならない。
一 都道府県知事の選挙にあつては、少なくとも十七日前に
二 指定都市の長の選挙にあつては、少なくとも十四日前に
三 都道府県の議会の議員及び指定都市の議会の議員の選挙にあつては、少なくとも九日前に
四 指定都市以外の市の議会の議員及び長の選挙にあつては、少なくとも七日前に
五 町村の議会の議員及び長の選挙にあつては少なくとも五日前に
解説:
公職選挙法 第33条の2(衆議院議員及び参議院議員の再選挙及び補欠選挙)
原文:
第三十三条の二 衆議院議員及び参議院議員の第百九条第一号に掲げる事由による再選挙は、これを行うべき事由が生じた日から四十日以内に、衆議院議員及び参議院議員の同条第四号に掲げる事由による再選挙(選挙の無効による再選挙に限る。)は、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙については中央選挙管理会、参議院合同選挙区選挙については当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会)が第二百二十条第一項後段の規定による通知を受けた日から四十日以内に行う。
2 衆議院議員及び参議院議員の再選挙(前項に規定する再選挙を除く。以下「統一対象再選挙」という。)又は補欠選挙は、九月十六日から翌年の三月十五日まで(以下この条において「第一期間」という。)にこれを行うべき事由が生じた場合は当該期間の直後の四月の第四日曜日に、三月十六日からその年の九月十五日まで(以下この条において「第二期間」という。)にこれを行うべき事由が生じた場合は当該期間の直後の十月の第四日曜日に行う。
3 衆議院議員の統一対象再選挙又は補欠選挙は、参議院議員の任期が終わる年において第二期間の初日から参議院議員の任期が終わる日の五十四日前の日(その日後に国会が開会されていた場合は、当該通常選挙の期日の公示の日の直前の国会閉会の日)までにこれを行うべき事由が生じた場合は、前項の規定にかかわらず、当該通常選挙の期日に行う。
4 参議院議員の統一対象再選挙又は補欠選挙は、在任期間を異にする参議院議員の任期が終わる年において第二期間の初日から通常選挙の期日の公示がなされるまでにこれを行うべき事由が生じた場合は、第二項の規定にかかわらず、当該通常選挙の期日に行う。
5 参議院議員の統一対象再選挙又は補欠選挙は、次の各号の区分による選挙が行われるときにおいて当該選挙の期日の告示がなされるまでにこれを行うべき事由が生じた場合は、第二項及び前項の規定にかかわらず、次の各号の区分による選挙の期日に行う。
一 比例代表選出議員の場合には、在任期間を異にする比例代表選出議員の第一項に規定する再選挙(選挙の一部無効による再選挙を除く。)が行われるとき。
二 選挙区選出議員の場合には、当該選挙区において在任期間を同じくする選挙区選出議員の第一項に規定する再選挙(当選人がその選挙における議員の定数に達しないことによる再選挙に限る。)又は在任期間を異にする選挙区選出議員の同項に規定する再選挙(選挙の一部無効による再選挙を除く。)が行われるとき。
6 衆議院議員及び参議院議員の再選挙(統一対象再選挙を除く。)は、当該議員の任期(参議院議員については在任期間を同じくするものの任期をいう。以下この項において同じ。)が終わる前六月以内にこれを行うべき事由が生じた場合は行わず、衆議院議員及び参議院議員の統一対象再選挙又は補欠選挙は、当該議員の任期が終わる日の六月前の日が属する第一期間又は第二期間の初日以後これを行うべき事由が生じた場合は行わない。
7 衆議院議員及び参議院議員の再選挙又は補欠選挙は、その選挙を必要とするに至つた選挙についての第二百四条又は第二百八条の規定による訴訟の出訴期間又は訴訟が係属している間は、行うことができない。この場合において、これらの期間に第一項又は第二項に規定する事由が生じた選挙についての前各項の規定の適用については、第一項中「これを行うべき事由が生じた日」とあるのは「第二百四条若しくは第二百八条に規定する出訴期間の経過又は当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙については中央選挙管理会、参議院合同選挙区選挙については当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会)の第二百二十条第一項後段の規定による通知の受領のうちいずれか遅い方の事由が生じた日」と、第二項から前項までの規定中「これを行うべき事由が生じた場合」とあるのは「第二百四条若しくは第二百八条に規定する出訴期間の経過又はこれらの規定による訴訟が係属しなくなつたことのうちいずれか遅い方の事由が生じた場合」とする。
8 衆議院議員及び参議院議員の再選挙及び補欠選挙の期日は、特別の定めがある場合を除くほか、次の各号の区分により、告示しなければならない。
一 衆議院議員の選挙にあつては、少なくとも十二日前に
二 参議院議員の選挙にあつては、少なくとも十七日前に
解説:
この条文は、衆議院議員および参議院議員の再選挙および補欠選挙の実施に関する詳細な規定を定めています。
公職選挙法 第34条(地方公共団体の議会の議員及び長の再選挙、補欠選挙等)
原文:
第三十四条 地方公共団体の議会の議員及び長の再選挙、補欠選挙(第百十四条の規定による選挙を含む。)又は増員選挙若しくは第百十六条の規定による一般選挙は、これを行うべき事由が生じた日から五十日以内に行う。
2 前項に掲げる選挙のうち、第百九条、第百十条又は第百十三条の規定による地方公共団体の議会の議員の再選挙、補欠選挙又は増員選挙は、当該議員の任期が終わる前六月以内にこれを行うべき事由が生じた場合は行わない。ただし、議員の数がその定数の三分の二に達しなくなつたときは、この限りでない。
3 第一項に掲げる選挙は、その選挙を必要とするに至つた選挙についての第二百二条若しくは第二百六条の規定による異議の申出期間、第二百二条若しくは第二百六条の規定による異議の申出に対する決定若しくは審査の申立てに対する裁決が確定しない間又は第二百三条若しくは第二百七条の規定による訴訟が係属している間(次項及び第五項において「争訟係属等期間」と総称する。)は、行うことができない。
4 第一項に掲げる選挙のうち、次の各号に掲げる選挙についての同項の規定の適用については、同項中「これを行うべき事由が生じた日」とあるのは、当該各号に定める日(第二号から第六号までに定める日が争訟係属等期間にあるときは、第一号に定める日)に読み替えるものとする。
一 その選挙を必要とするに至つた選挙についての争訟係属等期間にこれを行うべき事由が生じた選挙 第二百二条若しくは第二百六条に規定する異議の申出期間の経過、第二百二条若しくは第二百六条に規定する異議の申出に対する決定若しくは審査の申立てに対する裁決の確定又は当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会の第二百二十条第一項後段の規定による通知の受領のうち最も遅い事由が生じた日
二 第百九条第五号に掲げる事由による再選挙 当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会が第二百二十条第二項の規定による通知を受領した日(第二百十条第一項の規定による訴訟が提起されなかつたことに係るものによる再選挙にあつては、同項に規定する出訴期間が経過した日)
三 第百九条第六号に掲げる事由による再選挙 当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会が第二百五十四条の規定による通知を受領した日
四 補欠選挙又は増員選挙(前二号の規定の適用がある場合を除く。) 当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会が最後に第百十一条第一項又は第三項の規定による通知を受領した日
五 第百十四条の規定による選挙 当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会が第百十一条第一項第四号の規定による通知を受領した日
六 第百十六条の規定による一般選挙 第二号から第四号までに定める日のうち最も遅い日
5 地方公共団体の議会の議員の再選挙、補欠選挙又は増員選挙のうち、その選挙を必要とするに至つた選挙についての争訟係属等期間に第二項に規定する事由が生じた選挙についての同項の規定の適用については、同項中「これを行うべき事由が生じた場合」とあるのは、「第二百二条若しくは第二百六条に規定する異議の申出期間の経過、第二百二条若しくは第二百六条に規定する異議の申出に対する決定若しくは審査の申立てに対する裁決の確定又は第二百三条若しくは第二百七条の規定による訴訟が係属しなくなつたことのうち最も遅い事由が生じた場合」とする。
6 第一項の選挙の期日は、特別の定めがある場合を除くほか、次の各号の区分により、告示しなければならない。
一 都道府県知事の選挙にあつては、少なくとも十七日前に
二 指定都市の長の選挙にあつては、少なくとも十四日前に
三 都道府県の議会の議員及び指定都市の議会の議員の選挙にあつては、少なくとも九日前に
四 指定都市以外の市の議会の議員及び長の選挙にあつては、少なくとも七日前に
五 町村の議会の議員及び長の選挙にあつては、少なくとも五日前に
解説:
公職選挙法 第34条の2(地方公共団体の議会の議員及び長の任期満了による選挙の期日の特例)
原文:
第三十四条の二 地方公共団体の議会の議員の任期満了の日が当該地方公共団体の長の任期満了の日前九十日に当たる日から長の任期満了の日の前日までの間にある場合において当該地方公共団体の議会の議員の任期満了による一般選挙と長の任期満了による選挙を第百十九条第一項の規定により同時に行おうとするときは、第三十三条第一項の規定にかかわらず、これらの選挙は、当該地方公共団体の長の任期満了の日前五十日に当たる日又は当該地方公共団体の議会の議員の任期満了の日前三十日に当たる日のいずれか遅い日から当該地方公共団体の議会の議員の任期満了の日後五十日に当たる日又は当該地方公共団体の長の任期満了の日のいずれか早い日までの間に行うことができる。
2 都道府県の選挙管理委員会又は市町村の選挙管理委員会は、前項の規定により選挙を行おうとする場合には、当該地方公共団体の議会の議員の任期満了の日前六十日までにその旨を告示しなければならない。
3 第三十三条第一項及び第一項の規定にかかわらず、前項の規定による告示がなされた後当該地方公共団体の長の任期満了による選挙の期日の告示がなされるまでに当該地方公共団体の議会の議員が任期満了以外の事由によりすべてなくなつた場合(当該地方公共団体の議会の議員の任期満了による一般選挙の期日の告示がなされている場合(第三十三条第四項ただし書の規定の適用がある場合を除く。)を除く。)における当該地方公共団体の長の任期満了による選挙は、当該地方公共団体の長の任期満了の日前五十日に当たる日又は当該地方公共団体の議会の議員の任期が満了することとされていた日前三十日に当たる日のいずれか遅い日から当該地方公共団体の長の任期満了の日までの間に行い、前項の規定による告示がなされた後当該地方公共団体の議会の議員の任期満了による一般選挙の期日の告示がなされるまでに当該地方公共団体の長が欠け、又は退職を申し出た場合(当該地方公共団体の長の任期満了による選挙の期日の告示がなされている場合(第三十三条第四項ただし書の規定の適用がある場合を除く。)を除く。)における当該地方公共団体の議会の議員の任期満了による一般選挙は、当該地方公共団体の議会の議員の任期満了の日前三十日に当たる日から当該地方公共団体の議会の議員の任期満了の日後五十日に当たる日又は当該地方公共団体の長の任期が満了することとされていた日までの間に行う。
4 前三項の規定は、地方公共団体の長の任期満了の日が当該地方公共団体の議会の議員の任期満了の日前九十日に当たる日から議員の任期満了の日の前日までにある場合について、準用する。この場合において、第一項中「長の任期満了の日前五十日」とあるのは「議会の議員の任期満了の日前五十日」と、「議会の議員の任期満了の日前三十日」とあるのは「長の任期満了の日前三十日」と、「議会の議員の任期満了の日後五十日」とあるのは「長の任期満了の日後五十日」と、「当該地方公共団体の長の任期満了の日の」とあるのは「当該地方公共団体の議会の議員の任期満了の日の」と、第二項中「前項」とあるのは「第四項において準用する前項」と、「議会の議員の任期満了の日」とあるのは「長の任期満了の日」と、前項中「第一項の」とあるのは「次項において準用する第一項の」と、「前項」とあるのは「次項において準用する前項」と、「長の任期満了による選挙」とあるのは「議会の議員の任期満了による一般選挙」と、「議会の議員が任期満了以外の事由によりすべてなくなつた」とあるのは「長が任期満了以外の事由により欠け、又は退職を申し出た」と、「議会の議員の任期満了による一般選挙」とあるのは「長の任期満了による選挙」と、「長の任期満了の日」とあるのは「議会の議員の任期満了の日」と、「議会の議員の任期が満了することとされていた日」とあるのは「長の任期が満了することとされていた日」と、「長が欠け、又は退職を申し出た」とあるのは「議会の議員がすべてなくなつた」と、「議会の議員の任期満了の日」とあるのは「長の任期満了の日」と、「長の任期が満了することとされていた日」とあるのは「議会の議員の任期が満了することとされていた日」と読み替えるものとする。
5 第三十三条第五項の規定は、第一項又は第三項(これらの規定を前項において準用する場合を含む。)の規定により行われる選挙について、準用する。
解説:
第六章 投票
公職選挙法 第35条(選挙の方法)
原文:
第三十五条 選挙は、投票により行う。
解説:
公職選挙法 第36条(一人一票)
原文:
第三十六条 投票は、各選挙につき、一人一票に限る。ただし、衆議院議員の選挙については小選挙区選出議員及び比例代表選出議員ごとに、参議院議員の選挙については選挙区選出議員及び比例代表選出議員ごとに一人一票とする。
解説:
公職選挙法 第37条(投票管理者)
原文:
第三十七条 各選挙ごとに、投票管理者を置く。
2 投票管理者は、選挙権を有する者の中から市町村の選挙管理委員会の選任した者をもつて、これに充てる。
3 衆議院議員の選挙において、小選挙区選出議員の選挙と比例代表選出議員の選挙を同時に行う場合においては、市町村の選挙管理委員会は、小選挙区選出議員についての投票管理者を同時に比例代表選出議員についての投票管理者とすることができる。
4 参議院議員の選挙において、選挙区選出議員の選挙と比例代表選出議員の選挙を同時に行う場合においては、市町村の選挙管理委員会は、選挙区選出議員についての投票管理者を同時に比例代表選出議員についての投票管理者とすることができる。
5 投票管理者は、投票に関する事務を担任する。
6 投票管理者は、選挙権を有しなくなつたときは、その職を失う。
7 市町村の選挙管理委員会は、市町村の区域を分けて数投票区を設けた場合には、政令で定めるところにより一以上の投票区を指定し、当該指定した投票区の投票管理者に、政令で定めるところにより、当該投票区以外の投票区に属する選挙人がした第四十九条の規定による投票に関する事務のうち政令で定めるものを行わせることができる。
解説:
公職選挙法 第38条(投票立会人)
原文:
第三十八条 市町村の選挙管理委員会は、各選挙ごとに、選挙権を有する者の中から、本人の承諾を得て、二人以上五人以下の投票立会人を選任し、その選挙の期日前三日までに、本人に通知しなければならない。
2 投票立会人で参会する者が投票所を開くべき時刻になつても二人に達しないとき又はその後二人に達しなくなつたときは、投票管理者は、選挙権を有する者の中から二人に達するまでの投票立会人を選任し、直ちにこれを本人に通知し、投票に立ち会わせなければならない。
3 当該選挙の公職の候補者は、これを投票立会人に選任することができない。
4 同一の政党その他の政治団体に属する者は、一の投票区において、二人以上を投票立会人に選任することができない。
5 投票立会人は、正当な理由がなければ、その職を辞することができない。
解説:
公職選挙法 第39条(投票所)
原文:
第三十九条 投票所は、市役所、町村役場又は市町村の選挙管理委員会の指定した場所に設ける。
解説:
公職選挙法 第40条(投票所の開閉時間)
原文:
第四十条 投票所は、午前七時に開き、午後八時に閉じる。ただし、市町村の選挙管理委員会は、選挙人の投票の便宜のため必要があると認められる特別の事情のある場合又は選挙人の投票に支障を来さないと認められる特別の事情のある場合に限り、投票所を開く時刻を二時間以内の範囲内において繰り上げ若しくは繰り下げ、又は投票所を閉じる時刻を四時間以内の範囲内において繰り上げることができる。
2 市町村の選挙管理委員会は、前項ただし書の場合においては、直ちにその旨を告示するとともに、これをその投票所の投票管理者に通知し、かつ、市町村の議会の議員又は長の選挙以外の選挙にあつては、直ちにその旨を都道府県の選挙管理委員会に届け出なければならない。
解説:
公職選挙法 第41条(投票所の告示)
原文:
第四十一条 市町村の選挙管理委員会は、選挙の期日から少くとも五日前に、投票所を告示しなければならない。
2 天災その他避けることのできない事故に因り前項の規定により告示した投票所を変更したときは、選挙の当日を除く外、市町村の選挙管理委員会は、前項の規定にかかわらず、直ちにその旨を告示しなければならない。
解説:
公職選挙法 第41条の2(共通投票所)
原文:
第四十一条の二 市町村の選挙管理委員会は、選挙人の投票の便宜のため必要があると認める場合(当該市町村の区域を分けて数投票区を設けた場合に限る。)には、投票所のほか、その指定した場所に、当該市町村の区域内(衆議院小選挙区選出議員の選挙若しくは都道府県の議会の議員の選挙において当該市町村が二以上の選挙区に分かれているとき、又は第十五条第六項の規定による選挙区があるときは、当該市町村の区域内における当該選挙区の区域内)のいずれの投票区に属する選挙人も投票をすることができる共通投票所を設けることができる。
2 市町村の選挙管理委員会は、前項の規定により共通投票所を設ける場合には、投票所において投票をした選挙人が共通投票所において投票をすること及び共通投票所において投票をした選挙人が投票所又は他の共通投票所において投票をすることを防止するために必要な措置を講じなければならない。
3 天災その他避けることのできない事故により、共通投票所において投票を行わせることができないときは、市町村の選挙管理委員会は、当該共通投票所を開かず、又は閉じるものとする。
4 市町村の選挙管理委員会は、前項の規定により共通投票所を開かず、又は閉じる場合には、直ちにその旨を告示しなければならない。
5 第一項の規定により共通投票所を設ける場合における次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
6 前二条及び第五十八条から第六十条までの規定は、共通投票所について準用する。この場合において、第四十条第一項ただし書中「選挙人の投票の便宜のため必要があると認められる特別の事情のある場合又は選挙人の投票に支障を来さないと認められる特別の事情のある場合に限り」とあるのは「必要があると認めるときは」と、「若しくは」とあるのは「若しくは当該時刻を」と、「時刻を四時間以内の範囲内において」とあるのは「時刻を」と読み替えるものとする。
7 第一項の規定により共通投票所を設ける場合において、第五十六条又は第五十七条第一項の規定により投票の期日を定めたときにおける次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
8 前各項に定めるもののほか、共通投票所に関し必要な事項は、政令で定める。
解説:
公職選挙法 第42条(選挙人名簿又は在外選挙人名簿の登録と投票)
原文:
第四十二条 選挙人名簿又は在外選挙人名簿に登録されていない者は、投票をすることができない。ただし、選挙人名簿に登録されるべき旨の決定書又は確定判決書を所持し、選挙の当日投票所に至る者があるときは、投票管理者は、その者に投票をさせなければならない。
2 選挙人名簿又は在外選挙人名簿に登録された者であつても選挙人名簿又は在外選挙人名簿に登録されることができない者であるときは、投票をすることができない。
解説:
公職選挙法 第43条(選挙権のない者の投票)
原文:
第四十三条 選挙の当日(第四十八条の二の規定による投票にあつては、投票の当日)、選挙権を有しない者は、投票をすることができない。
解説:
公職選挙法 第44条(投票所における投票)
原文:
第四十四条 選挙人は、選挙の当日、自ら投票所に行き、投票をしなければならない。
2 選挙人は、選挙人名簿又はその抄本(当該選挙人名簿が第十九条第三項の規定により磁気ディスクをもつて調製されている場合には、当該選挙人名簿に記録されている全部若しくは一部の事項又は当該事項を記載した書類。次項、第五十五条及び第五十六条において同じ。)の対照を経なければ、投票をすることができない。
3 第九条第三項の規定により都道府県の議会の議員及び長の選挙権を有する者が、従前住所を有していた現に選挙人名簿に登録されている市町村において当該都道府県の議会の議員又は長の選挙の投票をする場合には、前項の選挙人名簿又はその抄本の対照を経る際に、引き続き当該都道府県の区域内に住所を有することを証するに足りる文書を提示し、又は引き続き当該都道府県の区域内に住所を有することの確認を受けなければならない。
解説:
公職選挙法 第45条(投票用紙の交付及び様式)
原文:
第四十五条 投票用紙は、選挙の当日、投票所において選挙人に交付しなければならない。
2 投票用紙の様式は、衆議院議員又は参議院議員の選挙については総務省令で定め、地方公共団体の議会の議員又は長の選挙については当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会が定める。
解説:
公職選挙法 第46条(投票の記載事項及び投函)
原文:
第四十六条 衆議院(比例代表選出)議員又は参議院(比例代表選出)議員の選挙以外の選挙の投票については、選挙人は、投票所において、投票用紙に当該選挙の公職の候補者一人の氏名を自書して、これを投票箱に入れなければならない。
2 衆議院(比例代表選出)議員の選挙の投票については、選挙人は、投票所において、投票用紙に一の衆議院名簿届出政党等(第八十六条の二第一項の規定による届出をした政党その他の政治団体をいう。以下同じ。)の同項の届出に係る名称又は略称を自書して、これを投票箱に入れなければならない。
3 参議院(比例代表選出)議員の選挙の投票については、選挙人は、投票所において、投票用紙に公職の候補者たる参議院名簿登載者(第八十六条の三第一項の参議院名簿登載者をいう。以下この章から第八章までにおいて同じ。)一人の氏名を自書して、これを投票箱に入れなければならない。ただし、公職の候補者たる参議院名簿登載者の氏名を自書することに代えて、一の参議院名簿届出政党等(同項の規定による届出をした政党その他の政治団体をいう。以下同じ。)の同項の届出に係る名称又は略称を自書することができる。
4 投票用紙には、選挙人の氏名を記載してはならない。
解説:
公職選挙法 第46条の2(記号式投票)
原文:
第四十六条の二 地方公共団体の議会の議員又は長の選挙の投票(次条、第四十八条の二及び第四十九条の規定による投票を除く。)については、地方公共団体は、前条第一項の規定にかかわらず、条例で定めるところにより、選挙人が、自ら、投票所において、投票用紙に氏名が印刷された公職の候補者のうちその投票しようとするもの一人に対して、投票用紙の記号を記載する欄に○の記号を記載して、これを投票箱に入れる方法によることができる。
2 前項の場合においては、第四十八条第一項中「当該選挙の公職の候補者の氏名」とあるのは「○の記号」と、「第四十六条第一項から第三項まで」とあるのは「第四十六条の二第一項及び第二項」と、同条第二項中「公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。)一人の氏名」とあるのは「公職の候補者一人に対して○の記号」と、第六十八条第一項第一号中「用いないもの」とあるのは「用いないもの又は所定の○の記号の記載方法によらないもの」と、同項第二号中「公職の候補者となることができない者の氏名」とあるのは「公職の候補者となることができない者に対して○の記号」と、同項第四号及び第五号中「公職の候補者の氏名」とあるのは「公職の候補者に対して○の記号」と、同項第六号中「公職の候補者の氏名のほか、他事を記載したもの。ただし、職業、身分、住所又は敬称の類を記入したものは、この限りでない。」とあるのは「○の記号以外の事項を記載したもの」と、同項第七号中「公職の候補者の氏名を自書しないもの」とあるのは「○の記号を自ら記載しないもの」と、同項第八号中「公職の候補者の何人」とあるのは「公職の候補者のいずれに対して○の記号」と、第八十六条の四第五項中「三日」とあるのは「四日」と、「二日」とあるのは「三日」と、同条第六項中「第一項から第四項までの規定の例により、都道府県知事又は市長の選挙にあつてはその選挙の期日前三日までに、町村の長の選挙にあつてはその選挙の期日前二日までに、当該選挙における候補者の届出をすることができる」とあるのは「選挙の期日は、政令で定める日に延期するものとする。この場合においては、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会は、直ちにその旨を告示しなければならない」と、同条第七項中「前項」とあるのは「前項の規定により選挙の期日を延期した場合における次項」と、「第三十三条第五項(第三十四条の二第五項において準用する場合を含む。)、第三十四条第六項又は第百十九条第三項の規定により告示した期日後五日に当たる日」とあるのは「政令で定める日」と、同条第八項中「前項」とあるのは「前二項」と、「当該選挙の期日前三日までに」とあるのは「政令で定める日までに」と、第百二十六条第一項中「第七項」とあるのは「第六項又は第七項」と、同条第二項中「第七項」とあるのは「第六項又は第七項」と、「七日以内」とあるのは「政令で定める日以内」と、同条第三項中「第七項」とあるのは「第六項又は第七項」とし、第六十八条第一項第三号及び第六十八条の二の規定は、適用しない。
3 第一項の場合において、○の記号の記載方法、投票用紙に印刷する公職の候補者の氏名の順序の決定方法及び公職の候補者が死亡し、又は公職の候補者たることを辞したものとみなされた場合における投票用紙における公職の候補者の表示方法その他必要な事項は、政令で定める。
解説:
公職選挙法 第47条(点字投票)
原文:
第四十七条 投票に関する記載については、政令で定める点字は文字とみなす。
解説:
公職選挙法 第48条(代理投票)
原文:
第四十八条 心身の故障その他の事由により、自ら当該選挙の公職の候補者の氏名(衆議院比例代表選出議員の選挙の投票にあつては衆議院名簿届出政党等の名称及び略称、参議院比例代表選出議員の選挙の投票にあつては公職の候補者たる参議院名簿登載者の氏名又は参議院名簿届出政党等の名称及び略称)を記載することができない選挙人は、第四十六条第一項から第三項まで、第五十条第四項及び第五項並びに第六十八条の規定にかかわらず、投票管理者に申請し、代理投票をさせることができる。
2 前項の規定による申請があつた場合においては、投票管理者は、投票立会人の意見を聴いて、投票所の事務に従事する者のうちから当該選挙人の投票を補助すべき者二人を定め、その一人に投票の記載をする場所において投票用紙に当該選挙人が指示する公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。)一人の氏名、一の衆議院名簿届出政党等の名称若しくは略称又は一の参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称を記載させ、他の一人をこれに立ち会わせなければならない。
3 前二項の場合において必要な事項は、政令で定める。
解説:
公職選挙法 第48条の2(期日前投票)
原文:
第四十八条の二 選挙の当日に次の各号に掲げる事由のいずれかに該当すると見込まれる選挙人の投票については、第四十四条第一項の規定にかかわらず、当該選挙の期日の公示又は告示があつた日の翌日から選挙の期日の前日までの間、期日前投票所において、行わせることができる。
一 職務若しくは業務又は総務省令で定める用務に従事すること。
二 用務(前号の総務省令で定めるものを除く。)又は事故のためその属する投票区の区域外に旅行又は滞在をすること。
三 疾病、負傷、妊娠、老衰若しくは身体の障害のため若しくは産褥にあるため歩行が困難であること又は刑事施設、労役場、監置場、少年院若しくは少年鑑別所に収容されていること。
四 交通至難の島その他の地で総務省令で定める地域に居住していること又は当該地域に滞在をすること。
五 その属する投票区のある市町村の区域外の住所に居住していること。
六 天災又は悪天候により投票所に到達することが困難であること。
2 市町村の選挙管理委員会は、二以上の期日前投票所を設ける場合には、一の期日前投票所において投票をした選挙人が他の期日前投票所において投票をすることを防止するために必要な措置を講じなければならない。
3 天災その他避けることのできない事故により、期日前投票所において投票を行わせることができないときは、市町村の選挙管理委員会は、期日前投票所を開かず、又は閉じるものとする。
4 市町村の選挙管理委員会は、前項の規定により期日前投票所を開かず、又は閉じる場合には、直ちにその旨を告示しなければならない。市町村の選挙管理委員会が当該期日前投票所を開く場合も、同様とする。
5 第一項の規定により期日前投票所において投票を行わせる場合における次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とし、第三十七条第七項及び第五十七条の規定は、適用しない。
6 第三十九条から第四十一条まで及び第五十八条から第六十条までの規定は、期日前投票所について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
7 市町村の選挙管理委員会は、期日前投票所を設ける場合には、当該市町村の人口、地勢、交通等の事情を考慮して、期日前投票所の効果的な設置、期日前投票所への交通手段の確保その他の選挙人の投票の便宜のため必要な措置を講ずるものとする。
8 第一項の場合において、投票録の作成の方法その他必要な事項は、政令で定める。
解説:
公職選挙法 第49条(不在者投票)
原文:
第四十九条 前条第一項の選挙人の投票については、同項の規定によるほか、政令で定めるところにより、第四十二条第一項ただし書、第四十四条、第四十五条、第四十六条第一項から第三項まで、第四十八条及び第五十条の規定にかかわらず、不在者投票管理者の管理する投票を記載する場所において、投票用紙に投票の記載をし、これを封筒に入れて不在者投票管理者に提出する方法により行わせることができる。
2 選挙人で身体に重度の障害があるもの(身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第四条に規定する身体障害者、戦傷病者特別援護法(昭和三十八年法律第百六十八号)第二条第一項に規定する戦傷病者又は介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第七条第三項に規定する要介護者であるもので、政令で定めるものをいう。)の投票については、前条第一項及び前項の規定によるほか、政令で定めるところにより、第四十二条第一項ただし書、第四十四条、第四十五条、第四十六条第一項から第三項まで、第四十八条及び第五十条の規定にかかわらず、その現在する場所において投票用紙に投票の記載をし、これを郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者、同条第九項に規定する特定信書便事業者若しくは同法第三条第四号に規定する外国信書便事業者による同法第二条第二項に規定する信書便(以下「郵便等」という。)により送付する方法により行わせることができる。
3 前項の選挙人で同項に規定する方法により投票をしようとするもののうち自ら投票の記載をすることができないものとして政令で定めるものは、第六十八条の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、あらかじめ市町村の選挙管理委員会の委員長に届け出た者(選挙権を有する者に限る。)をして投票に関する記載をさせることができる。
4 特定国外派遣組織に属する選挙人で国外に滞在するもののうち選挙の当日前条第一項第一号に掲げる事由に該当すると見込まれるものの投票については、同項及び第一項の規定によるほか、政令で定めるところにより、第四十二条第一項ただし書、第四十四条、第四十五条、第四十六条第一項から第三項まで、第四十八条及び第五十条の規定にかかわらず、国外にある不在者投票管理者の管理する投票を記載する場所において、投票用紙に投票の記載をし、これを封筒に入れて不在者投票管理者に提出する方法により行わせることができる。
5 前項の特定国外派遣組織とは、法律の規定に基づき国外に派遣される組織のうち次の各号のいずれにも該当する組織であつて、当該組織において同項に規定する方法による投票が適正に実施されると認められるものとして政令で定めるものをいう。
一 当該組織の長が当該組織の運営について管理又は調整を行うための法令に基づく権限を有すること。
二 当該組織が国外の特定の施設又は区域に滞在していること。
6 特定国外派遣組織となる組織を国外に派遣することを定める法律の規定に基づき国外に派遣される選挙人(特定国外派遣組織に属するものを除く。)で、現に特定国外派遣組織が滞在する施設又は区域に滞在しているものは、この法律の規定の適用については、当該特定国外派遣組織に属する選挙人とみなす。
7 選挙人で船舶安全法(昭和八年法律第十一号)にいう遠洋区域を航行区域とする船舶その他これに準ずるものとして総務省令で定める船舶(以下この項において「指定船舶」という。)に乗つて本邦以外の区域を航海する船員(船員法(昭和二十二年法律第百号)第一条に規定する船員をいい、実習を行うため航海する学生、生徒その他の者であつて船員手帳に準ずる文書の交付を受けているもの(以下この項において「実習生」という。)を含む。)であるもの又は選挙人で指定船舶以外の船舶であつて指定船舶に準ずるものとして総務省令で定めるものに乗つて本邦以外の区域を航海する船員(船員法第一条に規定する船員をいい、船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第九十二条第一項の規定により船員法第二条第二項に規定する予備船員とみなされる者及び船員の雇用の促進に関する特別措置法(昭和五十二年法律第九十六号)第十四条第一項の規定により船員法第二条第二項に規定する予備船員とみなされる者並びに実習生を含む。)であるもののうち選挙の当日前条第一項第一号に掲げる事由に該当すると見込まれるものの衆議院議員の総選挙又は参議院議員の通常選挙における投票については、同項及び第一項の規定によるほか、政令で定めるところにより、第四十二条第一項ただし書、第四十四条、第四十五条、第四十六条第一項から第三項まで、第四十八条及び第五十条の規定にかかわらず、不在者投票管理者の管理する場所において、総務省令で定める投票送信用紙に投票の記載をし、これを総務省令で指定する市町村の選挙管理委員会の委員長にファクシミリ装置を用いて送信する方法により、行わせることができる。
8 前項の規定は、同項の選挙人で同項の不在者投票管理者の管理する場所において投票をすることができないものとして政令で定めるものであるもののうち選挙の当日前条第一項第一号に掲げる事由に該当すると見込まれるものの衆議院議員の総選挙又は参議院議員の通常選挙における投票について準用する。この場合において、前項中「不在者投票管理者の管理する場所」とあるのは、「その現在する場所」と読み替えるものとする。
9 国が行う南極地域における科学的調査の業務を行う組織(以下この項において「南極地域調査組織」という。)に属する選挙人(南極地域調査組織に同行する選挙人で当該南極地域調査組織の長の管理の下に南極地域における活動を行うものを含む。)で次の各号に掲げる施設又は船舶に滞在するもののうち選挙の当日前条第一項第一号に掲げる事由に該当すると見込まれるものの衆議院議員の総選挙又は参議院議員の通常選挙における投票については、同項及び第一項の規定によるほか、政令で定めるところにより、第四十二条第一項ただし書、第四十四条、第四十五条、第四十六条第一項から第三項まで、第四十八条及び第五十条の規定にかかわらず、その滞在する次の各号に掲げる施設又は船舶の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める場所において、総務省令で定める投票送信用紙に投票の記載をし、これを総務省令で指定する市町村の選挙管理委員会の委員長にファクシミリ装置を用いて送信する方法により、行わせることができる。
一 南極地域にある当該科学的調査の業務の用に供される施設で国が設置するもの 不在者投票管理者の管理する場所
二 本邦と前号に掲げる施設との間において南極地域調査組織を輸送する船舶で前項の総務省令で定めるもの この項に規定する方法による投票を行うことについて不在者投票管理者が当該船舶の船長の許可を得た場所
10 不在者投票管理者は、市町村の選挙管理委員会が選定した者を投票に立ち会わせることその他の方法により、不在者投票の公正な実施の確保に努めなければならない。
解説:
公職選挙法 第49条の2(在外投票等)
解説:
公職選挙法 第50条(選挙人の確認及び投票の拒否)
原文:
第五十条 投票管理者は、投票をしようとする選挙人が本人であるかどうかを確認することができないときは、その本人である旨を宣言させなければならない。その宣言をしない者は、投票をすることができない。
2 投票の拒否は、投票立会人の意見を聴き、投票管理者が決定しなければならない。
3 前項の決定を受けた選挙人において不服があるときは、投票管理者は、仮に投票をさせなければならない。
4 前項の投票は、選挙人をしてこれを封筒に入れて封をし、表面に自らその氏名を記載して投票箱に入れさせなければならない。
5 投票立会人において異議のある選挙人についても、また前二項と同様とする。
解説:
公職選挙法 第51条(退出せしめられた者の投票)
原文:
第五十一条 第六十条の規定により投票所外に退出せしめられた者は、最後になつて投票をすることができる。但し、投票管理者は、投票所の秩序をみだる虞がないと認める場合においては、投票をさせることを妨げない。
解説:
公職選挙法 第52条(投票の秘密保持)
原文:
第五十二条 何人も、選挙人の投票した被選挙人の氏名又は政党その他の政治団体の名称若しくは略称を陳述する義務はない。
解説:
公職選挙法 第53条(投票箱の閉鎖)
原文:
第五十三条 投票所を閉じるべき時刻になつたときは、投票管理者は、その旨を告げて、投票所の入口を鎖し、投票所にある選挙人の投票の結了するのを待つて、投票箱を閉鎖しなければならない。
2 何人も、投票箱の閉鎖後は、投票をすることができない。
解説:
公職選挙法 第54条(投票録の作成)
原文:
第五十四条 投票管理者は、投票録を作り、投票に関する次第を記載し、投票立会人とともに、これに署名しなければならない。
解説:
公職選挙法 第55条(投票箱等の送致)
原文:
第五十五条 投票管理者が同時に当該選挙の開票管理者である場合を除くほか、投票管理者は、一人又は数人の投票立会人とともに、選挙の当日、その投票箱、投票録、選挙人名簿又はその抄本及び在外選挙人名簿又はその抄本(当該在外選挙人名簿が第三十条の二第四項の規定により磁気ディスクをもつて調製されている場合には、当該在外選挙人名簿に記録されている全部若しくは一部の事項又は当該事項を記載した書類。以下この条及び次条において同じ。)を開票管理者に送致しなければならない。ただし、当該選挙人名簿が第十九条第三項の規定により磁気ディスクをもつて調製されている場合で政令で定めるときは選挙人名簿又はその抄本を、当該在外選挙人名簿が第三十条の二第四項の規定により磁気ディスクをもつて調製されている場合で政令で定めるときは在外選挙人名簿又はその抄本を、それぞれ、送致することを要しない。
解説:
公職選挙法 第56条(繰上投票)
原文:
第五十六条 島その他交通不便の地について、選挙の期日に投票箱を送致することができない状況があると認めるときは、都道府県の選挙管理委員会(市町村の議会の議員又は長の選挙については、市町村の選挙管理委員会)は、適宜にその投票の期日を定め、開票の期日までにその投票箱、投票録、選挙人名簿又はその抄本及び在外選挙人名簿又はその抄本を送致させることができる。
解説:
公職選挙法 第57条(繰延投票)
原文:
第五十七条 天災その他避けることのできない事故により、投票所において、投票を行うことができないとき、又は更に投票を行う必要があるときは、都道府県の選挙管理委員会(市町村の議会の議員又は長の選挙については、市町村の選挙管理委員会)は、更に期日を定めて投票を行わせなければならない。この場合において、当該選挙管理委員会は、直ちにその旨を告示するとともに、更に定めた期日を少なくとも二日前に告示しなければならない。
2 衆議院議員、参議院議員又は都道府県の議会の議員若しくは長の選挙について前項に規定する事由を生じた場合には、市町村の選挙管理委員会は、当該選挙の選挙長(衆議院比例代表選出議員若しくは参議院比例代表選出議員の選挙又は参議院合同選挙区選挙については、選挙分会長)を経て都道府県の選挙管理委員会にその旨を届け出なければならない。
解説:
公職選挙法 第58条(投票所に出入し得る者)
原文:
第五十八条 選挙人、投票所の事務に従事する者、投票所を監視する職権を有する者又は当該警察官でなければ、投票所に入ることができない。
2 前項の規定にかかわらず、選挙人の同伴する子供(幼児、児童、生徒その他の年齢満十八年未満の者をいう。以下この項において同じ。)は、投票所に入ることができる。ただし、投票管理者が、選挙人の同伴する子供が投票所に入ることにより生ずる混雑、けん騒その他これらに類する状況から、投票所の秩序を保持することができなくなるおそれがあると認め、その旨を選挙人に告知したときは、この限りでない。
3 選挙人を介護する者その他の選挙人とともに投票所に入ることについてやむを得ない事情がある者として投票管理者が認めた者についても、前項本文と同様とする。
解説:
公職選挙法 第59条(投票所の秩序保持のための処分の請求)
原文:
第五十九条 投票管理者は、投票所の秩序を保持し、必要があると認めるときは、当該警察官の処分を請求することができる。
解説:
公職選挙法 第60条(投票所における秩序保持)
原文:
第六十条 投票所において演説討論をし若しくはけん騒にわたり又は投票に関し協議若しくは勧誘をし、その他投票所の秩序をみだす者があるときは、投票管理者は、これを制止し、命に従わないときは投票所外に退出せしめることができる。
解説:
第七章 開票
公職選挙法 第61条(開票管理者)
原文:
第六十一条 各選挙ごとに、開票管理者を置く。
2 開票管理者は、当該選挙の選挙権を有する者の中から市町村の選挙管理委員会の選任した者をもつて、これに充てる。
3 衆議院議員の選挙において、小選挙区選出議員の選挙と比例代表選出議員の選挙を同時に行う場合においては、市町村の選挙管理委員会は、小選挙区選出議員についての開票管理者を同時に比例代表選出議員についての開票管理者とすることができる。
4 参議院議員の選挙において、選挙区選出議員の選挙と比例代表選出議員の選挙を同時に行う場合においては、市町村の選挙管理委員会は、選挙区選出議員についての開票管理者を同時に比例代表選出議員についての開票管理者とすることができる。
5 開票管理者は、開票に関する事務を担任する。
6 開票管理者は、当該選挙の選挙権を有しなくなつたときは、その職を失う。
解説:
公職選挙法 第62条(開票立会人)
原文:
第六十二条 公職の候補者(衆議院小選挙区選出議員の選挙にあつては候補者届出政党(第八十六条第一項又は第八項の規定による届出をした政党その他の政治団体をいう。以下同じ。)及び公職の候補者(候補者届出政党の届出に係るものを除く。)、衆議院比例代表選出議員の選挙にあつては衆議院名簿届出政党等、参議院比例代表選出議員の選挙にあつては参議院名簿届出政党等)は、当該選挙の開票区ごとに、当該開票区の区域の全部又は一部をその区域に含む市町村の選挙人名簿に登録された者の中から、本人の承諾を得て、開票立会人となるべき者一人を定め、その選挙の期日前三日までに、市町村の選挙管理委員会に届け出ることができる。ただし、同一人を当該選挙の他の開票区における開票立会人となるべき者及び当該選挙と同じ日に行われるべき他の選挙における開票立会人となるべき者として届け出ることはできない。
2 前項の規定により届出のあつた者(次の各号に掲げる事由が生じたときは、当該各号に定めるものの届出に係る者を除く。以下この条において同じ。)が、十人を超えないときは直ちにその者をもつて開票立会人とし、十人を超えるときは届出のあつた者の中から市町村の選挙管理委員会がくじで定めた者十人をもつて開票立会人としなければならない。
一 公職の候補者(候補者届出政党の届出に係るものを除く。以下この号において同じ。)が死亡したとき、第八十六条第九項若しくは第八十六条の四第九項の規定により公職の候補者の届出が却下されたとき又は第八十六条第十二項若しくは第八十六条の四第十項の規定により公職の候補者がその候補者たることを辞したとき(第九十一条第二項又は第百三条第四項の規定によりその候補者たることを辞したものとみなされる場合を含む。) 当該公職の候補者
二 候補者届出政党の届出に係る候補者が死亡したとき、第八十六条第九項の規定により候補者届出政党がした候補者の届出が却下されたとき又は同条第十一項の規定により候補者届出政党が候補者の届出を取り下げたとき(第九十一条第一項又は第百三条第四項の規定により公職の候補者の届出が取り下げられたものとみなされる場合を含む。) 当該候補者届出政党
三 衆議院名簿届出政党等につき第八十六条の二第十項の規定による届出があつたとき又は同条第十一項の規定による却下があつたとき 当該衆議院名簿届出政党等
四 参議院名簿届出政党等につき第八十六条の三第二項において準用する第八十六条の二第十項の規定による届出があつたとき又は第八十六条の三第二項において準用する第八十六条の二第十一項の規定による却下があつたとき 当該参議院名簿届出政党等
3 同一の政党その他の政治団体に属する公職の候補者の届出にかかる者は、一の開票区において、三人以上開票立会人となることができない。
4 第一項の規定により届出のあつた者で同一の政党その他の政治団体に属する公職の候補者の届出にかかるものが三人以上あるときは、第二項の規定にかかわらず、その者の中で市町村の選挙管理委員会がくじで定めた者二人以外の者は、開票立会人となることができない。
5 第二項又は前項の規定により開票立会人が定まつた後、同一の政党その他の政治団体に属する公職の候補者の届出にかかる開票立会人が三人以上となつたときは、市町村の選挙管理委員会がくじで定めた者二人以外の者は、その職を失う。
6 第二項、第四項又は前項の規定によるくじを行うべき場所及び日時は、市町村の選挙管理委員会において、予め告示しなければならない。
7 第二項各号に掲げる事由が生じたときは、当該各号に定めるものの届出に係る開票立会人は、その職を失う。
8 都道府県の選挙管理委員会が第十八条第二項の規定により市町村の区域を分けて、又は数市町村の区域の全部若しくは一部を合わせて、開票区を設ける場合において、当該開票区を選挙の期日前二日から選挙の期日の前日までの間に設けたときは市町村の選挙管理委員会において、当該開票区を選挙の期日以後に設けたときは開票管理者において、当該開票区の区域の全部又は一部をその区域に含む市町村の選挙人名簿に登録された者の中から三人以上十人以下の開票立会人を選任し、直ちにこれを本人に通知し、開票に立ち会わせなければならない。ただし、同一の政党その他の政治団体に属する者を三人以上選任することができない。
9 第二項の規定による開票立会人が三人に達しないとき又は開票立会人が選挙の期日の前日までに三人に達しなくなつたときは市町村の選挙管理委員会において、開票立会人が選挙の期日以後に三人に達しなくなつたとき又は開票立会人で参会する者が開票所を開くべき時刻になつても三人に達しないとき若しくはその後三人に達しなくなつたときは開票管理者において、その開票区の区域の全部又は一部をその区域に含む市町村の選挙人名簿に登録された者の中から三人に達するまでの開票立会人を選任し、直ちにこれを本人に通知し、開票に立ち会わせなければならない。ただし、同項の規定による開票立会人を届け出た公職の候補者の属する政党その他の政治団体、同項の規定による開票立会人を届け出た候補者届出政党、衆議院名簿届出政党等若しくは参議院名簿届出政党等又は市町村の選挙管理委員会若しくは開票管理者の選任した開票立会人の属する政党その他の政治団体と同一の政党その他の政治団体に属する者を当該公職の候補者、候補者届出政党、衆議院名簿届出政党等若しくは参議院名簿届出政党等の届出に係る開票立会人又は市町村の選挙管理委員会若しくは開票管理者の選任に係る開票立会人と通じて三人以上選任することができない。
10 当該選挙の公職の候補者は、開票立会人となることができない。
11 開票立会人は、正当な理由がなければ、その職を辞することができない。
解説:
公職選挙法 第63条(開票所の設置)
原文:
第六十三条 開票所は、市役所、町村役場又は市町村の選挙管理委員会の指定した場所に設ける。
解説:
公職選挙法 第64条(開票の場所及び日時の告示)
原文:
第六十四条 市町村の選挙管理委員会は、予め開票の場所及び日時を告示しなければならない。
解説:
公職選挙法 第65条(開票日)
原文:
第六十五条 開票は、すべての投票箱の送致を受けた日又はその翌日に行う。
解説:
公職選挙法 第66条(開票)
原文:
第六十六条 開票管理者は、開票立会人立会の上、投票箱を開き、先ず第五十条第三項及び第五項の規定による投票を調査し、開票立会人の意見を聴き、その投票を受理するかどうかを決定しなければならない。
2 開票管理者は、開票立会人とともに、当該選挙における各投票所及び期日前投票所の投票を開票区ごとに混同して、投票を点検しなければならない。
3 投票の点検が終わつたときは、開票管理者は、直ちにその結果を選挙長(衆議院比例代表選出議員若しくは参議院比例代表選出議員の選挙又は参議院合同選挙区選挙については、選挙分会長)に報告しなければならない。
解説:
公職選挙法 第67条(開票の場合の投票の効力の決定)
原文:
第六十七条 投票の効力は、開票立会人の意見を聴き、開票管理者が決定しなければならない。その決定に当つては、第六十八条の規定に反しない限りにおいて、その投票した選挙人の意思が明白であれば、その投票を有効とするようにしなければならない。
解説:
公職選挙法 第68条(無効投票)
原文:
第六十八条 衆議院(比例代表選出)議員又は参議院(比例代表選出)議員の選挙以外の選挙の投票については、次の各号のいずれかに該当するものは、無効とする。
一 所定の用紙を用いないもの
二 公職の候補者でない者又は第八十六条の八第一項、第八十七条第一項若しくは第二項、第八十七条の二、第八十八条、第二百五十一条の二若しくは第二百五十一条の三の規定により公職の候補者となることができない者の氏名を記載したもの
三 第八十六条第一項若しくは第八項の規定による届出をした政党その他の政治団体で同条第一項各号のいずれにも該当していなかつたものの当該届出に係る候補者、同条第九項後段の規定による届出に係る候補者又は第八十七条第三項の規定に違反してされた届出に係る候補者の氏名を記載したもの
四 一投票中に二人以上の公職の候補者の氏名を記載したもの
五 被選挙権のない公職の候補者の氏名を記載したもの
六 公職の候補者の氏名のほか、他事を記載したもの。ただし、職業、身分、住所又は敬称の類を記入したものは、この限りでない。
七 公職の候補者の氏名を自書しないもの
八 公職の候補者の何人を記載したかを確認し難いもの
2 衆議院(比例代表選出)議員の選挙の投票については、次の各号のいずれかに該当するものは、無効とする。
一 所定の用紙を用いないもの
二 衆議院名簿届出政党等以外の政党その他の政治団体(第八十六条の二第十項の規定による届出をした政党その他の政治団体を含む。)の名称又は略称を記載したもの
三 第八十六条の二第一項の規定による届出をした政党その他の政治団体で同項各号のいずれにも該当していなかつたもの又は第八十七条第五項の規定に違反して第八十六条の二第一項の衆議院名簿を重ねて届け出ている政党その他の政治団体の名称又は略称を記載したもの
四 第八十六条の二第一項の衆議院名簿登載者の全員につき、同条第七項各号に規定する事由が生じており又は同項後段の規定による届出がされている場合の当該衆議院名簿に係る政党その他の政治団体の名称又は略称を記載したもの
五 一投票中に二以上の衆議院名簿届出政党等の第八十六条の二第一項の規定による届出に係る名称又は略称を記載したもの
六 衆議院名簿届出政党等の第八十六条の二第一項の規定による届出に係る名称及び略称のほか、他事を記載したもの。ただし、本部の所在地、代表者の氏名又は敬称の類を記入したものは、この限りでない。
七 衆議院名簿届出政党等の第八十六条の二第一項の規定による届出に係る名称又は略称を自書しないもの
八 衆議院名簿届出政党等のいずれを記載したかを確認し難いもの
3 参議院(比例代表選出)議員の選挙の投票については、次の各号のいずれかに該当するものは、無効とする。
一 所定の用紙を用いないもの
二 公職の候補者たる参議院名簿登載者でない者、第八十六条の三第二項において準用する第八十六条の二第七項後段の規定による届出に係る参議院名簿登載者若しくは第八十六条の八第一項、第八十七条第一項若しくは同条第六項において準用する同条第四項、第八十八条、第二百五十一条の二若しくは第二百五十一条の三の規定により公職の候補者となることができない参議院名簿登載者の氏名を記載したもの又は参議院名簿届出政党等以外の政党その他の政治団体の名称若しくは略称を記載したもの。ただし、代表者の氏名の類を記入したもので第八号ただし書に該当する場合は、この限りでない。
三 第八十六条の三第一項の規定による届出をした政党その他の政治団体で同項各号のいずれにも該当していなかつたもの若しくは同条第二項において準用する第八十六条の二第十項の規定による届出をしたもの又は第八十七条第六項において準用する同条第五項の規定に違反して第八十六条の三第一項の参議院名簿を重ねて届け出ている政党その他の政治団体の同項の規定による届出に係る参議院名簿登載者の氏名又はその届出に係る名称若しくは略称を記載したもの
四 参議院名簿登載者の全員につき、第八十六条の三第二項において準用する第八十六条の二第七項各号に規定する事由が生じており又は第八十六条の三第二項において準用する第八十六条の二第七項後段の規定による届出がされている場合の当該参議院名簿に係る政党その他の政治団体の名称又は略称を記載したもの
五 一投票中に二人以上の参議院名簿登載者の氏名又は二以上の参議院名簿届出政党等の第八十六条の三第一項の規定による届出に係る名称若しくは略称を記載したもの
六 一投票中に一人の参議院名簿登載者の氏名及び当該参議院名簿登載者に係る参議院名簿届出政党等以外の参議院名簿届出政党等の第八十六条の三第一項の規定による届出に係る名称又は略称を記載したもの
七 被選挙権のない参議院名簿登載者の氏名を記載したもの
八 公職の候補者たる参議院名簿登載者の氏名又は参議院名簿届出政党等の第八十六条の三第一項の規定による届出に係る名称及び略称のほか、他事を記載したもの。ただし、公職の候補者たる参議院名簿登載者の氏名の記載のある投票については当該参議院名簿登載者に係る参議院名簿届出政党等の同項の規定による届出に係る名称若しくは略称又は職業、身分、住所若しくは敬称の類(当該参議院名簿登載者が同項後段の規定により優先的に当選人となるべき候補者としてその氏名及び当選人となるべき順位が同項の参議院名簿に記載されている者(同条第二項において読み替えて準用する第八十六条の二第九項後段の規定により優先的に当選人となるべき候補者としてその氏名及び当選人となるべき順位が同項の規定による届出に係る文書に記載された者を含む。以下同じ。)である場合にあつては、当該参議院名簿登載者に係る参議院名簿届出政党等の第八十六条の三第一項の規定による届出に係る名称若しくは略称、当選人となるべき順位又は職業、身分、住所若しくは敬称の類)を、参議院名簿登載者の氏名の記載のない投票で参議院名簿届出政党等の同項の規定による届出に係る名称又は略称を記載したものについては本部の所在地、代表者の氏名又は敬称の類(当該参議院名簿届出政党等の届出に係る参議院名簿登載者のうちに同項後段の規定により優先的に当選人となるべき候補者としてその氏名及び当選人となるべき順位が同項の参議院名簿に記載されている者がある場合にあつては、その記載に係る順位、本部の所在地、代表者の氏名又は敬称の類)を記入したものは、この限りでない。
九 公職の候補者たる参議院名簿登載者の氏名又は参議院名簿届出政党等の第八十六条の三第一項の規定による届出に係る名称若しくは略称を自書しないもの
十 公職の候補者たる参議院名簿登載者の何人又は参議院名簿届出政党等のいずれを記載したかを確認し難いもの
解説:
無効投票の条件
特定の選挙における追加条件
公職選挙法 第六十八条の二(同一氏名の候補者等に対する投票の効力)
原文:
第六十八条の二 同一の氏名、氏又は名の公職の候補者が二人以上ある場合において、その氏名、氏又は名のみを記載した投票は、前条第一項第八号の規定にかかわらず、有効とする。
2 第八十六条の二第一項の規定による届出に係る名称又は略称が同一である衆議院名簿届出政党等が二以上ある場合において、その名称又は略称のみを記載した投票は、前条第二項第八号の規定にかかわらず、有効とする。
3 第八十六条の三第一項の規定による届出に係る参議院名簿登載者(公職の候補者たる者に限る。以下この条において同じ。)の氏名、氏若しくは名又は参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称が同一である参議院名簿登載者又は参議院名簿届出政党等が二以上ある場合において、これらの氏名、氏若しくは名又は名称若しくは略称のみを記載した投票は、前条第三項第十号の規定にかかわらず、有効とする。
4 第一項又は第二項の有効投票は、開票区ごとに、当該候補者又は当該衆議院名簿届出政党等のその他の有効投票数に応じてあん分し、それぞれこれに加えるものとする。
5 第三項の有効投票は、開票区ごとに、当該参議院名簿登載者のその他の有効投票数又は当該参議院名簿届出政党等のその他の有効投票数(当該参議院名簿届出政党等に係る各参議院名簿登載者の有効投票数を含まないものをいう。)に応じてあん分し、それぞれこれに加えるものとする。
解説:
公職選挙法 第六十八条の三(特定の参議院名簿登載者の有効投票)
原文:
第六十八条の三 前条第三項及び第五項の規定を適用する場合を除き、第八十六条の三第一項後段の規定により優先的に当選人となるべき候補者としてその氏名及び当選人となるべき順位が同項の参議院名簿に記載されている者である参議院名簿登載者の有効投票(前条第五項の規定によりあん分して加えられた有効投票を含む。)は、当該参議院名簿登載者に係る参議院名簿届出政党等の有効投票とみなす。
解説:
公職選挙法 第六十九条(開票の参観)
原文:
第六十九条 選挙人は、その開票所につき、開票の参観を求めることができる。
解説:
公職選挙法 第七十条(開票録の作成)
原文:
第七十条 開票管理者は、開票録を作り、開票に関する次第を記載し、開票立会人とともに、これに署名しなければならない。
解説:
公職選挙法 第七十一条(投票、投票録及び開票録の保存)
原文:
第七十一条 投票は、有効無効を区別し、投票録及び開票録と併せて、市町村の選挙管理委員会において、当該選挙にかかる議員又は長の任期間、保存しなければならない。
解説:
公職選挙法 第七十二条(一部無効に因る再選挙の開票)
原文:
第七十二条 選挙の一部が無効となり再選挙を行つた場合の開票においては、その投票の効力を決定しなければならない。
解説:
公職選挙法 第七十三条(繰延開票)
原文:
第七十三条 第五十七条第一項前段及び第二項の規定は、開票について準用する。
解説:
公職選挙法 第七十四条(開票所の取締り)
原文:
第七十四条 第五十八条第一項、第五十九条及び第六十条の規定は、開票所の取締りについて準用する。
解説:
第八章 選挙会及び選挙分会
公職選挙法 第七十五条(選挙長及び選挙分会長)
原文:
第七十五条 各選挙ごとに、選挙長を置く。
2 衆議院(比例代表選出)議員若しくは参議院(比例代表選出)議員の選挙又は参議院合同選挙区選挙においては、前項の選挙長を置くほか、都道府県ごとに、選挙分会長を置く。
3 選挙長は、当該選挙の選挙権を有する者の中から当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙については中央選挙管理会、参議院合同選挙区選挙については当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会)の選任した者をもつて、選挙分会長は、当該選挙の選挙権を有する者の中から都道府県の選挙管理委員会の選任した者をもつて、これに充てる。
4 選挙長は、選挙会に関する事務を、選挙分会長は、選挙分会に関する事務を、担任する。
5 選挙長及び選挙分会長は、当該選挙の選挙権を有しなくなつたときは、その職を失う。
解説:
公職選挙法 第七十六条(選挙立会人)
原文:
第七十六条 第六十二条(第八項を除く。)の規定は、選挙会及び選挙分会の選挙立会人について準用する。この場合において、同条第一項中「当該選挙の開票区ごとに、当該開票区の区域の全部又は一部をその区域に含む市町村の選挙人名簿に登録された者」とあるのは「当該選挙の選挙権を有する者(第七十九条第二項の規定により開票の事務を選挙会の事務に併せて行う旨の告示がされた場合にあつては、その開票区の区域の全部又は一部をその区域に含む市町村の選挙人名簿に登録された者。第九項において同じ。)」と、「期日前三日まで」とあるのは「期日前三日まで(第七十九条第一項に規定する場合にあつては、同条第二項の規定による告示がされた日からその選挙の期日前三日まで)」と、「市町村の選挙管理委員会」とあるのは「当該選挙長(衆議院比例代表選出議員若しくは参議院比例代表選出議員の選挙又は参議院合同選挙区選挙における選挙分会の選挙立会人については、当該選挙分会長。以下この条において同じ。)」と、同項ただし書中「同一人を当該選挙の他の開票区における開票立会人となるべき者及び」とあるのは「同一人を」と、同条第二項中「市町村の選挙管理委員会」とあるのは「当該選挙長」と、同条第三項中「開票区」とあるのは「選挙会(衆議院比例代表選出議員若しくは参議院比例代表選出議員の選挙又は参議院合同選挙区選挙については、選挙会又は選挙分会。第九項において同じ。)」と、同条第四項から第六項までの規定中「市町村の選挙管理委員会」とあるのは「当該選挙長」と、同条第九項本文中「達しないとき又は」とあるのは「達しないとき、」と、「選挙の期日の前日までに三人に達しなくなつたときは市町村の選挙管理委員会において、開票立会人が選挙の期日以後に三人に達しなくなつたとき」とあるのは「選挙会の期日までに三人に達しなくなつたとき」と、「開票所」とあるのは「選挙会」と、「開票管理者」とあるのは「、当該選挙長」と、「その開票区の区域の全部又は一部をその区域に含む市町村の選挙人名簿に登録された者」とあるのは「当該選挙の選挙権を有する者」と、「開票に」とあるのは「選挙会に」と、同項ただし書中「市町村の選挙管理委員会若しくは開票管理者」とあるのは「当該選挙長」と読み替えるものとする。
解説:
公職選挙法 第七十七条(選挙会及び選挙分会の開催場所)
原文:
第七十七条 選挙会は、都道府県庁又は当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙については中央選挙管理会、参議院合同選挙区選挙については当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会)の指定した場所で開く。
2 選挙分会は、都道府県庁又は都道府県の選挙管理委員会の指定した場所で開く。
解説:
公職選挙法 第七十八条(選挙会及び選挙分会の場所及び日時)
原文:
第七十八条 当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙については中央選挙管理会、参議院合同選挙区選挙については当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会)はあらかじめ選挙会の場所及び日時を、都道府県の選挙管理委員会はあらかじめ選挙分会の場所及び日時を、それぞれ告示しなければならない。
解説:
公職選挙法 第七十九条(開票事務と選挙会事務との合同)
原文:
第七十九条 衆議院(小選挙区選出)議員又は地方公共団体の議会の議員若しくは長の選挙において選挙会の区域と開票区の区域が同一である場合には、第六十六条第一項及び第二項、第六十七条、第六十八条第一項並びに第六十八条の二第一項及び第四項の規定を除いた第七章の規定にかかわらず、当該選挙の開票の事務は、選挙会場において選挙会の事務に併せて行うことができる。
2 前項に規定する場合においては、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会は、当該選挙の期日の公示又は告示があつた日に、当該選挙の開票の事務を選挙会の事務に併せて行うかどうかを告示しなければならない。
3 第一項の規定により開票の事務を選挙会の事務に併せて行う場合においては、開票管理者又は開票立会人は、選挙長又は選挙立会人をもつてこれに充て、開票に関する次第は、選挙録中に併せて記載するものとする。
解説:
公職選挙法 第八十条(選挙会又は選挙分会の開催)
原文:
第八十条 選挙長(衆議院比例代表選出議員若しくは参議院比例代表選出議員の選挙又は参議院合同選挙区選挙における選挙長を除く。)又は選挙分会長は、全ての開票管理者から第六十六条第三項の規定による報告を受けた日又はその翌日に選挙会又は選挙分会を開き、選挙立会人立会いの上、その報告を調査し、各公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。第三項において同じ。)、各衆議院名簿届出政党等又は各参議院名簿届出政党等の得票総数(各参議院名簿届出政党等の得票総数にあつては、当該参議院名簿届出政党等に係る各参議院名簿登載者(当該選挙の期日において公職の候補者たる者に限る。)の得票総数を含むものをいう。第三項において同じ。)を計算しなければならない。
2 前条第一項の場合においては、選挙長は、前項の規定にかかわらず、投票の点検の結果により、各公職の候補者の得票総数を計算しなければならない。
3 第一項に規定する選挙長又は選挙分会長は、選挙の一部が無効となり再選挙を行つた場合において第六十六条第三項の規定による報告を受けたときは、第一項の規定の例により、他の部分の報告とともに、更にこれを調査し、各公職の候補者、各衆議院名簿届出政党等又は各参議院名簿届出政党等の得票総数を計算しなければならない。
解説:
公職選挙法 第八十一条(衆議院比例代表選出議員若しくは参議院比例代表選出議員の選挙又は参議院合同選挙区選挙の選挙会の開催)
原文:
第八十一条 衆議院(比例代表選出)議員の選挙においては、選挙分会長は、前条第一項及び第三項の規定による調査を終わつたときは、選挙録の写しを添えて、直ちにその結果を当該選挙長に報告しなければならない。
2 前項の選挙長は、すべての選挙分会長から同項の規定による報告を受けた日若しくは中央選挙管理会から第百一条第四項の規定による通知を受けた日のいずれか遅い日(当該選挙が衆議院小選挙区選出議員の選挙と同時に行われない場合にあつては、すべての選挙分会長から前項の規定による報告を受けた日)又はその翌日に選挙会を開き、選挙立会人立会いの上、その報告を調査し、各衆議院名簿届出政党等の得票総数を計算しなければならない。
3 選挙の一部が無効となり再選挙を行つた場合において第一項の規定による報告を受けたときは、当該選挙長は、前項の規定の例により、他の部分の報告とともに、更にこれを調査し、各衆議院名簿届出政党等の得票総数を計算しなければならない。
4 前三項の規定は、参議院(比例代表選出)議員の選挙について準用する。この場合において、第二項中「同項の規定による報告を受けた日若しくは中央選挙管理会から第百一条第四項の規定による通知を受けた日のいずれか遅い日(当該選挙が衆議院小選挙区選出議員の選挙と同時に行われない場合にあつては、すべての選挙分会長から前項の規定による報告を受けた日)」とあるのは「同項の規定による報告を受けた日」と、「各衆議院名簿届出政党等の得票総数」とあるのは「各参議院名簿届出政党等の得票総数(当該参議院名簿届出政党等に係る各参議院名簿登載者(当該選挙の期日において公職の候補者たる者に限る。以下この項において同じ。)の得票総数を含むものをいう。次項において同じ。)及び各参議院名簿登載者の得票総数」と、前項中「各衆議院名簿届出政党等の得票総数」とあるのは「各参議院名簿届出政党等の得票総数及び各参議院名簿登載者の得票総数」と読み替えるものとする。
5 第一項から第三項までの規定は、参議院合同選挙区選挙について準用する。この場合において、第二項中「同項の規定による報告を受けた日若しくは中央選挙管理会から第百一条第四項の規定による通知を受けた日のいずれか遅い日(当該選挙が衆議院小選挙区選出議員の選挙と同時に行われない場合にあつては、すべての選挙分会長から前項の規定による報告を受けた日)」とあるのは「同項の規定による報告を受けた日」と、同項及び第三項中「各衆議院名簿届出政党等」とあるのは「各候補者」と読み替えるものとする。
解説:
公職選挙法 第八十二条(選挙会及び選挙分会の参観)
原文:
第八十二条 選挙人は、その選挙会及び選挙分会の参観を求めることができる。
解説:
公職選挙法 第八十三条(選挙録の作成及び選挙録その他関係書類の保存)
原文:
第八十三条 選挙長又は選挙分会長は、選挙録を作り、選挙会又は選挙分会に関する次第を記載し、選挙立会人とともに、これに署名しなければならない。
2 選挙録は、第六十六条第三項の規定による報告に関する書類(衆議院比例代表選出議員の選挙にあつては第八十一条第一項の規定による報告に関する書類、参議院比例代表選出議員の選挙にあつては同条第四項において準用する同条第一項の規定による報告に関する書類、参議院合同選挙区選挙にあつては同条第五項において準用する同条第一項の規定による報告に関する書類)と併せて、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙の選挙会に関するものについては中央選挙管理会、参議院合同選挙区選挙の選挙会に関するものについては当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会、選挙分会に関するものについては当該都道府県の選挙管理委員会)において、当該選挙に係る議員又は長の任期間、保存しなければならない。
3 第七十九条の場合においては、投票の有効無効を区別し、投票録及び選挙録と併せて、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会において、当該選挙にかかる議員又は長の任期間、保存しなければならない。
解説:
公職選挙法 第八十四条(繰延選挙会又は繰延選挙分会)
原文:
第八十四条 第五十七条第一項前段の規定は、選挙会及び選挙分会について準用する。この場合において、同項前段中「都道府県の選挙管理委員会(市町村の議会の議員又は長の選挙については、市町村の選挙管理委員会)」とあるのは、「当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙会に関しては中央選挙管理会、参議院合同選挙区選挙の選挙会に関しては当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会、選挙分会に関しては都道府県の選挙管理委員会)」と読み替えるものとする。
解説:
公職選挙法 第八十五条(選挙会場及び選挙分会場の取締り)
原文:
第八十五条 第五十八条第一項、第五十九条及び第六十条の規定は、選挙会場及び選挙分会場の取締りについて準用する。
解説:
第九章 公職の候補者
公職選挙法 第八十六条(衆議院小選挙区選出議員の選挙における候補者の立候補の届出等)
原文:
第八十六条 衆議院(小選挙区選出)議員の選挙において、次の各号のいずれかに該当する政党その他の政治団体は、当該政党その他の政治団体に所属する者を候補者としようとするときは、当該選挙の期日の公示又は告示があつた日に、郵便等によることなく、文書でその旨を当該選挙長に届け出なければならない。
一 当該政党その他の政治団体に所属する衆議院議員又は参議院議員を五人以上有すること。
二 直近において行われた衆議院議員の総選挙における小選挙区選出議員の選挙若しくは比例代表選出議員の選挙又は参議院議員の通常選挙における比例代表選出議員の選挙若しくは選挙区選出議員の選挙における当該政党その他の政治団体の得票総数が当該選挙における有効投票の総数の百分の二以上であること。
2 衆議院(小選挙区選出)議員の候補者となろうとする者は、前項の公示又は告示があつた日に、郵便等によることなく、文書でその旨を当該選挙長に届け出なければならない。
3 選挙人名簿に登録された者が他人を衆議院(小選挙区選出)議員の候補者としようとするときは、本人の承諾を得て、第一項の公示又は告示があつた日に、郵便等によることなく、文書で当該選挙長にその推薦の届出をすることができる。
4 第一項の文書には、当該政党その他の政治団体の名称、本部の所在地及び代表者(総裁、会長、委員長その他これらに準ずる地位にある者をいう。以下この条から第八十六条の七まで、第百四十二条の二第三項、第百六十九条第七項、第百七十五条第九項及び第百八十条第二項において同じ。)の氏名並びに候補者となるべき者の氏名、本籍、住所、生年月日及び職業その他政令で定める事項を記載しなければならない。
5 第一項の文書には、次に掲げる文書を添えなければならない。ただし、直近において行われた衆議院議員の総選挙の期日後に第八十六条の六第一項又は第二項の規定による届出をした政党その他の政治団体で同条第九項の規定による届出をしていないもの(同条第四項の規定により添えた文書の内容に異動があつたものにあつては、選挙の期日の公示又は告示の日の前日までに同条第七項の規定による届出をしたものに限る。次条第二項において「衆議院名称届出政党」という。)が、第一項の規定による届出をする場合においては、第一号に掲げる文書及び第二号に掲げる文書のうち政令で定めるものの添付を省略することができる。
一 政党その他の政治団体の綱領、党則、規約その他これらに相当するものを記載した文書
二 第一項各号のいずれかに該当することを証する政令で定める文書
三 当該届出が第八十七条第三項の規定に違反するものでないことを代表者が誓う旨の宣誓書
四 候補者となるべき者の候補者となることについての同意書及び第八十六条の八第一項、第八十七条第一項若しくは第二項、第八十七条の二、第二百五十一条の二又は第二百五十一条の三の規定により公職の候補者となることができない者でないことを当該候補者となるべき者が誓う旨の宣誓書
五 候補者となるべき者の選定を当該政党その他の政治団体において行う機関の名称、その構成員の選出方法及び候補者となるべき者の選定の手続を記載した文書並びに当該候補者となるべき者の選定を適正に行つたことを当該機関を代表する者が誓う旨の宣誓書
六 その他政令で定める文書
6 第二項及び第三項の文書には、候補者となるべき者の氏名、本籍、住所、生年月日及び職業その他政令で定める事項を記載しなければならない。
7 第二項及び第三項の文書には、第八十六条の八第一項、第八十七条第一項若しくは第二項、第八十七条の二、第二百五十一条の二又は第二百五十一条の三の規定により公職の候補者となることができない者でないことを当該候補者となるべき者が誓う旨の宣誓書、当該候補者となるべき者の所属する政党その他の政治団体の名称(二以上の政党その他の政治団体に所属するときは、いずれか一の政党その他の政治団体の名称)を記載した文書及び当該記載に関する政党その他の政治団体の代表者の証明書その他政令で定める文書を添えなければならない。
8 第一項の公示又は告示があつた日に届出のあつた候補者が二人以上ある場合において、その日後、当該候補者が死亡し、当該届出が取り下げられたものとみなされ、当該候補者が候補者たることを辞したものとみなされ、又は次項後段の規定により当該届出が却下されたときは、前各項の規定の例により、当該選挙の期日前三日までに、候補者の届出をすることができる。
9 次の各号のいずれかに該当する事由があることを知つたときは、選挙長は、第一項から第三項まで又は前項の規定による届出を却下しなければならない。第一項又は前項の規定により届出のあつた者につき除名、離党その他の事由により当該候補者届出政党に所属する者でなくなつた旨の届出が当該選挙の期日の前日までに当該候補者届出政党から文書でされたときも、また同様とする。
一 第一項又は前項の規定による政党その他の政治団体の届出が第一項各号のいずれにも該当しない政党その他の政治団体によつてされたものであること。
二 第一項又は前項の規定による政党その他の政治団体の届出が第八十七条第三項の規定に違反してされたものであること。
三 第一項から第三項まで又は前項の規定により届出のあつた者が第八十六条の八第一項、第八十七条第一項若しくは第二項、第八十七条の二、第八十八条、第二百五十一条の二又は第二百五十一条の三の規定により公職の候補者となり、又は公職の候補者であることができない者であること。
10 前項後段の文書には、当該届出に係る事由が、除名である場合にあつては当該除名の手続を記載した文書及び当該除名が適正に行われたことを代表者が誓う旨の宣誓書を、離党である場合にあつては当該候補者が候補者届出政党に提出した離党届の写しを、その他の事由である場合にあつては当該事由を証する文書を、それぞれ、添えなければならない。
11 候補者届出政党は、第一項の規定により候補者の届出をした場合には同項の公示又は告示があつた日に、第八項の規定により候補者の届出をした場合には当該選挙の期日前三日までに選挙長に届出をしなければ、その候補者の届出を取り下げることができない。
12 候補者(候補者届出政党の届出に係るものを除く。以下この項において同じ。)は、第二項又は第三項の規定により届出のあつた候補者にあつては第一項の公示又は告示があつた日に、第八項の規定により届出のあつた候補者にあつては当該選挙の期日前三日までに選挙長に届出をしなければ、その候補者たることを辞することができない。
13 第一項から第三項まで、第八項、第十一項若しくは前項の規定による届出があつたとき、第九項の規定により届出を却下したとき又は候補者が死亡し若しくは第九十一条第一項若しくは第二項若しくは第百三条第四項の規定に該当するに至つたことを知つたときは、選挙長は、直ちにその旨を告示するとともに、当該都道府県の選挙管理委員会に報告しなければならない。
14 第一項第一号に規定する衆議院議員又は参議院議員の数の算定、同項第二号に規定する政党その他の政治団体の得票総数(第七項の文書にその名称を記載された政党その他の政治団体の得票総数を含む。次条第十四項及び第百五十条第八項において同じ。)の算定その他第一項の規定の適用について必要な事項は、政令で定める。
解説:
公職選挙法 第八十六条の三(参議院比例代表選出議員の選挙における名簿による立候補の届出等)
原文:
第八十六条の三 参議院(比例代表選出)議員の選挙においては、次の各号のいずれかに該当する政党その他の政治団体は、当該政党その他の政治団体の名称(一の略称を含む。)及びその所属する者(当該政党その他の政治団体が推薦する者を含む。第九十八条第三項において同じ。)の氏名を記載した文書(以下「参議院名簿」という。)を選挙長に届け出ることにより、その参議院名簿に記載されている者(以下「参議院名簿登載者」という。)を当該選挙における候補者とすることができる。この場合においては、候補者とする者のうちの一部の者について、優先的に当選人となるべき候補者として、その氏名及びそれらの者の間における当選人となるべき順位をその他の候補者とする者の氏名と区分してこの項の規定により届け出る文書に記載することができる。
一 当該政党その他の政治団体に所属する衆議院議員又は参議院議員を五人以上有すること。
二 直近において行われた衆議院議員の総選挙における小選挙区選出議員の選挙若しくは比例代表選出議員の選挙又は参議院議員の通常選挙における比例代表選出議員の選挙若しくは選挙区選出議員の選挙における当該政党その他の政治団体の得票総数が当該選挙における有効投票の総数の百分の二以上であること。
三 当該参議院議員の選挙において候補者(この項の規定による届出をすることにより候補者となる参議院名簿登載者を含む。)を十人以上有すること。
2 前条第二項、第三項、第五項、第七項(第四号を除く。)及び第八項から第十四項までの規定は、参議院(比例代表選出)議員の選挙について準用する。この場合において、同条第二項各号列記以外の部分中「前項」とあるのは「次条第一項」と、「衆議院名簿」とあるのは「同項の参議院名簿(以下この条において「参議院名簿」という。)」と、「衆議院名称届出政党」とあるのは「任期満了前九十日に当たる日から七日を経過する日までの間に第八十六条の七第一項の規定による届出をした政党その他の政治団体で同条第五項の規定による届出をしていないもの(同条第三項の規定により添えた文書の内容に異動がないものに限る。)」と、「同項」とあるのは「次条第一項」と、同項第一号中「衆議院名簿登載者」とあるのは「次条第一項の参議院名簿登載者(以下この条において「参議院名簿登載者」という。)」と、同項第三号中「前項各号」とあるのは「次条第一項各号」と、同項第四号中「第八十七条第五項」とあるのは「第八十七条第六項において準用する同条第五項」と、同項第五号中「衆議院名簿登載者」とあるのは「参議院名簿登載者」と、「又は第八十七条第一項若しくは第四項」とあるのは「、第八十七条第一項若しくは同条第六項において準用する同条第四項、第二百五十一条の二又は第二百五十一条の三」と、同項第六号中「衆議院名簿登載者の選定及びそれらの者の間における当選人となるべき順位の決定(以下単に「衆議院名簿登載者の選定」という。)」とあるのは「参議院名簿登載者の選定(当該政党その他の政治団体が次条第一項後段の規定により優先的に当選人となるべき候補者として候補者とする者の氏名及び当選人となるべき順位を参議院名簿に記載した場合においては、その記載に係る者の選定及びそれらの者の間における当選人となるべき順位の決定を含む。以下この号において同じ。)」と、「並びに衆議院名簿登載者」とあるのは「及び参議院名簿登載者」と、「当該衆議院名簿登載者」とあるのは「当該参議院名簿登載者」と、同条第三項中「衆議院名簿」とあるのは「参議院名簿」と、「第八十六条の六第六項」とあるのは「第八十六条の七第四項」と、「いずれかの選挙区における衆議院名簿登載者」とあるのは「参議院名簿登載者」と、「同条第六項」とあるのは「同条第四項」と、同条第五項中「各衆議院名簿の衆議院名簿登載者(当該選挙と同時に行われる衆議院小選挙区選出議員の選挙における候補者であつて、前項の規定により、当該衆議院名簿の衆議院名簿登載者とされたものを除く。)」とあるのは「各参議院名簿の参議院名簿登載者」と、「数は、選挙区ごとに」とあるのは「数は」と、同条第七項中「第一項の規定」とあるのは「次条第一項の規定」と、「衆議院名簿」とあるのは「参議院名簿」と、「衆議院名簿登載者」とあるのは「参議院名簿登載者」と、「衆議院名簿届出政党等」とあるのは「参議院名簿届出政党等」と、「所属する者」とあるのは「所属する者(当該政党その他の政治団体が推薦する者を含む。)」と、「第八十七条第一項若しくは第四項又は第八十八条」とあるのは「第八十七条第一項若しくは同条第六項において準用する同条第四項、第八十八条、第二百五十一条の二又は第二百五十一条の三」と、同条第八項中「衆議院名簿登載者」とあるのは「参議院名簿登載者」と、「衆議院名簿届出政党等」とあるのは「参議院名簿届出政党等」と、同条第九項中「第一項の規定による届出の後」とあるのは「次条第一項の規定による届出の後」と、「衆議院名簿登載者でなくなつた」とあるのは「参議院名簿登載者でなくなつた」と、「が第一項」とあるのは「が同条第一項」と、「衆議院名簿登載者の」とあるのは「参議院名簿登載者の」と、「衆議院名簿届出政党等」とあるのは「参議院名簿届出政党等」と、「第二項」とあるのは「同条第二項において準用する第二項」と、「においては、当該届出の際現に衆議院名簿登載者である」とあるのは「において、同条第一項後段の規定により優先的に当選人となるべき候補者としてその氏名及び当選人となるべき順位が参議院名簿に記載されている者が参議院名簿登載者でなくなつたときは、その参議院名簿登載者でなくなつた者の数を超えない範囲内において、当該届出により参議院名簿登載者とする者について、優先的に当選人となるべき候補者として、その氏名並びに同項後段の規定により優先的に当選人となるべき候補者としてその氏名及び当選人となるべき順位が参議院名簿に記載されている者の間における当選人となるべき順位を当該届出に係る文書に記載するとともに、当該届出の際現に同項後段の規定により優先的に当選人となるべき候補者としてその氏名及び当選人となるべき順位が参議院名簿に記載されている」と、同条第十項中「衆議院名簿届出政党等」とあるのは「参議院名簿届出政党等」と、「衆議院名簿」とあるのは「参議院名簿」と、同条第十一項中「第一項」とあるのは「次条第一項」と、「第八十七条第五項」とあるのは「第八十七条第六項において準用する同条第五項」と、「衆議院名簿」とあるのは「参議院名簿」と、「衆議院名簿登載者」とあるのは「参議院名簿登載者」と、同条第十二項中「違反してされたものであること又は当該届出の結果当該衆議院名簿登載者の数が第五項の規定に違反することとなつたこと」とあるのは「違反してされたものであること」と、同条第十三項中「第一項、第九項」とあるのは「次条第一項若しくはこの条第九項」と、「衆議院名簿」とあるのは「参議院名簿」と、「衆議院名簿登載者」とあるのは「参議院名簿登載者」と、同条第十四項中「第一項第一号」とあるのは「次条第一項第一号」と、「必要な事項」とあるのは「必要な事項並びに参議院(比例代表選出)議員の再選挙及び補欠選挙における第二項ただし書の規定の適用について必要な事項」と読み替えるものとする。
解説:
このように、第八十六条の三は、参議院比例代表選挙における候補者の届出に関する詳細な規定を示しており、政党や候補者の適格性、届出の手続き、不適格者の排除などが明確に定められています。
公職選挙法 第八十六条の四(衆議院議員又は参議院比例代表選出議員の選挙以外の選挙における候補者の立候補の届出等)
原文:
第八十六条の四 公職の候補者(衆議院議員又は参議院比例代表選出議員の候補者を除く。以下この条において同じ。)となろうとする者は、当該選挙の期日の公示又は告示があつた日に、郵便等によることなく、文書でその旨を当該選挙長に届け出なければならない。
2 選挙人名簿に登録された者が他人を公職の候補者としようとするときは、本人の承諾を得て、前項の公示又は告示があつた日に、郵便等によることなく、文書でその推薦の届出をすることができる。
3 前二項の文書には、公職の候補者となるべき者の氏名、本籍、住所、生年月日、職業及び所属する政党その他の政治団体の名称(二以上の政党その他の政治団体に所属するときは、いずれか一の政党その他の政治団体の名称とし、次項に規定する証明書に係る政党その他の政治団体の名称をいうものとする。)その他政令で定める事項を記載しなければならない。
4 第一項及び第二項の文書には、次の各号に掲げる選挙の区分に応じ当該各号に定める宣誓書、所属する政党その他の政治団体の名称を記載する場合にあつては当該記載に関する当該政党その他の政治団体の証明書(参議院選挙区選出議員の候補者については、当該政党その他の政治団体の代表者の証明書)その他政令で定める文書を添えなければならない。
一 参議院(選挙区選出)議員の選挙 第八十六条の八第一項、第八十七条第一項、第八十七条の二、第二百五十一条の二又は第二百五十一条の三の規定により当該選挙において公職の候補者となることができない者でないことを当該公職の候補者となるべき者が誓う旨の宣誓書
二 都道府県の議会の議員の選挙 当該選挙の期日において第九条第二項又は第三項に規定する住所に関する要件を満たす者であると見込まれること及び第八十六条の八第一項、第八十七条第一項、第二百五十一条の二又は第二百五十一条の三の規定により当該選挙において公職の候補者となることができない者でないことを当該公職の候補者となるべき者が誓う旨の宣誓書
三 市町村の議会の議員の選挙 当該選挙の期日において第九条第二項に規定する住所に関する要件を満たす者であると見込まれること及び第八十六条の八第一項、第八十七条第一項、第二百五十一条の二又は第二百五十一条の三の規定により当該選挙において公職の候補者となることができない者でないことを当該公職の候補者となるべき者が誓う旨の宣誓書
四 地方公共団体の長の選挙 第八十六条の八第一項、第八十七条第一項、第二百五十一条の二又は第二百五十一条の三の規定により当該選挙において公職の候補者となることができない者でないことを当該公職の候補者となるべき者が誓う旨の宣誓書
5 参議院(選挙区選出)議員又は地方公共団体の議会の議員の選挙については、第一項の公示又は告示があつた日に届出のあつた公職の候補者が、その選挙における議員の定数を超える場合において、その日後、当該候補者が死亡し又は公職の候補者たることを辞したものとみなされたときは、前各項の規定の例により、参議院(選挙区選出)議員又は都道府県若しくは市の議会の議員の選挙にあつてはその選挙の期日前三日までに、町村の議会の議員の選挙にあつてはその選挙の期日前二日までに、当該選挙における公職の候補者の届出をすることができる。
6 地方公共団体の長の選挙については、第一項の告示があつた日に届出のあつた候補者が二人以上ある場合において、その日後、当該候補者が死亡し又は候補者たることを辞したものとみなされたときは、第一項から第四項までの規定の例により、都道府県知事又は市長の選挙にあつてはその選挙の期日前三日までに、町村の長の選挙にあつてはその選挙の期日前二日までに、当該選挙における候補者の届出をすることができる。
7 地方公共団体の長の選挙について第一項、第二項又は前項の規定により届出のあつた候補者が二人以上ある場合において、その選挙の期日の前日までに、当該候補者が死亡し又は候補者たることを辞したものとみなされたため候補者が一人となつたときは、選挙の期日は、第三十三条第五項(第三十四条の二第五項において準用する場合を含む。)、第三十四条第六項又は第百十九条第三項の規定により告示した期日後五日に当たる日に延期するものとする。この場合においては、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会は、直ちにその旨を告示しなければならない。
8 前項又は第百二十六条第二項の場合においては、その告示があつた日から当該選挙の期日前三日までに、第一項から第四項までの規定の例により、当該地方公共団体の長の候補者の届出をすることができる。
9 第一項、第二項、第五項、第六項又は前項の規定により当該選挙において届出のあつた者が第八十六条の八第一項、第八十七条第一項、第八十七条の二、第八十八条、第二百五十一条の二又は第二百五十一条の三の規定により当該選挙において公職の候補者となり、又は公職の候補者であることができない者であることを知つたときは、選挙長は、その届出を却下しなければならない。
10 公職の候補者は、第一項又は第二項の規定により届出のあつた公職の候補者にあつては第一項の公示又は告示があつた日に、第五項、第六項又は第八項の規定により届出のあつた公職の候補者にあつては当該各項に定める日までに選挙長に届出をしなければ、その候補者たることを辞することができない。
11 第一項、第二項、第五項、第六項、第八項若しくは前項の規定による届出があつたとき、第九項の規定により届出を却下したとき又は公職の候補者が死亡し、若しくは第九十一条第二項若しくは第百三条第四項の規定に該当するに至つたことを知つたときは、選挙長は、直ちにその旨を告示するとともに、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(参議院合同選挙区選挙については、当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会)に報告しなければならない。
解説:
この規定は、衆議院議員や参議院比例代表選出議員以外の選挙における立候補届出の詳細な手続きと条件を示しています。
公職選挙法 第八十六条の五(候補者の選定の手続の届出等)
原文:
第八十六条の五 第八十六条第一項各号のいずれかに該当する政党その他の政治団体は、当該政党その他の政治団体の衆議院(小選挙区選出)議員の候補者となるべき者の選定及び衆議院名簿登載者の選定(以下この条において「候補者の選定」という。)の手続を定めたときは、その日から七日以内に、郵便等によることなく、文書でその旨を総務大臣に届け出なければならない。
2 前項の文書には、当該政党その他の政治団体の名称、本部の所在地及び代表者の氏名並びに候補者の選定を行う機関の名称、その構成員の選出方法及び候補者の選定の手続を記載するものとする。
3 第一項の文書には、当該政党その他の政治団体の綱領、党則、規約その他これらに相当するものを記載した文書及び第八十六条第一項各号のいずれかに該当することを証する政令で定める文書を添えなければならない。
4 第一項の規定による届出をした政党その他の政治団体は、同項の規定により届け出た事項に異動があつたときは、その異動の日から七日以内に、郵便等によることなく、文書でその異動に係る事項を総務大臣に届け出なければならない。
5 総務大臣は、第一項の規定による届出があつたときは、速やかに、当該届出に係る政党その他の政治団体の名称、本部の所在地及び代表者の氏名並びに候補者の選定を行う機関の名称、その構成員の選出方法及び候補者の選定の手続を告示しなければならない。これらの事項につき前項の規定による届出があつた場合も、同様とする。
6 第一項の規定による届出をした政党その他の政治団体は、第三項の文書の内容に異動があつたときは、その異動の日から七日以内に、文書でその異動に係る事項を総務大臣に届け出なければならない。
7 第一項の規定による届出をした政党その他の政治団体が解散し、又は第八十六条第一項各号のいずれかに該当する政党その他の政治団体でなくなつたときは、その代表者は、その事実が生じた日から七日以内に、文書でその旨を総務大臣に届け出なければならない。この場合においては、総務大臣は、その旨の告示をしなければならない。
解説:
公職選挙法 第八十六条の六(衆議院比例代表選出議員の選挙における政党その他の政治団体の名称の届出等)
原文:
第八十六条の六 第八十六条の二第一項に規定する政党その他の政治団体のうち同項第一号又は第二号に該当する政党その他の政治団体は、衆議院議員の総選挙の期日から三十日以内(当該期間が衆議院の解散の日にかかる場合にあつては、当該解散の日までの間)に、郵便等によることなく、文書で、当該政党その他の政治団体の名称及び一の略称を中央選挙管理会に届け出るものとする。この場合において、当該名称及び略称は、その代表者若しくはいずれかの選挙区において衆議院名簿登載者としようとする者の氏名が表示され、又はそれらの者の氏名が類推されるような名称及び略称であつてはならない。
2 第八十六条の二第一項に規定する政党その他の政治団体のうち同項第一号又は第二号に該当する政党その他の政治団体は、衆議院議員の総選挙の期日後二十四日を経過する日から当該衆議院議員の任期満了の日前九十日に当たる日又は衆議院の解散の日のいずれか早い日までの間に同項第一号又は第二号に該当することとなつたときは、前項前段の規定にかかわらず、その該当することとなつた日から七日以内(当該期間が衆議院の解散の日にかかる場合にあつては、当該解散の日までの間)に、郵便等によることなく、文書で、当該政党その他の政治団体の名称及び一の略称を中央選挙管理会に届け出るものとする。この場合においては、同項後段の規定を準用する。
3 前二項の文書には、当該政党その他の政治団体の名称及び一の略称、本部の所在地、代表者の氏名その他政令で定める事項を記載しなければならない。
4 第一項及び第二項の文書には、当該政党その他の政治団体の綱領、党則、規約その他これらに相当するものを記載した文書及び当該政党その他の政治団体が第八十六条の二第一項第一号又は第二号に該当することを証する政令で定める文書を添えなければならない。
5 第一項又は第二項の規定による届出をした政党その他の政治団体は、これらの規定による届出をした日後衆議院議員の任期満了の日前九十日に当たる日又は衆議院の解散の日のいずれか早い日までの間に、これらの規定により届け出た事項に異動があつたときは、その異動の日から七日以内(当該期間が衆議院の解散の日にかかる場合にあつては、当該解散の日までの間)に、郵便等によることなく、文書でその異動に係る事項を中央選挙管理会に届け出なければならない。
6 中央選挙管理会は、第一項又は第二項の規定による届出があつたときは、速やかに、これらの規定による届出に係る政党その他の政治団体の名称及び略称、本部の所在地並びに代表者の氏名を告示しなければならない。これらの事項につき前項の規定による届出があつたときも、同様とする。
7 第一項又は第二項の規定による届出をした政党その他の政治団体は、第四項の文書の内容に異動があつたときは、その異動の日から七日以内に、文書でその異動に係る事項を中央選挙管理会に届け出なければならない。
8 第一項又は第二項の規定による届出をした政党その他の政治団体が、これらの規定による届出をした日後衆議院議員の任期満了の日前九十日に当たる日又は衆議院の解散の日のいずれか早い日までの間に、解散し又は第八十六条の二第一項第一号若しくは第二号に該当する政党その他の政治団体でなくなつたときは、その代表者は、その事実が生じた日から七日以内に、文書でその旨を中央選挙管理会に届け出なければならない。この場合においては、中央選挙管理会は、その旨の告示をしなければならない。
9 第一項又は第二項の規定による届出をした政党その他の政治団体は、衆議院議員の任期満了の日前九十日に当たる日又は衆議院の解散の日のいずれか早い日後においても、郵便等によることなく、文書で、中央選挙管理会に当該届出を撤回する旨の届出をすることができる。この場合においては、中央選挙管理会は、その旨の告示をしなければならない。
10 衆議院(比例代表選出)議員の再選挙及び補欠選挙における第一項、第二項、第五項又は第七項から前項までの規定の適用について必要な事項は、政令で定める。
解説:
公職選挙法 第八十六条の七(参議院比例代表選出議員の選挙における政党その他の政治団体の名称の届出等)
原文:
第八十六条の七 第八十六条の三第一項に規定する政党その他の政治団体のうち同項第一号又は第二号に該当する政党その他の政治団体は、参議院議員の任期満了の日前九十日に当たる日から七日を経過する日までの間に、郵便等によることなく、文書で、当該政党その他の政治団体の名称及び一の略称を中央選挙管理会に届け出るものとする。この場合において、当該名称及び略称は、その代表者若しくは参議院名簿登載者としようとする者の氏名が表示され、又はそれらの者の氏名が類推されるような名称及び略称であつてはならない。
2 前項の文書には、当該政党その他の政治団体の名称及び一の略称、本部の所在地、代表者の氏名その他政令で定める事項を記載しなければならない。
3 第一項の文書には、当該政党その他の政治団体の綱領、党則、規約その他これらに相当するものを記載した文書及び当該政党その他の政治団体が第八十六条の三第一項第一号又は第二号に該当することを証する政令で定める文書を添えなければならない。
4 中央選挙管理会は、第一項の期間経過後速やかに、同項の規定による届出に係る政党その他の政治団体の名称及び略称、本部の所在地並びに代表者の氏名を告示しなければならない。
5 第一項の規定による届出をした政党その他の政治団体は、前項の規定による告示があつた日以後においても、郵便等によることなく文書で、中央選挙管理会に当該届出を撤回する旨の届出をすることができる。この場合においては、中央選挙管理会は、その旨の告示をしなければならない。
6 参議院(比例代表選出)議員の再選挙及び補欠選挙における第一項の規定の適用について必要な事項は、政令で定める。
解説:
公職選挙法 第八十六条の八(被選挙権のない者等の立候補の禁止)
原文:
第八十六条の八 第十一条第一項、第十一条の二若しくは第二百五十二条又は政治資金規正法第二十八条の規定により被選挙権を有しない者は、公職の候補者となり、又は公職の候補者であることができない。
2 第二百五十一条の二第一項各号に掲げる者又は第二百五十一条の三第一項に規定する組織的選挙運動管理者等の選挙に関する犯罪により公職の候補者となり、又は公職の候補者であることができない者については、これらの条の定めるところによる。
解説:
公職選挙法 第八十七条(重複立候補等の禁止)
原文:
第八十七条 一の選挙において公職の候補者となつた者は、同時に、他の選挙における公職の候補者となることができない。
2 衆議院(小選挙区選出)議員の選挙において、一の政党その他の政治団体の届出に係る候補者は、当該選挙において、同時に、他の政党その他の政治団体の届出に係る候補者であることができない。
3 衆議院(小選挙区選出)議員の選挙において、候補者届出政党は、一の選挙区においては、重ねて候補者の届出をすることができない。
4 一の衆議院名簿の公職の候補者たる衆議院名簿登載者は、当該選挙において、同時に、他の衆議院名簿の公職の候補者たる衆議院名簿登載者であることができない。
5 衆議院(比例代表選出)議員の選挙において、衆議院名簿届出政党等は、一の選挙区においては、重ねて衆議院名簿を届け出ることができない。
6 前二項の規定は、参議院(比例代表選出)議員の選挙について準用する。この場合において、第四項中「衆議院名簿」とあるのは「参議院名簿」と、「衆議院名簿登載者」とあるのは「参議院名簿登載者」と、前項中「衆議院名簿届出政党等」とあるのは「参議院名簿届出政党等」と、「一の選挙区においては、重ねて」とあるのは「重ねて」と、「衆議院名簿」とあるのは「参議院名簿」と読み替えるものとする。
解説:
公職選挙法 第八十七条の二(衆議院小選挙区選出議員又は参議院選挙区選出議員たることを辞した者等の立候補制限)
原文:
第八十七条の二 国会法(昭和二十二年法律第七十九号)第百七条の規定により衆議院(小選挙区選出)議員若しくは参議院(選挙区選出)議員たることを辞した者又は第九十条の規定により衆議院(小選挙区選出)議員若しくは参議院(選挙区選出)議員たることを辞したものとみなされた者は、当該辞し、又は辞したものとみなされたことにより生じた欠員について行われる補欠選挙(通常選挙と合併して一の選挙として行われる選挙を除く。)における候補者となることができない。
解説:
公職選挙法 第八十八条(選挙事務関係者の立候補制限)
原文:
第八十八条 左の各号に掲げる者は、在職中、その関係区域内において、当該選挙の公職の候補者となることができない。
一 投票管理者
二 開票管理者
三 選挙長及び選挙分会長
解説:
公職選挙法 第八十九条(公務員の立候補制限)
原文:
第八十九条 国若しくは地方公共団体の公務員又は行政執行法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第四項に規定する行政執行法人をいう。以下同じ。)若しくは特定地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第二項に規定する特定地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の役員若しくは職員は、在職中、公職の候補者となることができない。ただし、次の各号に掲げる公務員(行政執行法人又は特定地方独立行政法人の役員及び職員を含む。次条及び第百三条第三項において同じ。)は、この限りでない。
一 内閣総理大臣その他の国務大臣、内閣官房副長官、内閣総理大臣補佐官、副大臣、大臣政務官及び大臣補佐官
二 技術者、監督者及び行政事務を担当する者以外の者で、政令で指定するもの
三 専務として委員、顧問、参与、嘱託員その他これらに準ずる職にある者で臨時又は非常勤のものにつき、政令で指定するもの
四 消防団長その他の消防団員(常勤の者を除く。)及び水防団長その他の水防団員(常勤の者を除く。)
五 地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和二十七年法律第二百八十九号)第三条第四号に規定する職員で、政令で指定するもの
2 衆議院議員の任期満了による総選挙又は参議院議員の通常選挙が行われる場合においては、当該衆議院議員又は参議院議員は、前項本文の規定にかかわらず、在職中その選挙における公職の候補者となることができる。地方公共団体の議会の議員又は長の任期満了による選挙が行われる場合において当該議員又は長がその選挙における公職の候補者となる場合も、また同様とする。
3 第一項本文の規定は、同項第一号、第二号、第四号及び第五号に掲げる者並びに前項に規定する者がその職に伴い兼ねている国若しくは地方公共団体の公務員又は行政執行法人若しくは特定地方独立行政法人の役員若しくは職員たる地位に影響を及ぼすものではない。
解説:
公職選挙法 第九十条(立候補のための公務員の退職)
原文:
第九十条 前条の規定により公職の候補者となることができない公務員が、第八十六条第一項から第三項まで若しくは第八項、第八十六条の二第一項若しくは第九項、第八十六条の三第一項若しくは同条第二項において準用する第八十六条の二第九項又は第八十六条の四第一項、第二項、第五項、第六項若しくは第八項の規定による届出により公職の候補者となつたときは、当該公務員の退職に関する法令の規定にかかわらず、その届出の日に当該公務員たることを辞したものとみなす。
解説:
公職選挙法 第九十一条(公務員となつた候補者の取扱い)
原文:
第九十一条 第八十六条第一項又は第八項の規定により候補者として届出のあつた者(候補者届出政党の届出に係るものに限る。)が、第八十八条又は第八十九条の規定により公職の候補者となることができない者となつたときは、当該届出は、取り下げられたものとみなす。
2 第八十六条第二項、第三項若しくは第八項又は第八十六条の四第一項、第二項、第五項、第六項若しくは第八項の規定により公職の候補者として届出のあつた者(候補者届出政党の届出に係るものを除く。)が、第八十八条又は第八十九条の規定により公職の候補者となることができない者となつたときは、その候補者たることを辞したものとみなす。
3 衆議院(比例代表選出)議員又は参議院(比例代表選出)議員の選挙において、衆議院名簿登載者又は参議院名簿登載者が第八十八条又は第八十九条の規定により公職の候補者となることができない者となつたときは、その者は、公職の候補者たる衆議院名簿登載者又は参議院名簿登載者でなくなるものとする。
解説:
公職選挙法 第九十二条(供託)
原文:
第九十二条 第八十六条第一項から第三項まで若しくは第八項又は第八十六条の四第一項、第二項、第五項、第六項若しくは第八項の規定により公職の候補者の届出をしようとするものは、公職の候補者一人につき、次の各号の区分による金額又はこれに相当する額面の国債証書(その権利の帰属が社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされるものを含む。以下この条において同じ。)を供託しなければならない。
一 衆議院(小選挙区選出)議員の選挙 三百万円
二 参議院(選挙区選出)議員の選挙 三百万円
三 都道府県の議会の議員の選挙 六十万円
四 都道府県知事の選挙 三百万円
五 指定都市の議会の議員の選挙 五十万円
六 指定都市の長の選挙 二百四十万円
七 指定都市以外の市の議会の議員の選挙 三十万円
八 指定都市以外の市の長の選挙 百万円
九 町村の議会の議員の選挙 十五万円
十 町村長の選挙 五十万円
2 第八十六条の二第一項の規定により届出をしようとする政党その他の政治団体は、選挙区ごとに、当該衆議院名簿の衆議院名簿登載者一人につき、六百万円(当該衆議院名簿登載者が当該衆議院比例代表選出議員の選挙と同時に行われる衆議院小選挙区選出議員の選挙における候補者(候補者となるべき者を含む。)である場合にあつては、三百万円)又はこれに相当する額面の国債証書を供託しなければならない。
3 第八十六条の三第一項の規定により届出をしようとする政党その他の政治団体は、当該参議院名簿の参議院名簿登載者一人につき、六百万円又はこれに相当する額面の国債証書を供託しなければならない。
解説:
公職選挙法 第九十三条(公職の候補者に係る供託物の没収)
原文:
第九十三条 第八十六条第一項から第三項まで若しくは第八項又は第八十六条の四第一項、第二項、第五項、第六項若しくは第八項の規定により届出のあつた公職の候補者の得票数が、その選挙において、次の各号の区分による数に達しないときは、前条第一項の供託物は、衆議院(小選挙区選出)議員又は参議院(選挙区選出)議員の選挙にあつては国庫に、地方公共団体の議会の議員又は長の選挙にあつては当該地方公共団体に帰属する。
一 衆議院(小選挙区選出)議員の選挙 有効投票の総数の十分の一
二 参議院(選挙区選出)議員の選挙 通常選挙における当該選挙区内の議員の定数をもつて有効投票の総数を除して得た数の八分の一。ただし、選挙すべき議員の数が通常選挙における当該選挙区内の議員の定数を超える場合においては、その選挙すべき議員の数をもつて有効投票の総数を除して得た数の八分の一
三 地方公共団体の議会の議員の選挙 当該選挙区内の議員の定数(選挙区がないときは、議員の定数)をもつて有効投票の総数を除して得た数の十分の一
四 地方公共団体の長の選挙 有効投票の総数の十分の一
2 前項の規定は、同項に規定する公職の候補者の届出が取り下げられ、又は公職の候補者が当該候補者たることを辞した場合(第九十一条第一項又は第二項の規定に該当するに至つた場合を含む。)及び前項に規定する公職の候補者の届出が第八十六条第九項又は第八十六条の四第九項の規定により却下された場合に、準用する。
解説:
公職選挙法 第九十四条(名簿届出政党等に係る供託物の没収)
原文:
第九十四条 衆議院(比例代表選出)議員の選挙において、衆議院名簿届出政党等につき、選挙区ごとに、三百万円に第一号に掲げる数を乗じて得た金額と六百万円に第二号に掲げる数を乗じて得た金額を合算して得た額が当該衆議院名簿届出政党等に係る第九十二条第二項の供託物の額に達しないときは、当該供託物のうち、当該供託物の額から当該合算して得た額を減じて得た額に相当する額の供託物は、国庫に帰属する。
一 当該衆議院名簿届出政党等の届出に係る衆議院名簿の衆議院名簿登載者のうち、当該選挙と同時に行われた衆議院(小選挙区選出)議員の選挙の当選人とされた者の数
二 当該衆議院名簿届出政党等に係る当選人の数に二を乗じて得た数
2 第八十六条の二第十項の規定により衆議院名簿を取り下げ、又は同条第十一項の規定により同条第一項の規定による届出を却下された政党その他の政治団体に係る第九十二条第二項の供託物は、国庫に帰属する。
3 参議院(比例代表選出)議員の選挙において、参議院名簿届出政党等につき、第一号に掲げる数が第二号に掲げる数に達しないときは、当該参議院名簿届出政党等に係る第九十二条第三項の供託物のうち六百万円に同号に掲げる数から第一号に掲げる数を減じて得た数を乗じて得た金額に相当する額の供託物は、国庫に帰属する。
一 当該参議院名簿届出政党等に係る当選人の数に二を乗じて得た数
二 第八十六条の三第一項の規定による届出のときにおける参議院名簿登載者の数
4 第八十六条の三第二項において準用する第八十六条の二第十項の規定により参議院名簿を取り下げ、又は第八十六条の三第二項において準用する第八十六条の二第十一項の規定により第八十六条の三第一項の規定による届出を却下された政党その他の政治団体に係る第九十二条第三項の供託物は、国庫に帰属する。
解説:
第十章 当選人
公職選挙法 第九十五条(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙以外の選挙における当選人)
原文:
第九十五条 衆議院(比例代表選出)議員又は参議院(比例代表選出)議員の選挙以外の選挙においては、有効投票の最多数を得た者をもつて当選人とする。ただし、次の各号の区分による得票がなければならない。
一 衆議院(小選挙区選出)議員の選挙 有効投票の総数の六分の一以上の得票
二 参議院(選挙区選出)議員の選挙 通常選挙における当該選挙区内の議員の定数をもつて有効投票の総数を除して得た数の六分の一以上の得票。ただし、選挙すべき議員の数が通常選挙における当該選挙区内の議員の定数を超える場合においては、その選挙すべき議員の数をもつて有効投票の総数を除して得た数の六分の一以上の得票
三 地方公共団体の議会の議員の選挙 当該選挙区内の議員の定数(選挙区がないときは、議員の定数)をもつて有効投票の総数を除して得た数の四分の一以上の得票
四 地方公共団体の長の選挙 有効投票の総数の四分の一以上の得票
2 当選人を定めるに当り得票数が同じであるときは、選挙会において、選挙長がくじで定める。
解説:
公職選挙法 第九十五条の二(衆議院比例代表選出議員の選挙における当選人の数及び当選人)
原文:
第九十五条の二 衆議院(比例代表選出)議員の選挙においては、各衆議院名簿届出政党等の得票数を一から当該衆議院名簿届出政党等に係る衆議院名簿登載者(当該選挙の期日において公職の候補者たる者に限る。第百三条第四項を除き、以下この章及び次章において同じ。)の数に相当する数までの各整数で順次除して得たすべての商のうち、その数値の最も大きいものから順次に数えて当該選挙において選挙すべき議員の数に相当する数になるまでにある商で各衆議院名簿届出政党等の得票数に係るものの個数をもつて、それぞれの衆議院名簿届出政党等の当選人の数とする。
2 前項の場合において、二以上の商が同一の数値であるため同項の規定によつてはそれぞれの衆議院名簿届出政党等に係る当選人の数を定めることができないときは、それらの商のうち、当該選挙において選挙すべき議員の数に相当する数になるまでにあるべき商を、選挙会において、選挙長がくじで定める。
3 衆議院名簿において、第八十六条の二第六項の規定により二人以上の衆議院名簿登載者について当選人となるべき順位が同一のものとされているときは、当該当選人となるべき順位が同一のものとされた者の間における当選人となるべき順位は、当該選挙と同時に行われた衆議院(小選挙区選出)議員の選挙における得票数の当該選挙区における有効投票の最多数を得た者に係る得票数に対する割合の最も大きい者から順次に定める。この場合において、当選人となるべき順位が同一のものとされた衆議院名簿登載者のうち、当該割合が同じであるものがあるときは、それらの者の間における当選人となるべき順位は、選挙会において、選挙長がくじで定める。
4 衆議院(比例代表選出)議員の選挙においては、各衆議院名簿届出政党等の届出に係る衆議院名簿登載者のうち、それらの者の間における当選人となるべき順位に従い、第一項及び第二項の規定により定められた当該衆議院名簿届出政党等の当選人の数に相当する数の衆議院名簿登載者を、当選人とする。
5 第一項、第二項及び前項の場合において、当該選挙と同時に行われた衆議院(小選挙区選出)議員の選挙の当選人とされた衆議院名簿登載者があるときは、当該衆議院名簿登載者は、衆議院名簿に記載されていないものとみなして、これらの規定を適用する。
6 第一項、第二項及び第四項の場合において、当該選挙と同時に行われた衆議院(小選挙区選出)議員の選挙においてその得票数が第九十三条第一項第一号に規定する数に達しなかつた衆議院名簿登載者があるときは、当該衆議院名簿登載者は、衆議院名簿に記載されていないものとみなして、これらの規定を適用する。
解説:
公職選挙法 第九十五条の三(参議院比例代表選出議員の選挙における当選人の数及び当選人となるべき順位並びに当選人)
原文:
第九十五条の三 参議院(比例代表選出)議員の選挙においては、各参議院名簿届出政党等の得票数(当該参議院名簿届出政党等に係る各参議院名簿登載者(当該選挙の期日において公職の候補者たる者に限る。第百三条第四項を除き、以下この章及び次章において同じ。)の得票数を含むものをいう。)を一から当該参議院名簿届出政党等に係る参議院名簿登載者の数に相当する数までの各整数で順次除して得たすべての商のうち、その数値の最も大きいものから順次に数えて当該選挙において選挙すべき議員の数に相当する数になるまでにある商で各参議院名簿届出政党等の得票数(当該参議院名簿届出政党等に係る各参議院名簿登載者の得票数を含むものをいう。)に係るものの個数をもつて、それぞれの参議院名簿届出政党等の当選人の数とする。
2 前項の場合において、二以上の商が同一の数値であるため同項の規定によつてはそれぞれの参議院名簿届出政党等に係る当選人の数を定めることができないときは、それらの商のうち、当該選挙において選挙すべき議員の数に相当する数になるまでにあるべき商を、選挙会において、選挙長がくじで定める。
3 各参議院名簿届出政党等(次項に規定する参議院名簿届出政党等を除く。)の届出に係る参議院名簿において、参議院名簿登載者の間における当選人となるべき順位は、その得票数の最も多い者から順次に定める。この場合において、その得票数が同じである者があるときは、それらの者の間における当選人となるべき順位は、選挙会において、選挙長がくじで定める。
4 参議院名簿届出政党等であつて、その届出に係る参議院名簿登載者のうちに第八十六条の三第一項後段の規定により優先的に当選人となるべき候補者としてその氏名及び当選人となるべき順位が参議院名簿に記載されている者である参議院名簿登載者があるものの届出に係る各参議院名簿において、当該参議院名簿登載者の当選人となるべき順位は、その他の参議院名簿登載者の当選人となるべき順位より上位とし、当該その他の参議院名簿登載者の間における当選人となるべき順位は、その得票数の最も多い者から順次に定める。この場合において、当該その他の参議院名簿登載者のうちにその得票数が同じである者があるときは、前項後段の規定を準用する。
5 参議院(比例代表選出)議員の選挙においては、各参議院名簿届出政党等の届出に係る参議院名簿登載者のうち、それらの者の間における当選人となるべき順位に従い、第一項及び第二項の規定により定められた当該参議院名簿届出政党等の当選人の数に相当する数の参議院名簿登載者を、当選人とする。
解説:
公職選挙法 第九十六条(当選人の更正決定)
原文:
第九十六条 第二百六条、第二百七条第一項又は第二百八条第一項の規定による異議の申出、審査の申立て又は訴訟の結果、再選挙を行わないで当選人(衆議院比例代表選出議員の選挙にあつては衆議院名簿届出政党等に係る当選人の数又は当選人、参議院比例代表選出議員の選挙にあつては参議院名簿届出政党等に係る当選人の数若しくは当選人となるべき順位又は当選人。以下この条において同じ。)を定めることができる場合においては、直ちに選挙会を開き、当選人を定めなければならない。
解説:
公職選挙法 第九十七条(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙以外の選挙における当選人の繰上補充)
原文:
第九十七条 衆議院(比例代表選出)議員又は参議院(比例代表選出)議員の選挙以外の選挙について、当選人が死亡者であるとき又は第九十九条、第百三条第二項若しくは第四項若しくは第百四条の規定により当選を失つたときは、直ちに選挙会を開き、第九十五条第一項ただし書の規定による得票者で当選人とならなかつたもの(衆議院小選挙区選出議員又は地方公共団体の長の選挙については、同条第二項の規定の適用を受けた得票者で当選人とならなかつたもの)の中から当選人を定めなければならない。
2 参議院(選挙区選出)議員又は地方公共団体の議会の議員の選挙について、第百九条第五号若しくは第六号の事由がその選挙の期日から三箇月以内に生じた場合において第九十五条第一項ただし書の規定による得票者で当選人とならなかつたものがあるとき又はこれらの事由がその選挙の期日から三箇月経過後に生じた場合において同条第二項の規定の適用を受けた得票者で当選人とならなかつたものがあるときは、直ちに選挙会を開き、その者の中から当選人を定めなければならない。
3 衆議院(小選挙区選出)議員又は地方公共団体の長の選挙について、第百九条第五号又は第六号の事由が生じた場合において、第九十五条第二項の規定の適用を受けた得票者で当選人とならなかつたものがあるときは、直ちに選挙会を開き、その者の中から当選人を定めなければならない。
解説:
公職選挙法 第九十七条の二(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙における当選人の繰上補充)
原文:
第九十七条の二 衆議院(比例代表選出)議員の選挙について、当選人が死亡者である場合、第九十九条、第九十九条の二第一項(同条第五項において準用する場合を含む。)若しくは第百三条第二項若しくは第四項の規定により当選を失つた場合又は第二百五十一条、第二百五十一条の二若しくは第二百五十一条の三の規定により当選が無効となつた場合において、当該当選人に係る衆議院名簿の衆議院名簿登載者で当選人とならなかつたものがあるときは、直ちに選挙会を開き、その者の中から、その衆議院名簿における当選人となるべき順位に従い、当選人を定めなければならない。
2 第九十五条の二第五項及び第六項の規定は、前項の場合について準用する。
3 第一項の規定は、参議院(比例代表選出)議員の選挙について準用する。この場合において、同項中「第九十九条の二第一項(同条第五項において準用する場合を含む。)」とあるのは「第九十九条の二第六項において準用する同条第一項(同条第五項において準用する場合を含む。)」と、「若しくは第二百五十一条の三」とあるのは「、第二百五十一条の三若しくは第二百五十一条の四」と、「衆議院名簿の衆議院名簿登載者」とあるのは「参議院名簿の参議院名簿登載者」と、「その衆議院名簿」とあるのは「その参議院名簿に係る参議院名簿登載者の間」と読み替えるものとする。
解説:
公職選挙法 第九十八条(被選挙権の喪失と当選人の決定等)
原文:
第九十八条 前三条の場合において、第九十五条第一項ただし書の規定による得票者、同条第二項の規定の適用を受けた得票者、衆議院名簿登載者又は参議院名簿登載者で、当選人とならなかつたものが、その選挙の期日後において被選挙権を有しなくなつたとき又は第二百五十一条の二若しくは第二百五十一条の三の規定により当該選挙に係る第二百五十一条の二第一項各号に掲げる者若しくは第二百五十一条の三第一項に規定する組織的選挙運動管理者等の選挙に関する犯罪によつて当該選挙に係る選挙区(選挙区がないときは、選挙の行われる区域)において行われる当該公職に係る選挙において公職の候補者となり若しくは公職の候補者であることができない者となつたときは、これを当選人と定めることができない。衆議院名簿登載者で当選人とならなかつたものが、第二百五十一条の二又は第二百五十一条の三の規定により当該選挙と同時に行われた衆議院(小選挙区選出)議員の選挙に係る第二百五十一条の二第一項各号に掲げる者又は第二百五十一条の三第一項に規定する組織的選挙運動管理者等の選挙に関する犯罪によつて当該衆議院(小選挙区選出)議員の選挙に係る選挙区において行われる当該衆議院(小選挙区選出)議員の選挙において公職の候補者となり又は公職の候補者であることができない者となつたときも、また同様とする。
2 衆議院(小選挙区選出)議員の選挙に係る第九十六条又は第九十七条の場合において、候補者届出政党が届け出た候補者であつた者のうち、第九十五条第一項ただし書の規定による得票者又は同条第二項の規定の適用を受けた得票者で当選人とならなかつたものにつき除名、離党その他の事由により当該候補者届出政党に所属する者でなくなつた旨の届出が、文書で、第九十六条又は第九十七条に規定する事由が生じた日の前日までに選挙長にされているときは、これを当選人と定めることができない。
3 衆議院(比例代表選出)議員又は参議院(比例代表選出)議員の選挙に係る第九十六条又は前条の場合において、衆議院名簿登載者又は参議院名簿登載者で、当選人とならなかつたものにつき除名、離党その他の事由により当該衆議院名簿届出政党等又は参議院名簿届出政党等に所属する者でなくなつた旨の届出が、文書で、これらの条に規定する事由が生じた日の前日までに選挙長にされているときは、これを当選人と定めることができない。衆議院名簿又は参議院名簿を取り下げる旨の届出が、文書で、これらの条に規定する事由が生じた日の前日までに選挙長にされている場合の当該衆議院名簿の衆議院名簿登載者又は参議院名簿の参議院名簿登載者で、当選人とならなかつたものについても、また同様とする。
4 第八十六条第十項の規定は第二項の届出について、第八十六条の二第八項及び第十項後段(これらの規定を第八十六条の三第二項において準用する場合を含む。)の規定は前項の届出について準用する。
解説:
公職選挙法 第九十九条(被選挙権の喪失に因る当選人の失格)
原文:
第九十九条 当選人は、その選挙の期日後において被選挙権を有しなくなつたときは、当選を失う。
解説:
公職選挙法 第九十九条の二(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙における所属政党等の移動による当選人の失格)
原文:
第九十九条の二 衆議院(比例代表選出)議員の選挙における当選人(第九十六条、第九十七条の二第一項又は第百十二条第二項の規定により当選人と定められた者を除く。以下この項から第四項までにおいて同じ。)は、その選挙の期日以後において、当該当選人が衆議院名簿登載者であつた衆議院名簿届出政党等以外の政党その他の政治団体で、当該選挙における衆議院名簿届出政党等であるもの(当該当選人が衆議院名簿登載者であつた衆議院名簿届出政党等(当該衆議院名簿届出政党等に係る合併又は分割(二以上の政党その他の政治団体の設立を目的として一の政党その他の政治団体が解散し、当該二以上の政党その他の政治団体が設立されることをいう。)が行われた場合における当該合併後に存続する政党その他の政治団体若しくは当該合併により設立された政党その他の政治団体又は当該分割により設立された政党その他の政治団体を含む。)を含む二以上の政党その他の政治団体の合併により当該合併後に存続するものを除く。第四項において「他の衆議院名簿届出政党等」という。)に所属する者となつたときは、当選を失う。
2 衆議院(比例代表選出)議員の選挙における当選人が、除名、離党その他の事由により当該当選人が衆議院名簿登載者であつた衆議院名簿届出政党等に所属する者でなくなつた場合は、当該衆議院名簿届出政党等は、直ちに文書でその旨を選挙長に届け出なければならない。この場合において、選挙長は、直ちにその旨を当該当選人に通知しなければならない。
3 前項前段の文書には、当該届出に係る事由が、除名である場合にあつては当該除名の手続を記載した文書を、離党である場合にあつては当該当選人が衆議院名簿届出政党等に提出した離党届の写しを、その他の事由である場合にあつては当該事由を証する文書を、それぞれ、添えなければならない。
4 第二項の通知を受けた当選人は、当該当選人がその選挙の期日以後において他の衆議院名簿届出政党等に所属していない場合には、当該当選人がその選挙の期日以後において他の衆議院名簿届出政党等に所属していないことを誓う旨の宣誓書を、当該通知を受けた日から五日以内に選挙長に提出しなければならない。
5 前各項の規定は、衆議院(比例代表選出)議員の選挙における当選人で第九十六条、第九十七条の二第一項又は第百十二条第二項の規定により当選人と定められたものについて準用する。この場合において、第一項中「その選挙の期日」とあるのは「第九十六条、第九十七条の二第一項又は第百十二条第二項の規定により当該当選人が選挙会において当選人と定められた日」と、「所属する者となつたとき」とあるのは「所属する者となつたとき(第九十六条、第九十七条の二第一項又は第百十二条第二項の規定により当該当選人が選挙会において当選人と定められた日において所属する者である場合を含む。)」と、前項中「その選挙の期日」とあるのは「第九十六条、第九十七条の二第一項又は第百十二条第二項の規定により当該当選人が選挙会において当選人と定められた日」と読み替えるものとする。
6 前各項の規定は、参議院(比例代表選出)議員の選挙における当選人について準用する。この場合において、第一項中「第九十七条の二第一項」とあるのは「第九十七条の二第三項において準用する同条第一項」と、「第百十二条第二項」とあるのは「第百十二条第四項において準用する同条第二項」と、「衆議院名簿登載者」とあるのは「参議院名簿登載者」と、「衆議院名簿届出政党等」とあるのは「参議院名簿届出政党等」と、第二項中「衆議院名簿登載者」とあるのは「参議院名簿登載者」と、「衆議院名簿届出政党等」とあるのは「参議院名簿届出政党等」と、「所属する者」とあるのは「所属する者(当該参議院名簿届出政党等が推薦する者を含む。)」と、第三項及び第四項中「衆議院名簿届出政党等」とあるのは「参議院名簿届出政党等」と、前項中「第九十七条の二第一項」とあるのは「第九十七条の二第三項において準用する同条第一項」と、「第百十二条第二項」とあるのは「第百十二条第四項において準用する同条第二項」と読み替えるものとする。
解説:
公職選挙法 第百条(無投票当選)
原文:
第百条 衆議院(小選挙区選出)議員の選挙において、第八十六条第一項から第三項まで又は第八項の規定による届出のあつた候補者が一人であるとき又は一人となつたときは、投票は、行わない。
2 衆議院(比例代表選出)議員の選挙において、第八十六条の二第一項若しくは第九項の規定による届出に係る衆議院名簿登載者の総数がその選挙において選挙すべき議員の数を超えないとき若しくは超えなくなつたとき又は同条第一項の規定による届出をした衆議院名簿届出政党等が一であるとき若しくは一となつたときは、投票は、行わない。
3 参議院(比例代表選出)議員の選挙において、第八十六条の三第一項又は同条第二項において準用する第八十六条の二第九項の規定による届出に係る参議院名簿登載者の総数がその選挙において選挙すべき議員の数を超えないとき又は超えなくなつたときは、投票は、行わない。
4 参議院(選挙区選出)議員若しくは地方公共団体の議会の議員の選挙において第八十六条の四第一項、第二項若しくは第五項の規定による届出のあつた候補者の総数がその選挙において選挙すべき議員の数を超えないとき若しくは超えなくなつたとき又は地方公共団体の長の選挙において同条第一項、第二項、第六項若しくは第八項の規定による届出のあつた候補者が一人であるとき若しくは一人となつたときは、投票は、行わない。
5 前各項又は第百二十七条の規定により投票を行わないこととなつたときは、選挙長は、直ちにその旨を当該選挙の各投票管理者に通知し、併せてこれを告示し、かつ、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙については中央選挙管理会、参議院合同選挙区選挙については当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会)に報告しなければならない。
6 第一項から第四項まで(第二項の規定の適用がある場合であつて、衆議院比例代表選出議員の選挙が衆議院小選挙区選出議員の選挙と同時に行われる場合を除く。)又は第百二十七条の場合においては、選挙長は、その選挙の期日から五日以内に選挙会を開き、当該公職の候補者をもつて当選人と定めなければならない。
7 前項に規定する場合を除くほか、衆議院(比例代表選出)議員の選挙において、第八十六条の二第一項又は第九項の規定による届出に係る衆議院名簿登載者の総数がその選挙において選挙すべき議員の数を超えないとき又は超えなくなつたときは、選挙長は、次条第四項の規定による通知があつた日又はその翌日に選挙会を開き、当該衆議院名簿登載者をもつて当選人と定めなければならない。この場合においては、第九十五条の二第五項及び第六項の規定を準用する。
8 前二項に規定する場合を除くほか、衆議院(比例代表選出)議員の選挙において、第八十六条の二第一項の規定による届出をした衆議院名簿届出政党等が一であるとき又は一となつたときは、選挙長は、次条第四項の規定による通知があつた日又はその翌日に選挙会を開き、当該衆議院名簿届出政党等の届出に係る衆議院名簿登載者のうち、その衆議院名簿における当選人となるべき順位に従い、その選挙において選挙すべき議員の数に相当する数の衆議院名簿登載者をもつて当選人と定めなければならない。この場合においては、第九十五条の二第三項、第五項及び第六項の規定を準用する。
9 前三項の場合において、当該公職の候補者の被選挙権の有無は、選挙立会人の意見を聴き、選挙長が決定しなければならない。
解説:
公職選挙法 第百一条(衆議院小選挙区選出議員の選挙における当選人決定の場合の報告、告知及び告示)
原文:
第百一条 衆議院(小選挙区選出)議員の選挙において、当選人が定まつたときは、選挙長は、直ちに当選人の住所、氏名及び得票数並びに当該当選人に係る候補者届出政党の名称、その選挙における各候補者の得票総数その他選挙の次第を、当該都道府県の選挙管理委員会に報告しなければならない。
2 前項の規定による報告があつたときは、都道府県の選挙管理委員会は、直ちに当選人には当選の旨を、候補者届出政党には当選人の住所及び氏名を告知し、かつ、当選人の住所及び氏名並びに当該当選人に係る候補者届出政党の名称を告示しなければならない。
3 衆議院議員の選挙において、小選挙区選出議員の選挙と比例代表選出議員の選挙を同時に行つた場合においては、第一項の報告を受けた都道府県の選挙管理委員会は、直ちに当該当選人の住所、氏名及び得票数並びに当該当選人に係る候補者届出政党の名称、その選挙における各候補者の得票総数その他選挙の次第を、中央選挙管理会に報告しなければならない。
4 前項の規定による報告があつたときは、中央選挙管理会は、直ちに当該当選人の住所、氏名及び得票数並びに当該当選人に係る候補者届出政党の名称、その選挙における各候補者の得票総数その他選挙の次第を、その選挙区を包括する衆議院(比例代表選出)議員の選挙区ごとに、当該衆議院(比例代表選出)議員の選挙の選挙長に通知しなければならない。
解説:
公職選挙法 第百一条の二(衆議院比例代表選出議員の選挙における当選人の数及び当選人の決定の場合の報告、告知及び告示)
原文:
第百一条の二 衆議院(比例代表選出)議員の選挙において、衆議院名簿届出政党等に係る当選人の数及び当選人が定まつたときは、選挙長は、直ちに衆議院名簿届出政党等に係る得票数、当選人の数並びに当選人の住所及び氏名その他選挙の次第を、中央選挙管理会に報告しなければならない。
2 前項の規定による報告があつたときは、中央選挙管理会は、直ちに衆議院名簿届出政党等には得票数、当選人の数並びに当選人の住所及び氏名を、当選人には当選の旨を告知し、かつ、衆議院名簿届出政党等に係る得票数、当選人の数並びに当選人の住所及び氏名を告示しなければならない。
3 第九十七条の二又は第百十二条第二項の場合においては、前二項中「得票数、当選人の数並びに当選人」とあるのは、「当選人」とする。
解説:
公職選挙法 第百一条の二の二(参議院比例代表選出議員の選挙における当選人の数及び当選人となるべき順位並びに当選人の決定の場合の報告、告知及び告示)
原文:
第百一条の二の二 参議院(比例代表選出)議員の選挙において、参議院名簿届出政党等に係る当選人の数及び当選人となるべき順位並びに当選人が定まつたときは、選挙長は、直ちに参議院名簿届出政党等に係る得票数(当該参議院名簿届出政党等に係る各参議院名簿登載者の得票数を含むものをいう。次項において同じ。)、当選人の数、当選人となるべき順位並びに当選人の住所及び氏名並びに各参議院名簿登載者の得票数その他選挙の次第を、中央選挙管理会に報告しなければならない。
2 前項の規定による報告があつたときは、中央選挙管理会は、直ちに参議院名簿届出政党等には当該参議院名簿届出政党等に係る得票数、当選人の数並びに当選人の住所及び氏名を、当選人には当選の旨を告知し、かつ、参議院名簿届出政党等に係る得票数、当選人の数並びに当選人の住所及び氏名を告示しなければならない。
3 第九十七条の二又は第百十二条第四項において準用する同条第二項の場合においては、第一項中「得票数(当該参議院名簿届出政党等に係る各参議院名簿登載者の得票数を含むものをいう。次項において同じ。)、当選人の数、当選人となるべき順位並びに当選人の住所及び氏名並びに各参議院名簿登載者の得票数」とあるのは「当選人の住所及び氏名」と、前項中「当該参議院名簿届出政党等に係る得票数、当選人の数並びに当選人」とあるのは「当選人」と、「かつ、参議院名簿届出政党等に係る得票数、当選人の数並びに当選人」とあるのは「かつ、参議院名簿届出政党等に係る当選人」とする。
解説:
公職選挙法 第百一条の三(衆議院議員又は参議院比例代表選出議員の選挙以外の選挙における当選人決定の場合の報告、告知及び告示)
原文:
第百一条の三 衆議院議員又は参議院(比例代表選出)議員の選挙以外の選挙において、当選人が定まつたときは、選挙長は、直ちに当選人の住所、氏名及び得票数、その選挙における各公職の候補者の得票総数その他選挙の次第を、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(参議院合同選挙区選挙については、当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会)に報告しなければならない。
2 前項の規定による報告があつたときは、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(参議院合同選挙区選挙については、当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会)は、直ちに当選人に当選の旨を告知し、かつ、当選人の住所及び氏名を告示しなければならない。
解説:
公職選挙法 第百二条(当選等の効力の発生)
原文:
第百二条 当選人の当選の効力(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙にあつては、当選人の数の決定の効力を含む。)は、第百一条第二項、第百一条の二第二項、第百一条の二の二第二項又は前条第二項の規定による告示があつた日から、生ずるものとする。
解説:
公職選挙法 第百三条(当選人が兼職禁止の職にある場合等の特例)
原文:
第百三条 当選人で、法律の定めるところにより当該選挙に係る議員又は長と兼ねることができない職にある者が、第百一条第二項、第百一条の二第二項、第百一条の二の二第二項又は第百一条の三第二項の規定により当選の告知を受けたときは、その告知を受けた日にその職を辞したものとみなす。
2 第九十六条、第九十七条、第九十七条の二又は第百十二条の規定により当選人と定められた者で、法律の定めるところにより当該選挙に係る議員又は長と兼ねることができない職にあるものが第百一条第二項、第百一条の二第二項、第百一条の二の二第二項又は第百一条の三第二項の規定により当選の告知を受けたときは、前項の規定にかかわらず、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙については中央選挙管理会、参議院合同選挙区選挙については当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会)に対し、その告知を受けた日から五日以内にその職を辞した旨の届出をしないときは、その当選を失う。
3 前項の場合において、同項に規定する公務員がその退職の申出をしたときは、当該公務員の退職に関する法令の規定にかかわらず、その申出の日に当該公務員たることを辞したものとみなす。
4 一の選挙につき第九十六条、第九十七条、第九十七条の二又は第百十二条の規定により当選人と定められた者が、他の選挙につき第八十六条第一項から第三項まで若しくは第八項の規定による届出のあつたものであるとき、第八十六条の二第一項若しくは第九項の規定による届出に係る衆議院名簿登載者であるとき、第八十六条の三第一項若しくは同条第二項において準用する第八十六条の二第九項の規定による届出に係る参議院名簿登載者であるとき又は第八十六条の四第一項、第二項、第五項、第六項若しくは第八項の規定による届出のあつたものであるときは、第九十一条又は第一項の規定にかかわらず、第百一条第二項、第百一条の二第二項、第百一条の二の二第二項又は第百一条の三第二項の規定により一の選挙の当選の告知を受けた日から五日以内にその選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙については中央選挙管理会、参議院合同選挙区選挙については当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会)にその当選を辞する旨の届出をしないときは、他の選挙について、その公職の候補者に係る候補者の届出が取り下げられ若しくはその公職の候補者たることを辞したものとみなし、若しくはその公職の候補者たる衆議院名簿登載者若しくは参議院名簿登載者でなくなり、又はその当選を失う。
解説:
公職選挙法 第百四条(請負等をやめない場合の地方公共団体の議会の議員又は長の当選人の失格)
原文:
第百四条 地方公共団体の議会の議員又は長の選挙における当選人で、当該地方公共団体に対し、地方自治法第九十二条の二又は第百四十二条に規定する関係を有する者は、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会に対し、第百一条の三第二項の規定による当選の告知を受けた日から五日以内に同法第九十二条の二又は第百四十二条に規定する関係を有しなくなつた旨の届出をしないときは、その当選を失う。
解説:
公職選挙法 第百五条(当選証書の付与)
原文:
第百五条 第百三条第二項及び第四項並びに前条に規定する場合を除くほか、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙については中央選挙管理会、参議院合同選挙区選挙については当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会)は、第百二条の規定により当選人の当選の効力が生じたときは、直ちに当該当選人に当選証書を付与しなければならない。
2 第百三条第二項及び第四項並びに前条の規定により当選を失わなかつた当選人については、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙については中央選挙管理会、参議院合同選挙区選挙については当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会)は、第百三条第二項及び第四項並びに前条に規定する届出があつたときは、直ちに当該当選人に当選証書を付与しなければならない。
解説:
公職選挙法 第百六条(当選人がない場合等の報告及び告示)
原文:
第百六条 当選人がないとき又は当選人がその選挙における議員の定数に達しないときは、選挙長は、直ちにその旨を当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙については中央選挙管理会、参議院合同選挙区選挙については当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会)に報告しなければならない。
2 前項の規定による報告があつたときは、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙については中央選挙管理会、参議院合同選挙区選挙については当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会)は、直ちにその旨を告示しなければならない。
解説:
公職選挙法 第百七条(選挙及び当選の無効の場合の告示)
原文:
第百七条 第十五章の規定による争訟の結果選挙若しくは当選が無効となつたとき若しくは第二百十条第一項の規定による訴訟が提起されなかつたこと、当該訴訟についての訴えを却下し若しくは訴状を却下する裁判が確定したこと若しくは当該訴訟が取り下げられたことにより当選が無効となつたとき又は第二百五十一条の規定により当選が無効となつたときは、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙については中央選挙管理会、参議院合同選挙区選挙については当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会)は、直ちにその旨を告示しなければならない。
解説:
第十五章の規定による争訟の結果、選挙または当選が無効となった場合や、第210条第1項の規定による訴訟が提起されなかった場合、当該訴訟についての訴えを却下し、または訴状を却下する裁判が確定した場合や、当該訴訟が取り下げられたことにより当選が無効となった場合、または第251条の規定により当選が無効となった場合に、選挙管理委員会は直ちにその旨を告示しなければなりません。
公職選挙法 第百八条(当選等に関する報告)
原文:
第百八条 前三条の場合においては、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙については中央選挙管理会、参議院合同選挙区選挙については当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会)は、次の区分により、直ちにその旨を報告しなければならない。
一 衆議院議員、参議院議員又は都道府県知事の選挙にあつては総務大臣に
二 都道府県の議会の議員の選挙にあつては都道府県知事に
三 市町村長の選挙にあつては都道府県知事及び都道府県の選挙管理委員会に
四 市町村の議会の議員の選挙にあつては都道府県知事、都道府県の選挙管理委員会及び市町村長に
2 総務大臣は、前項の規定により衆議院議員又は参議院議員の選挙につき第百五条の規定により当選証書を付与した旨の報告を受けたときは、直ちにその旨並びに当選人の住所及び氏名を内閣総理大臣に報告し、内閣総理大臣は、直ちにこれをそれぞれ衆議院議長又は参議院議長に報告しなければならない。
解説:
第十一章 特別選挙
公職選挙法 第109条(衆議院小選挙区選出議員、参議院選挙区選出議員又は地方公共団体の長の再選挙)
原文:
第百九条 衆議院(小選挙区選出)議員、参議院(選挙区選出)議員(在任期間を同じくするものをいう。)又は地方公共団体の長の選挙について次の各号に掲げる事由のいずれかが生じた場合においては、第九十六条、第九十七条又は第九十八条の規定により当選人を定めることができるときを除くほか、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(参議院合同選挙区選挙については、当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会)は、選挙の期日を告示し、再選挙を行わせなければならない。ただし、同一人に関し、次に掲げるその他の事由により又は第百十三条若しくは第百十四条の規定により選挙の期日を告示したときは、この限りでない。
一 当選人がないとき又は当選人がその選挙における議員の定数に達しないとき。
二 当選人が死亡者であるとき。
三 当選人が第九十九条、第百三条第二項若しくは第四項又は第百四条の規定により当選を失つたとき。
四 第二百二条、第二百三条、第二百四条、第二百六条、第二百七条又は第二百八条の規定による異議の申出、審査の申立て又は訴訟の結果当選人がなくなり又は当選人がその選挙における議員の定数に達しなくなつたとき。
五 第二百十条若しくは第二百十一条の規定による訴訟の結果、当選人の当選が無効となつたとき又は第二百十条第一項の規定による訴訟が提起されなかつたこと、当該訴訟についての訴えを却下し若しくは訴状を却下する裁判が確定したこと若しくは当該訴訟が取り下げられたことにより当選人の当選が無効となつたとき。
六 第二百五十一条の規定により当選人の当選が無効となつたとき。
解説:
この条文では、選挙の結果に問題が生じた場合や、当選者がいなくなった場合に公平性を保つために再選挙が行われることを規定しています。これにより、適切な代表者が選出される仕組みが確保されています。
公職選挙法 第110条(衆議院比例代表選出議員、参議院比例代表選出議員又は地方公共団体の議会の議員の再選挙)
原文:
第百十条 衆議院(比例代表選出)議員、参議院(比例代表選出)議員(在任期間を同じくするものをいう。)若しくは地方公共団体の議会の議員の選挙について前条各号に掲げる事由のいずれかが生じた場合又は衆議院(比例代表選出)議員若しくは参議院(比例代表選出)議員(在任期間を同じくするものをいう。)の選挙について第九十九条の二第一項(同条第五項(同条第六項において準用する場合を含む。)又は第六項において準用する場合を含む。)の規定により当選人が当選を失つた場合において、第九十六条、第九十七条、第九十七条の二又は第九十八条の規定により当選人を定めることができるときを除くほか、当該選挙の当選人の不足数が次の各号に該当するに至つたときは、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙については、中央選挙管理会)は、前条の規定の例により、再選挙を行わせなければならない。
一 衆議院(比例代表選出)議員の場合には、第百十三条第一項にいうその議員の欠員の数と通じて当該選挙区における議員の定数の四分の一を超えるに至つたとき。
二 参議院(比例代表選出)議員(在任期間を同じくするものをいう。)の場合には、第百十三条第一項にいうその議員の欠員の数と通じて通常選挙における議員の定数の四分の一を超えるに至つたとき。
三 都道府県の議会の議員の場合には、同一選挙区において第百十三条第一項にいうその議員の欠員の数と通じて二人以上に達したとき。ただし、議員の定数が一人である選挙区においては一人に達したとき。
四 市町村の議会の議員の場合には、第百十三条第一項にいうその議員の欠員の数と通じて当該選挙区における議員の定数(選挙区がないときは、議員の定数)の六分の一を超えるに至つたとき。
2 衆議院(比例代表選出)議員又は参議院(比例代表選出)議員(在任期間を同じくするものをいう。)の選挙について、第二百四条又は第二百八条の規定による訴訟の結果その全部又は一部が無効となつたときは、中央選挙管理会は、前条の規定の例により、再選挙を行わせなければならない。
3 地方公共団体の議会の議員の選挙について、第二百二条、第二百三条、第二百六条又は第二百七条の規定による異議の申出、審査の申立て又は訴訟の結果その全部又は一部が無効となつたことにより当選人がなくなり又は当選人がその選挙における議員の定数に達しなくなつたときは、第一項の規定にかかわらず、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会は、前条の規定の例により、再選挙を行わせなければならない。
4 参議院(比例代表選出)議員(在任期間を同じくするものをいう。)又は地方公共団体の議会の議員の選挙におけるその当選人の不足数が第一項各号に該当しなくても、次の各号の区分による選挙が行われるときは、同項の規定にかかわらず、その選挙と同時に再選挙を行う。ただし、第一項に規定する事由が次の各号の区分による選挙の期日の告示があつた後に(市町村の議会の議員の選挙については、当該市町村の他の選挙の期日の告示の日前十日以内に)生じたものであるときは、この限りでない。
一 参議院(比例代表選出)議員の場合には、在任期間を異にする比例代表選出議員の選挙が行われるとき。
二 地方公共団体の議会の議員の場合には、当該選挙区(選挙区がないときはその区域)において同一の地方公共団体の他の選挙が行われるとき。
5 前項の再選挙の期日は、同項各号の区分により行われる選挙の期日による。
6 第四項第二号の同一の地方公共団体の他の選挙が地方公共団体の長の任期満了によるものであるときは、同項の規定により同時に行われるべき地方公共団体の議会の議員の再選挙に対する第三十四条第二項本文の規定の適用については、同項本文中「これを行うべき事由が生じた場合」とあるのは、「当該地方公共団体の長の任期が満了することとなる場合」とする。
解説:
この条文では、比例代表選出議員や地方議会議員における議席の欠員が発生した場合の再選挙の条件や手続きを規定しており、議会の運営が適切に行われるように再選挙を行う仕組みが整備されています。
公職選挙法 第111条(議員又は長の欠けた場合等の通知)
原文:
第百十一条 衆議院議員、参議院議員若しくは地方公共団体の議会の議員に欠員を生じた場合又は地方公共団体の長が欠け若しくはその退職の申立てがあつた場合においては、次の区分により、その旨を通知しなければならない。
一 衆議院(小選挙区選出)議員及び参議院(選挙区選出)議員については、国会法第百十条の規定によりその欠員を生じた旨の通知があつた日から五日以内に、内閣総理大臣は総務大臣に通知し、総務大臣は都道府県知事を経て都道府県の選挙管理委員会(参議院合同選挙区選挙により選出された参議院選挙区選出議員については、合同選挙区都道府県の知事を経て参議院合同選挙区選挙管理委員会)に
二 衆議院(比例代表選出)議員及び参議院(比例代表選出)議員については、国会法第百十条の規定によりその欠員を生じた旨の通知があつた日から五日以内に、内閣総理大臣は総務大臣に通知し、総務大臣は中央選挙管理会に
三 地方公共団体の議会の議員については、その欠員を生じた日から五日以内に、その地方公共団体の議会の議長から当該都道府県又は市町村の選挙管理委員会に
四 地方公共団体の長については、その欠けた場合には欠けた日から五日以内にその職務を代理する者から、その退職の申立てがあつた場合には申立ての日から五日以内に地方公共団体の議会の議長から、当該都道府県又は市町村の選挙管理委員会に
2 前項の通知を受けた選挙管理委員会、参議院合同選挙区選挙管理委員会又は中央選挙管理会は、次条の規定の適用があると認めるときは、議員が欠員となつた旨又は長が欠け若しくはその退職の申立てがあつた旨を、直ちに当該選挙長に通知しなければならない。
3 地方自治法第九十条第三項又は第九十一条第三項の規定により地方公共団体の議会の議員の定数を増加した場合においては、当該条例施行の日から五日以内にその地方公共団体の議会の議長から当該都道府県又は市町村の選挙管理委員会にその旨を通知しなければならない。
解説:
この規定は、欠員が発生した際に迅速かつ適切に通知し、次の選挙などの必要な手続きを行うためのフレームワークを提供しています。
公職選挙法 第112条(議員又は長の欠けた場合等の繰上補充)
原文:
第百十二条 衆議院(小選挙区選出)議員の欠員が生じた場合において、第九十五条第二項の規定の適用を受けた得票者で当選人とならなかつたものがあるときは、選挙会を開き、その者の中から当選人を定めなければならない。
2 衆議院(比例代表選出)議員の欠員が生じた場合において、当該議員に係る衆議院名簿の衆議院名簿登載者で当選人とならなかつたものがあるときは、選挙会を開き、その者の中から、その衆議院名簿における当選人となるべき順位に従い、当選人を定めなければならない。
3 第九十五条の二第五項及び第六項の規定は、前項の場合について準用する。
4 第二項の規定は、参議院(比例代表選出)議員の欠員が生じた場合について準用する。この場合において、同項中「衆議院名簿の衆議院名簿登載者」とあるのは「参議院名簿の参議院名簿登載者」と、「その衆議院名簿」とあるのは「その参議院名簿に係る参議院名簿登載者の間」と読み替えるものとする。
5 参議院(選挙区選出)議員又は地方公共団体の議会の議員の欠員が、当該議員の選挙の期日から三箇月以内に生じた場合において第九十五条第一項ただし書の規定による得票者で当選人とならなかつたものがあるとき又は当該議員の選挙の期日から三箇月経過後に生じた場合において同条第二項の規定の適用を受けた得票者で当選人とならなかつたものがあるときは、選挙会を開き、その者の中から当選人を定めなければならない。
6 地方公共団体の長が欠け又はその退職の申立があつた場合において、第九十五条第二項の規定の適用を受けた得票者で当選人とならなかつたものがあるときは、選挙会を開き、その者の中から当選人を定めなければならない。
7 第九十八条の規定は、前各項の場合について準用する。
8 選挙長は、前条第二項の通知を受けた日から二十日以内に、選挙会を開き、当選人を定めなければならない。
解説:
この条文では、欠員が生じた場合の補充方法を定め、選挙結果に基づく公平な対応が求められています。
公職選挙法 第113条(補欠選挙及び増員選挙)
原文:
第百十三条 衆議院議員、参議院議員(在任期間を同じくするものをいう。)又は地方公共団体の議会の議員の欠員につき、第百十一条第一項第一号から第三号までの規定による通知を受けた場合において、前条第一項から第五項まで、第七項又は第八項の規定により、当選人を定めることができるときを除くほか、その議員の欠員の数が次の各号に該当するに至つたときは、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙については中央選挙管理会、参議院合同選挙区選挙については当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会)は、選挙の期日を告示し、補欠選挙を行わせなければならない。ただし、同一人に関し、第百九条又は第百十条の規定により選挙の期日を告示したときは、この限りでない。
一 衆議院(小選挙区選出)議員の場合には、一人に達したとき。
二 衆議院(比例代表選出)議員の場合には、第百十条第一項にいうその当選人の不足数と通じて当該選挙区における議員の定数の四分の一を超えるに至つたとき。
三 参議院(比例代表選出)議員(在任期間を同じくするものをいう。)の場合には、第百十条第一項にいうその当選人の不足数と通じて通常選挙における議員の定数の四分の一を超えるに至つたとき。
四 参議院(選挙区選出)議員(在任期間を同じくするものをいう。)の場合には、通常選挙における当該選挙区の議員の定数の四分の一を超えるに至つたとき。
五 都道府県の議会の議員の場合には、同一選挙区において第百十条第一項にいうその当選人の不足数と通じて二人以上に達したとき。ただし、議員の定数が一人である選挙区においては一人に達したとき。
六 市町村の議会の議員の場合には、第百十条第一項にいうその当選人の不足数と通じて当該選挙区における議員の定数(選挙区がないときは、議員の定数)の六分の一を超えるに至つたとき。
解説:
この条文では、欠員が生じた場合や、議員の定数が増加した場合の選挙手続きを定めており、議会運営が滞りなく行われるようにするための仕組みが整備されています。
公職選挙法 第113条 第2項(増員選挙)
原文:
2 第百十一条第三項の規定による通知を受けた場合においては、当該都道府県又は市町村の選挙管理委員会は、選挙の期日を告示し、増員選挙を行わせなければならない。
解説:
この条文は、議員の定数が増えた場合において、適切に議席を補充するための増員選挙を迅速に行うための手続きを定めています。
公職選挙法 第113条 第3項(補欠選挙の同時実施)
原文:
3 参議院議員(在任期間を同じくするものをいう。)又は地方公共団体の議会の議員の欠員の数が第一項各号に該当しなくても、次の各号の区分による選挙が行われるときは、同項本文の規定にかかわらず、その選挙と同時に補欠選挙を行う。ただし、次の各号の区分による選挙の期日の告示があつた後に(市町村の議会の議員の選挙については、当該市町村の他の選挙の期日の告示の日前十日以内に)当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(参議院比例代表選出議員の選挙については中央選挙管理会、参議院合同選挙区選挙については当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会)が第百十一条第一項第一号から第三号までの規定による通知を受けたときは、この限りでない。
一 参議院(比例代表選出)議員の場合には、在任期間を異にする比例代表選出議員の選挙が行われるとき。
二 参議院(選挙区選出)議員の場合には、当該選挙区において在任期間を同じくする選挙区選出議員の再選挙又は在任期間を異にする選挙区選出議員の選挙が行われるとき。
三 地方公共団体の議会の議員の場合には、当該選挙区(選挙区がないときは、その区域)において同一の地方公共団体の他の選挙が行われるとき。
解説:
この条文により、効率的な選挙運営が可能となり、選挙管理委員会が補欠選挙を適時に実施できる仕組みが整っています。
公職選挙法 第113条 第4項・第5項(補欠選挙の期日と準用)
原文:
4 前項の補欠選挙の期日は、同項各号の区分により行われる選挙の期日による。
5 第百十条第六項の規定は、第三項第三号の規定による地方公共団体の議会の議員の補欠選挙について準用する。
解説:
これにより、補欠選挙は他の選挙と同時に行われることで効率的に実施され、地方議会でも同様の手続きが適用されることが確保されています。
公職選挙法 第114条(長が欠けた場合及び退職の申立てがあつた場合の選挙)
原文:
第百十四条 地方公共団体の長が欠けるに至り又はその退職の申立てがあつたことにつき、第百十一条第一項第四号の規定による通知を受けた場合において、第百十二条第六項から第八項までの規定により当選人を定めることができるときを除くほか、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会は、選挙の期日を告示し、選挙を行わせなければならない。ただし、同一人に関し、第百九条の規定により選挙の期日を告示したときは、この限りでない。
解説:
この条文により、地方公共団体の長に欠員が生じた際に適切な選挙が迅速に行われるように規定されています。これにより、自治体の運営が滞ることなく継続される仕組みが確保されています。
公職選挙法 第115条(合併選挙及び在任期間を異にする議員の選挙の場合の当選人)
原文:
次の各号に掲げる選挙を各号の区分ごとに同時に行う場合においては、一の選挙(参議院議員の場合には比例代表選出議員又は選挙区選出議員の選挙ごとに)をもつて合併して行う。
一 参議院議員の場合には、その通常選挙、再選挙又は補欠選挙
二 地方公共団体の議会の議員の場合には、同一の地方公共団体についてのその再選挙、補欠選挙又は増員選挙
解説:
この規定は、選挙の効率を高め、同時に複数の選挙を行う際の混乱を防ぐために設けられています。選挙管理委員会は、これに基づいて選挙を合理的に進行させることが可能です。
公職選挙法 第115条第2項(在任期間を異にする参議院比例代表選出議員の選挙の合併)
原文:
2 在任期間を異にする参議院(比例代表選出)議員について選挙を合併して行つた場合においては、各参議院名簿届出政党等に係る当選人の数のうち、第九十五条の三第一項及び第二項中「当該選挙において選挙すべき議員の数」とあるのは、「当該選挙において選挙すべき在任期間の長い議員の数」としてこれらの規定を適用した場合における各参議院名簿届出政党等に係る当選人の数を、各参議院名簿届出政党等に係る在任期間の長い議員の選挙の当選人の数とする。
解説:
この規定により、在任期間の長い議員を優先的に選出するため、議会の安定性を確保しながら、選挙の公平性が保たれるようになっています。
公職選挙法 第115条第3項(比例代表選出議員の選挙合併とくじによる当選人の決定)
原文:
3 在任期間を異にする参議院(比例代表選出)議員について選挙を合併して行つた場合において、第百条第三項の規定の適用があるときは、くじにより、各参議院名簿届出政党等に係る在任期間の長い議員の選挙の当選人の数及び各参議院名簿(第九十五条の三第四項に規定する参議院名簿届出政党等の届出に係るものを除く。)における当選人となるべき順位を定める。
解説:
この規定により、選挙結果が僅差となった場合でも、くじ引きで公平に当選者を決定することが可能となり、公平な選挙手続きが保証されます。
公職選挙法 第115条第4項(比例代表選出議員の名簿順の優先決定)
原文:
4 前項に規定する場合において、第九十五条の三第四項に規定する参議院名簿届出政党等の届出に係る各参議院名簿においては、第八十六条の三第一項後段の規定により優先的に当選人となるべき候補者としてその氏名及び当選人となるべき順位が参議院名簿に記載されている者である参議院名簿登載者の当選人となるべき順位は、その他の参議院名簿登載者の当選人となるべき順位より上位とし、当該その他の参議院名簿登載者の間における当選人となるべき順位は、くじにより定める。
解説:
この条文により、比例代表選出の参議院議員選挙において、政党の名簿に記載された候補者の優先順位が公平に決定されるよう規定されています。特定の候補者が優先される場合でも、残りの候補者はくじ引きで順位を決定し、選挙が透明に行われる仕組みが保証されています。
公職選挙法 第115条第5項(在任期間を異にする参議院比例代表選出議員の当選人決定)
原文:
5 在任期間を異にする参議院(比例代表選出)議員について選挙を合併して行つた場合においては、各参議院名簿届出政党等の届出に係る参議院名簿登載者のうち、それらの者の間における当選人となるべき順位に従い、第二項又は第三項の規定により定められた当該参議院名簿届出政党等に係る在任期間の長い議員の選挙の当選人の数に相当する数の参議院名簿登載者を、在任期間の長い議員の選挙の当選人とする。
解説:
この規定により、在任期間が異なる議員の選挙を公平に合併しつつ、名簿順に従って適切な当選者を選ぶ手続きが確保されています。
公職選挙法 第115条第6項(在任期間を異にする参議院選挙区選出議員の当選人決定)
原文:
6 在任期間を異にする参議院(選挙区選出)議員について、選挙を合併して行つた場合においては、第九十五条第一項ただし書の規定による得票者の中で得票の最も多い者から、順次に在任期間の長い議員の選挙の当選人を定めなければならない。
解説:
この規定により、選挙区選出議員の選挙では、得票数の多い候補者が優先的に在任期間の長い議員として選ばれ、選挙の公平性が保たれる仕組みが確立されています。
公職選挙法 第115条第7項(選挙区選出議員の選挙合併時におけるくじ引きでの当選者決定)
原文:
7 在任期間を異にする参議院(選挙区選出)議員について選挙を合併して行つた場合において、第百条第四項の規定の適用があるときは、くじにより、いずれの候補者をもつて在任期間の長い議員の選挙の当選人とするかを定めなければならない。
解説:
この規定により、選挙結果が僅差で決定できない場合でも、くじ引きを用いることで公平に当選者を決定する手続きが確立されています。
公職選挙法 第115条第8項(第100条第9項の準用)
原文:
8 第百条第九項の規定は、第三項の場合における在任期間の長い議員の選挙の当選人の決定及び前項の場合に、準用する。
解説:
この規定により、くじ引きなどの手段で当選者を決定する際に、既存の手続きが適用されるため、公正な結果が得られる仕組みが整えられています。
公職選挙法 第115条第9項(繰上補充における在任期間の短い議員の当選者決定)
原文:
9 在任期間を異にする参議院議員について選挙を合併して行つた場合において、在任期間の長い議員の選挙の当選人又はその議員について、第九十七条、第九十七条の二又は第百十二条に規定する事由が生じたため、これらの規定により繰上補充を行う場合においては、比例代表選出議員の選挙にあつては当該議員又は当選人に係る参議院名簿の参議院名簿登載者で在任期間の短い議員又はその当選人があるときはその者の中から第五項に規定する参議院名簿登載者の間における当選人となるべき順位に従い、選挙区選出議員の選挙にあつてはその選挙において選挙された在任期間の短い議員又はその当選人があるときはその者の中から、当選人を定めるものとする。
解説:
この規定により、参議院議員の在任期間に関わる繰上補充が、公正かつ確実に行われるように設けられています。比例代表選出議員では名簿の順位、選挙区選出議員では選挙結果に基づき、次の当選者が適切に決定される仕組みが整えられています。
公職選挙法 第116条(議員又は当選人がすべてない場合の一般選挙)
原文:
第百十六条 地方公共団体の議会の議員又はその選挙における当選人について、第百十条(選挙の一部無効に係る部分を除く。)又は第百十三条に規定する事由が生じた場合において、議員又は当選人がすべてないとき又はすべてなくなつたときは、これらの規定にかかわらず、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会は、選挙の期日を告示し、一般選挙を行わせなければならない。
解説:
この条文により、地方議会が議員不足のために機能不全に陥ることを防ぎ、迅速に議会を再編成するための仕組みが確保されています。
公職選挙法 第117条(設置選挙)
原文:
第百十七条 地方公共団体が設置された場合においては、都道府県又は市町村の選挙管理委員会は、当該地方公共団体の議会の議員及び長についてそれぞれ選挙の期日を告示し、一般選挙及び長の選挙を行わせなければならない。
解説:
この規定は、地方公共団体の設置後、速やかに選挙を実施してその議会や長を選出し、自治体の運営が開始できるようにする仕組みを提供しています。
公職選挙法 第118条
原文:削除
第十二章 選挙を同時に行うための特例
公職選挙法 第119条(同時に行う選挙の範囲)
原文:
第百十九条 都道府県の議会の議員の選挙及び都道府県知事の選挙又は市町村の議会の議員の選挙及び市町村長の選挙は、それぞれ同時に行うことができる。
2 都道府県の選挙管理委員会は、次条第一項若しくは第二項の規定による届出又は第百八条第一項第三号若しくは第四号の規定による報告に基づき、当該市町村の選挙(市町村の議会の議員及び長の選挙をいう。以下この章において同じ。)を都道府県の選挙(都道府県の議会の議員及び長の選挙をいう。以下この章において同じ。)と同時に行わせることができる。
3 前項の規定による選挙の期日は、都道府県の選挙管理委員会において、告示しなければならない。
解説:
この規定により、地方自治体の選挙を効率的に行うことができ、選挙実施のための手続きがスムーズに進行できる仕組みが整えられています。
公職選挙法 第120条(選挙を同時に行うかどうかの決定手続)
原文:
第百二十条 市町村の選挙管理委員会は、市町村の議会の議員又は長の選挙を行う場合においては、任期満了に因る選挙については任期満了の日前六十日までに、任期満了以外の事由に因る選挙については第百八条第一項第三号又は第四号の規定により報告する場合を除く外選挙を行うべき事由を生じた日から三日以内に、その旨を都道府県の選挙管理委員会に届け出なければならない。
2 市町村の選挙管理委員会は、第三十四条の二第二項(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定による告示をした場合においては、直ちにその旨を都道府県の選挙管理委員会に届け出なければならない。
3 都道府県の選挙管理委員会は、第一項若しくは前項の規定による届出又は第百八条第一項第三号若しくは第四号の規定による報告のあつた日から三日以内に、当該市町村の選挙を都道府県の選挙と同時に行うかどうかを、当該市町村の選挙管理委員会に通知しなければならない。
解説:
この規定により、選挙が同時に行われるかどうかが迅速かつ適切に決定され、選挙の手続きが円滑に進むようになっています。
公職選挙法 第121条(選挙の同時施行決定までの市町村の選挙の施行停止)
原文:
第百二十一条 市町村の選挙は、前条第三項の規定による通知があるまでの間は、行うことができない。ただし、同項の期間内に通知がないときは、この限りでない。
解説:
この規定により、選挙の調整が行われ、選挙管理委員会が選挙の同時施行について適切な判断を下すまで選挙が実施されない仕組みが設けられています。
公職選挙法 第122条(投票及び開票の順序)
原文:
第百二十二条 第百十九条の規定により同時に選挙を行う場合における投票及び開票の順序は、同条第一項の規定による場合にあつては当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会が、同条第二項の規定による場合にあつては都道府県の選挙管理委員会が定める。
解説:
この規定により、同時選挙の際に投票や開票の順序を適切に管理し、公正で円滑な選挙運営を確保するための手続きが整えられています。
公職選挙法 第123条(投票、開票及び選挙会に関する規定の適用)
原文:
第百二十三条 第百十九条第一項又は第二項の規定により同時に選挙を行う場合においては、第三十六条及び第六十二条に規定するものを除く外、投票及び開票に関する規定は、各選挙に通じて適用する。第百十九条第一項の規定により同時に選挙を行う場合において、選挙会の区域が同一であるときは、第七十六条に規定するものを除く外、選挙会に関する規定についても、また同様とする。
2 前項の場合において必要な事項は、政令で定める。
解説:
この規定により、同時選挙の際の手続きが統一され、円滑な運営が保証されるようになっています。必要な詳細な事項については政令によって定められることが規定されています。
公職選挙法 第124条(繰上投票)
原文:
第百二十四条 都道府県の選挙と市町村の選挙を同時に行う場合においては、第五十六条の規定による投票の期日は、同条の規定にかかわらず、都道府県の選挙管理委員会が定める。
解説:
この規定により、都道府県と市町村の選挙が効率的に実施されるために、投票日を柔軟に設定できるようになっています。
公職選挙法 第125条(繰延投票)
原文:
第百二十五条 都道府県の選挙と市町村の選挙を同時に行う場合において、第五十七条第一項に規定する事由を生じたときは、都道府県の選挙管理委員会は、同項の規定の例により更に投票を行わせなければならない。
2 前項の場合においては、市町村の選挙管理委員会は、都道府県の選挙の選挙長を経て都道府県の選挙管理委員会にその旨を届け出なければならない。
解説:
この規定により、都道府県と市町村の選挙が同時に行われる際に、投票が延期される場合の手続きが統一され、迅速かつ適切な対応が求められます。
公職選挙法 第126条(長の候補者が一人となつた場合の選挙期日の延期)
原文:
第百二十六条 都道府県の選挙と市町村長の選挙を同時に行う場合において市町村長の選挙について第八十六条の四第七項に規定する事由が生じたときは、市町村の選挙管理委員会は、直ちにその旨を都道府県の選挙管理委員会に報告しなければならない。
2 都道府県知事の選挙と市町村長の選挙を同時に行う場合において、都道府県知事の選挙について第八十六条の四第七項に規定する事由が生じ、かつ、市町村長の選挙についてもまた前項の規定による報告により同条第七項に規定する事由が生じたことを知つたときは、都道府県の選挙管理委員会は、選挙の期日を延期し、その報告のあつた日(二以上の報告があつたときは、最後の報告のあつた日)から七日以内に、選挙を同時に行わせなければならない。この場合においては、その期日は、少なくとも五日前に告示しなければならない。
3 第百十九条第一項又は第二項の規定により同時に選挙を行う場合において、地方公共団体の長の選挙について第八十六条の四第七項に規定する事由が生じた場合に関し必要な事項は、前項の規定に該当する場合を除くほか、政令で定める。
解説:
この規定により、長の候補者が一人になった場合でも、選挙の延期や同時選挙が円滑に行われるための手続きが整えられています。
公職選挙法 第127条(無投票当選)
原文:
第百二十七条 第百十九条第一項又は第二項の規定により同時に選挙を行う場合において、第百条第四項に規定する事由が生じたときは、当該選挙に係る投票は、行わない。
解説:
この規定により、無投票当選が発生した場合の選挙手続きを簡略化し、無駄な投票を避ける仕組みが確立されています。
公職選挙法 第128条
原文:削除
第十三章 選挙運動
公職選挙法 第129条(選挙運動の期間)
原文:
第百二十九条 選挙運動は、各選挙につき、それぞれ第八十六条第一項から第三項まで若しくは第八項の規定による候補者の届出、第八十六条の二第一項の規定による衆議院名簿の届出、第八十六条の三第一項の規定による参議院名簿の届出(同条第二項において準用する第八十六条の二第九項の規定による届出に係る候補者については、当該届出)又は第八十六条の四第一項、第二項、第五項、第六項若しくは第八項の規定による公職の候補者の届出のあつた日から当該選挙の期日の前日まででなければ、することができない。
解説:
この規定により、選挙運動の期間が明確に定められ、候補者や政党が公平に選挙運動を行えるようなルールが確立されています。
公職選挙法 第130条(選挙事務所の設置及び届出)
原文:
第百三十条 選挙事務所は、次に掲げるものでなければ、設置することができない。
一 衆議院(小選挙区選出)議員の選挙にあつては、公職の候補者又はその推薦届出者(推薦届出者が数人あるときは、その代表者。以下この条、次条及び第百三十九条において同じ。)及び候補者届出政党
二 衆議院(比例代表選出)議員の選挙にあつては、衆議院名簿届出政党等
三 参議院(比例代表選出)議員の選挙にあつては、参議院名簿届出政党等及び公職の候補者たる参議院名簿登載者(第八十六条の三第一項後段の規定により優先的に当選人となるべき候補者としてその氏名及び当選人となるべき順位が参議院名簿に記載されている者を除く。)
四 前三号に掲げる選挙以外の選挙にあつては、公職の候補者又はその推薦届出者
解説:
この規定により、選挙事務所の設置が適正に行われ、選挙活動がスムーズに進むための枠組みが整えられています。
公職選挙法 第130条第2項(選挙事務所の設置及び届出)
原文:
2 前項各号に掲げるものは、選挙事務所を設置したときは、直ちにその旨を、市町村の選挙以外の選挙については当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙については中央選挙管理会及び当該選挙事務所が設置された都道府県の選挙管理委員会、参議院合同選挙区選挙については当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会及び当該選挙事務所が設置された都道府県の選挙管理委員会)及び当該選挙事務所が設置された市町村の選挙管理委員会に、市町村の選挙については当該市町村の選挙管理委員会に届け出なければならない。選挙事務所に異動があつたときも、また同様とする。
解説:
この規定により、選挙事務所の設置や変更が迅速かつ適正に報告され、選挙活動の透明性が確保されています。
公職選挙法 第131条(選挙事務所の数)
原文:
第百三十一条 前条第一項各号に掲げるものが設置する選挙事務所は、次の区分による数を超えることができない。ただし、政令で定めるところにより、交通困難等の状況のある区域においては、第一号の選挙事務所にあつては三箇所まで、第四号の選挙事務所にあつては五箇所(参議院合同選挙区選挙における選挙事務所にあつては、十箇所)まで、それぞれ設置することができる。
一 衆議院(小選挙区選出)議員の選挙における選挙事務所は、候補者又はその推薦届出者が設置するものにあつてはその候補者一人につき一箇所、候補者届出政党が設置するものにあつてはその候補者届出政党が届け出た候補者に係る選挙区ごとに一箇所
二 衆議院(比例代表選出)議員の選挙における衆議院名簿届出政党等の選挙事務所は、その衆議院名簿届出政党等が届け出た衆議院名簿に係る選挙区の区域内の都道府県ごとに、一箇所
三 参議院(比例代表選出)議員の選挙における選挙事務所は、参議院名簿届出政党等が設置するものにあつては都道府県ごとに一箇所、公職の候補者たる参議院名簿登載者が設置するものにあつてはその参議院名簿登載者一人につき一箇所
四 参議院(選挙区選出)議員又は都道府県知事の選挙における選挙事務所は、その公職の候補者一人につき、一箇所(参議院合同選挙区選挙における選挙事務所にあつては、二箇所)
五 地方公共団体の議会の議員又は市町村長の選挙における選挙事務所は、その公職の候補者一人につき、一箇所
解説:
この規定により、選挙活動の公平性が保たれるため、選挙事務所の数が適正に管理されています。
公職選挙法 第131条第2項(選挙事務所の移動制限)
原文:
2 前項各号の選挙事務所については、当該選挙事務所を設置したものは、当該選挙事務所ごとに、一日につき一回を超えて、これを移動(廃止に伴う設置を含む。)することができない。
解説:
この規定により、選挙事務所が不適切に何度も移動されることを防ぎ、選挙活動が秩序ある形で進行するよう管理されています。
公職選挙法 第131条第3項(選挙事務所の標札掲示)
原文:
3 第一項第一号から第四号までの選挙事務所については、当該選挙事務所を設置したものは、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙については中央選挙管理会、参議院合同選挙区選挙については当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会)が交付する標札を、選挙事務所を表示するために、その入口に掲示しなければならない。
解説:
この規定により、選挙事務所が適切に認識され、公正な選挙活動が行われるための透明性が確保されています。
公職選挙法 第132条(選挙当日の選挙事務所の制限)
原文:
第百三十二条 選挙事務所は、第百二十九条の規定にかかわらず、選挙の当日においても、当該投票所を設けた場所の入口から三百メートル以外の区域に限り、設置することができる。
解説:
この規定により、選挙当日の公正な投票環境を維持しながらも、選挙活動のための事務所設置が認められる範囲が明確にされています。
公職選挙法 第133条(休憩所等の禁止)
原文:
第百三十三条 休憩所その他これに類似する設備は、選挙運動のため設けることができない。
解説:
この規定により、選挙運動の公平性と透明性を保つため、特定の場所に集まりやすくする設備の設置が防止されています。
公職選挙法 第134条(選挙事務所の閉鎖命令)
原文:
第百三十四条 第百三十条第一項、第百三十一条第三項又は第百三十二条の規定に違反して選挙事務所の設置があると認めるときは、市町村の選挙以外の選挙については当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙については中央選挙管理会又は当該選挙事務所が設置された都道府県の選挙管理委員会、参議院合同選挙区選挙については当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会又は当該選挙事務所が設置された都道府県の選挙管理委員会)又は当該選挙事務所が設置された市町村の選挙管理委員会、市町村の選挙については当該市町村の選挙管理委員会は、直ちにその選挙事務所の閉鎖を命じなければならない。
2 第百三十一条第一項の規定による定数を超えて選挙事務所の設置があると認めるときは、その超過した数の選挙事務所についても、また前項と同様とする。
解説:
この規定により、違反となる選挙事務所の設置を防ぎ、選挙活動の透明性と公平性が確保されています。
公職選挙法 第135条(選挙事務関係者の選挙運動の禁止)
原文:
第百三十五条 第八十八条に掲げる者は、在職中、その関係区域内において、選挙運動をすることができない。
2 不在者投票管理者は、不在者投票に関し、その者の業務上の地位を利用して選挙運動をすることができない。
解説:
この規定は、選挙運営に携わる者が不当な影響力を行使することを防ぎ、選挙の公正性を保つための重要なルールです。
公職選挙法 第136条(特定公務員の選挙運動の禁止)
原文:
第百三十六条 次に掲げる者は、在職中、選挙運動をすることができない。
一 中央選挙管理会の委員及び中央選挙管理会の庶務に従事する総務省の職員、参議院合同選挙区選挙管理委員会の職員並びに選挙管理委員会の委員及び職員
二 裁判官
三 検察官
四 会計検査官
五 公安委員会の委員
六 警察官
七 収税官吏及び徴税の吏員
解説:
この規定は、公正な選挙を維持し、特定の公務員がその職務を利用して不適切な選挙運動を行わないようにするための措置です。
公職選挙法 第136条の2(公務員等の地位利用による選挙運動の禁止)
原文:
第百三十六条の二 次の各号のいずれかに該当する者は、その地位を利用して選挙運動をすることができない。
一 国若しくは地方公共団体の公務員又は行政執行法人若しくは特定地方独立行政法人の役員若しくは職員
二 沖縄振興開発金融公庫の役員又は職員(以下「公庫の役職員」という。)
2 前項各号に掲げる者が公職の候補者若しくは公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。)を推薦し、支持し、若しくはこれに反対する目的をもつてする次の各号に掲げる行為又は公職の候補者若しくは公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。)である同項各号に掲げる者が公職の候補者として推薦され、若しくは支持される目的をもつてする次の各号に掲げる行為は、同項に規定する禁止行為に該当するものとみなす。
解説:
この規定により、公務員などがその地位を不当に利用して選挙運動に関与することを防ぎ、公正な選挙を確保するための重要なルールが定められています。
公職選挙法 第137条(教育者の地位利用の選挙運動の禁止)
原文:
第百三十七条 教育者(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に規定する学校及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)に規定する幼保連携型認定こども園の長及び教員をいう。)は、学校の児童、生徒及び学生に対する教育上の地位を利用して選挙運動をすることができない。
解説:
この規定により、教育現場における政治的中立性が守られ、教育者がその影響力を利用して選挙活動に関与することを防止しています。
公職選挙法 第137条の2(年齢満十八年未満の者の選挙運動の禁止)
原文:
第百三十七条の二 年齢満十八年未満の者は、選挙運動をすることができない。
2 何人も、年齢満十八年未満の者を使用して選挙運動をすることができない。ただし、選挙運動のための労務に使用する場合は、この限りでない。
解説:
この規定は、18歳未満の者が政治的影響を受けず、公正な選挙活動が行われるように設けられたものです。
公職選挙法 第137条の3(選挙権及び被選挙権を有しない者の選挙運動の禁止)
原文:
第百三十七条の三 第二百五十二条又は政治資金規正法第二十八条の規定により選挙権及び被選挙権を有しない者は、選挙運動をすることができない。
解説:
この規定により、選挙権や被選挙権を持たない者が選挙に影響を与えることを防ぎ、公正な選挙活動が行われるようにしています。
公職選挙法 第138条(戸別訪問)
原文:
第百三十八条 何人も、選挙に関し、投票を得若しくは得しめ又は得しめない目的をもつて戸別訪問をすることができない。
2 いかなる方法をもつてするを問わず、選挙運動のため、戸別に、演説会の開催若しくは演説を行うことについて告知をする行為又は特定の候補者の氏名若しくは政党その他の政治団体の名称を言いあるく行為は、前項に規定する禁止行為に該当するものとみなす。
解説:
この規定により、選挙運動が特定の家庭に直接的な圧力をかけないようにし、選挙の公平性が保たれることを目指しています。
公職選挙法 第138条の2(署名運動の禁止)
原文:
第百三十八条の二 何人も、選挙に関し、投票を得若しくは得しめ又は得しめない目的をもつて選挙人に対し署名運動をすることができない。
解説:
この規定により、署名運動が選挙活動に不正な影響を与えることを防止し、選挙の透明性と公平性が確保されています。
公職選挙法 第138条の3(人気投票の公表の禁止)
原文:
第百三十八条の三 何人も、選挙に関し、公職に就くべき者(衆議院比例代表選出議員の選挙にあつては政党その他の政治団体に係る公職に就くべき者又はその数、参議院比例代表選出議員の選挙にあつては政党その他の政治団体に係る公職に就くべき者又はその数若しくは公職に就くべき順位)を予想する人気投票の経過又は結果を公表してはならない。
解説:
この規定により、選挙の公正性が保たれ、人気投票が選挙運動に悪影響を与えることを防止しています。
公職選挙法 第139条(飲食物の提供の禁止)
原文:
第百三十九条 何人も、選挙運動に関し、いかなる名義をもつてするを問わず、飲食物(湯茶及びこれに伴い通常用いられる程度の菓子を除く。)を提供することができない。ただし、衆議院(比例代表選出)議員の選挙以外の選挙において、選挙運動(衆議院小選挙区選出議員の選挙において候補者届出政党が行うもの及び参議院比例代表選出議員の選挙において参議院名簿届出政党等が行うものを除く。以下この条において同じ。)に従事する者及び選挙運動のために使用する労務者に対し、公職の候補者(参議院比例代表選出議員の選挙における候補者たる参議院名簿登載者で第八十六条の三第一項後段の規定により優先的に当選人となるべき候補者としてその氏名及び当選人となるべき順位が参議院名簿に記載されているものを除く。)一人について、当該選挙の選挙運動の期間中、政令で定める弁当料の額の範囲内で、かつ、両者を通じて十五人分(四十五食分)(第百三十一条第一項の規定により公職の候補者又はその推薦届出者が設置することができる選挙事務所の数が一を超える場合においては、その一を増すごとにこれに六人分(十八食分)を加えたもの)に、当該選挙につき選挙の期日の公示又は告示のあつた日からその選挙の期日の前日までの期間の日数を乗じて得た数分を超えない範囲内で、選挙事務所において食事するために提供する弁当(選挙運動に従事する者及び選挙運動のために使用する労務者が携行するために提供された弁当を含む。)については、この限りでない。
解説:
この規定により、公平な選挙運動を維持し、飲食物提供による選挙活動への影響を防ぐことを目的としています。
公職選挙法 第140条(気勢を張る行為の禁止)
原文:
第百四十条 何人も、選挙運動のため、自動車を連ね又は隊伍を組んで往来する等によつて気勢を張る行為をすることができない。
解説:
この規定は、選挙運動が公正で秩序ある形で行われることを目的としています。
公職選挙法 第140条の2(連呼行為の禁止)
原文:
第百四十条の二 何人も、選挙運動のため、連呼行為をすることができない。ただし、演説会場及び街頭演説(演説を含む。)の場所においてする場合並びに午前八時から午後八時までの間に限り、次条の規定により選挙運動のために使用される自動車又は船舶の上においてする場合は、この限りでない。
2 前項ただし書の規定により選挙運動のための連呼行為をする者は、学校(学校教育法第一条に規定する学校及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第二条第七項に規定する幼保連携型認定こども園をいう。以下同じ。)及び病院、診療所その他の療養施設の周辺においては、静穏を保持するように努めなければならない。
解説:
この規定は、選挙運動の過度な騒音や混乱を防ぎ、公共の秩序を保つことを目的としています。
公職選挙法 第141条(自動車、船舶及び拡声機の使用)
原文:
第百四十一条 次の各号に掲げる選挙においては、主として選挙運動のために使用される自動車(道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第二条第一項第九号に規定する自動車をいう。以下同じ。)又は船舶及び拡声機(携帯用のものを含む。以下同じ。)は、公職の候補者(参議院比例代表選出議員の選挙における候補者たる参議院名簿登載者で第八十六条の三第一項後段の規定により優先的に当選人となるべき候補者としてその氏名及び当選人となるべき順位が参議院名簿に記載されているものを除く。次条において同じ。)一人について当該各号に定めるもののほかは、使用することができない。ただし、拡声機については、個人演説会(演説を含む。)の開催中、その会場において別に一そろいを使用することを妨げるものではない。
一 衆議院(小選挙区選出)議員、参議院(選挙区選出)議員並びに地方公共団体の議会の議員及び長の選挙 自動車(その構造上宣伝を主たる目的とするものを除く。以下この号及び次号において同じ。)一台又は船舶一隻及び拡声機一そろい(参議院合同選挙区選挙にあつては、自動車二台又は船舶二隻(両者を使用する場合は通じて二)及び拡声機二そろい)
二 参議院(比例代表選出)議員の選挙 自動車二台又は船舶二隻(両者を使用する場合は通じて二)及び拡声機二そろい
解説:
この規定により、選挙運動が過度に目立たないようにし、公正で秩序ある選挙活動を確保しています。
公職選挙法 第141条 第2項(自動車、船舶及び拡声機の追加使用の条件)
原文:
第百四十一条第2項 前項の規定にかかわらず、衆議院(小選挙区選出)議員の選挙においては、候補者届出政党は、その届け出た候補者に係る選挙区を包括する都道府県ごとに、自動車一台又は船舶一隻及び拡声機一そろいを、当該都道府県における当該候補者届出政党の届出候補者(当該都道府県の区域内の選挙区において当該候補者届出政党が届け出た候補者をいう。以下同じ。)の数が三人を超える場合においては、その超える数が十人を増すごとにこれらに加え自動車一台又は船舶一隻及び拡声機一そろいを、主として選挙運動のために使用することができる。ただし、拡声機については、政党演説会(演説を含む。)の開催中、その会場において別に一そろいを使用することを妨げるものではない。
解説:
この規定は、候補者の数に応じて選挙運動に必要な設備の追加を認めることで、選挙運動の効率化を図ることを目的としています。
公職選挙法 第141条 第3項(比例代表選出議員選挙での自動車、船舶及び拡声機の追加使用)
原文:
第百四十一条第3項 衆議院(比例代表選出)議員の選挙においては、衆議院名簿届出政党等は、その届け出た衆議院名簿に係る選挙区ごとに、自動車一台又は船舶一隻及び拡声機一そろいを、当該選挙区における当該衆議院名簿届出政党等の衆議院名簿登載者の数が五人を超える場合においては、その超える数が十人を増すごとにこれらに加え自動車一台又は船舶一隻及び拡声機一そろいを、主として選挙運動のために使用することができる。ただし、拡声機については、政党等演説会(演説を含む。)の開催中、その会場において別に一そろいを使用することを妨げるものではない。
解説:
この規定は、比例代表選挙における公平な選挙運動を支援し、複数の候補者を擁する政党が適切に運動できるようにしています。
公職選挙法 第141条 第4項(比例代表選出議員選挙における自動車、船舶及び拡声機の使用制限)
原文:
第百四十一条第4項 衆議院(比例代表選出)議員の選挙においては、主として選挙運動のために使用される自動車、船舶及び拡声機は、前項の規定により衆議院名簿届出政党等が使用するもののほかは、使用することができない。
解説:
この制限は、選挙運動における公正さと秩序を保ち、必要以上に多くの機材を使って不公平な影響を与えないようにするためのものです。
公職選挙法 第141条 第5項(選挙運動のために使用される自動車、船舶及び拡声機の表示)
原文:
第百四十一条第5項 第一項本文、第二項本文又は第三項本文の規定により選挙運動のために使用される自動車、船舶又は拡声機には、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙については中央選挙管理会、参議院合同選挙区選挙については当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会)の定めるところの表示(自動車と船舶については、両者に通用する表示)をしなければならない。
解説:
この表示義務は、選挙運動に関する透明性を確保し、選挙活動が正当に行われていることを示すために重要な役割を果たします。
公職選挙法 第141条 第6項(選挙運動に使用される自動車の種類)
原文:
第百四十一条第6項 第一項の自動車は、町村の議会の議員又は長の選挙以外の選挙にあつては政令で定める乗用の自動車に、町村の議会の議員又は長の選挙にあつては政令で定める乗用の自動車又は小型貨物自動車(道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第三条の規定に基づき定められた小型自動車に該当する貨物自動車をいう。)に限るものとする。
解説:
この規定により、選挙運動に使用される車両が適切に規制され、使用可能な車両の種類が選挙の規模や対象によって異なることが明示されています。
公職選挙法 第141条 第7項(小選挙区及び比例代表選挙における自動車の無料使用)
原文:
第百四十一条第7項 衆議院(小選挙区選出)議員又は参議院議員の選挙においては、公職の候補者は、政令で定めるところにより、政令で定める額の範囲内で、第一項の自動車を無料で使用することができる。ただし、衆議院(小選挙区選出)議員又は参議院(選挙区選出)議員の選挙にあつては当該公職の候補者に係る供託物が第九十三条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定により国庫に帰属することとならない場合に、参議院(比例代表選出)議員の選挙にあつては当該公職の候補者たる参議院名簿登載者が当該参議院名簿登載者に係る参議院名簿届出政党等の第九十四条第三項第一号に掲げる数に相当する当選人となるべき順位までにある場合に限る。
解説:
この規定は、公職候補者が特定の条件を満たす場合、選挙運動において経済的な負担を軽減するための仕組みとなっています。
公職選挙法 第141条 第8項(地方公共団体の議員や長の選挙における自動車の無料使用)
原文:
第百四十一条第8項 地方公共団体の議会の議員又は長の選挙については、地方公共団体は、前項の規定(参議院比例代表選出議員の選挙に係る部分を除く。)に準じて、条例で定めるところにより、公職の候補者の第一項の自動車の使用について、無料とすることができる。
解説:
この規定により、地方公共団体は、候補者に対して選挙運動の一部の費用を軽減することができ、選挙運動が円滑に行えるよう支援する仕組みを整備することが可能です。