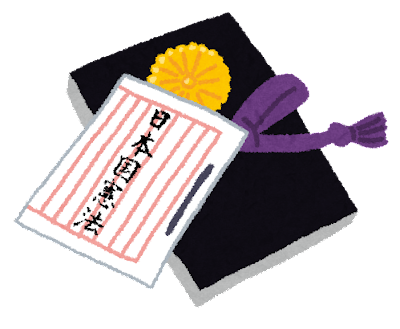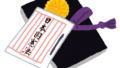昭和51年4月14日衆議院議員定員不均衡訴訟裁
この訴訟は、衆議院議員選挙において一人あたりの選挙区間での有権者数に著しい差があり、それが憲法が要求する投票価値の平等に反すると主張されたものです。人口変動を考慮しても合理的期間内に是正が行われなかったことが憲法違反とされました
衆議院議員定員不均衡訴訟では、選挙区の有権者数に大きなばらつきがあるため、一票の重みに不均等が生じているとして、選挙制度の見直しを求める訴えがなされます。最高裁判所は過去に、一票の価値の不均衡が憲法に反するとの判断を示し、選挙区割の是正を国に命じた事例があります。これは、「一人一票」の原則を守るため、定期的に選挙区の見直しが必要であることを示唆しています。
原告と被告の主張
- 原告の主張: 選挙区間での有権者数の差が憲法が要求する投票価値の平等に反し、違憲状態にあると主張しました。特に、是正が合理的期間内に行われなかった点を問題としました。
- 被告の主張: 裁判所の文書では直接被告の主張についての詳細は述べられていませんが、通常、国や選挙管理委員会などは、選挙制度や議員定数配分が憲法及び法律に基づいて適切に行われていると主張します。
争点
- 投票価値の不平等が憲法違反にあたるか。
- 定数配分規定全体が違憲となるか。
- 違憲となる場合、選挙自体が無効となるか。
裁判所の判断
- 投票価値の不平等について: 選挙区間での有権者数の不均衡が憲法上の選挙権の平等の要求に反するとして違憲と判断されました。
- 定数配分規定全体について: 定数配分規定は相互に有機的に関連し、全体として違憲の瑕疵を帯びると判断されました。
- 選挙自体の無効について: 事情判決の原理により、選挙を無効とはしないと判断されました。すなわち、違憲であっても既に行われた選挙の結果やそれに基づく法律等の効力は維持されることになりました。
判示事項
この判決では、以下の3点が判示されました:
- 憲法第14条1項、第15条1項・3項、第44条但し書は、国会両議院議員の選挙における選挙人の投票価値の平等を要求しています。
- 公職選挙法第13条、同法(昭和50年法律第63号による改正前のもの)別表第一及び附則7項から9項による選挙区及び議員定数の定めは、昭和47年12月10日の衆議院議員選挙時に全体として憲法に違反していました。
- 衆議院議員選挙が憲法に違反する公職選挙法の定めに基づいて行われたことにより違法な場合でも、選挙を無効とする判決をすることによって直ちに違憲状態が是正されるわけではないため、選挙を無効とする請求を棄却するとともに、選挙が違法である旨を主文で宣言すべきであるとしました。
裁判要旨
- 憲法は、国会両議院議員の選挙における選挙権の内容、すなわち各選挙人の投票の価値が平等であることを要求します。
- 具体的な選挙制度において、合理的に認められない投票価値の不平等が存在する場合、それは憲法違反となります。
- 選挙が憲法に違反している場合でも、選挙を無効とする判決を下すことによって直ちにその違憲状態が是正されるわけではないため、選挙を無効とする請求は棄却され、選挙が違法である旨が宣言されるべきです。
この判決は、選挙における一票の格差問題に関する重要な判断を示しており、選挙制度の公平性に関わる憲法解釈における基準を定めています。
主文(判決の結論)
- 原判決を変更し、上告人(控訴人)の請求を棄却する。
- しかし、1972年12月10日に行われた千葉県第一区の衆議院議員選挙は違法であると認定する。
- 訴訟費用は、全て被上告人(被控訴人)が負担する。
理由(判決の根拠)
- 選挙権の平等: 憲法は、選挙においてすべての国民の一票が等しい価値を持つべきだと要求しています。選挙権は、国民が国政に参加する基本的な権利であり、すべての国民に平等に保障されています。
- 投票価値の不平等の問題: 1972年の衆議院議員選挙では、公職選挙法に基づく選挙区と議員定数の決定により、投票価値に大きな不平等が生じていました。この不平等は合理的な根拠に基づかず、憲法に違反するとされました。
- 選挙の無効性に関する議論: 選挙の不平等は、選挙を無効とすべき十分な理由にはならず、原判決がこの点を誤って解釈したと批判されています。
選挙権の平等と選挙制度
- 選挙権は、議会制民主主義の根幹をなす基本的権利です。憲法は、選挙における各投票の価値が平等であることを要求しています。
- 投票価値の平等は、文字通りの数字的な一致を必要とするわけではありません。選挙制度の設計には多少の差異が生じる可能性がありますが、これは避けられないことです。
- 選挙制度は、国民の利害や意見が国政に反映されることを目指し、それぞれの国の事情に応じて決定されるものです。憲法は、投票価値の平等を選挙制度の唯一の基準としているわけではなく、選挙権の内容の平等も重要な考慮事項の一つです。
- 投票価値の不平等がある場合、それが合理的に認められる政策的目的に基づくものでなければならないとされています。
この判決は、選挙における一票の等価値という憲法上の原則に基づいて、選挙制度の合理性と公正性を検討し、選挙の不平等が憲法違反であることを認定しつつも、選挙の無効を直接的に命じることは避けるという法理を示しています。
衆議院議員選挙における議員定数配分規定の合憲性についての詳細な検討を含みます。簡単に説明すると以下のポイントに分けられます:
議員定数配分規定の目的と合憲性
- 衆議院議員選挙は、中選挙区単記投票制を採用しており、これは選挙人の多数意思の反映と少数意思の代表を確保する目的で設計されています。
- 選挙区と議員定数の配分には、選挙人数や人口数との比率の平等を基本的な基準としながらも、都道府県の役割や人口密度、交通事情など様々な要素を考慮する必要があります。
不平等が生じる原因と合憲性の評価
- 各選挙区の選挙人数と議員定数との比率には、必然的に差異が生じますが、この差異が著しい場合には選挙権の平等に関する憲法上の疑問が生じます。
- しかし、選挙区割りと議員定数の配分は、人口の変動を考慮し、合理的期間内に是正が行われるべきです。是正が行われない場合、憲法違反と判断されるべきです。
選挙の効力について
- ある選挙制度が憲法に違反しているとしても、その選挙を直ちに無効とする判断は、憲法の意図するところではなく、適切な解決策ではありません。
- 選挙が憲法に違反する法律に基づいて行われた場合、その選挙を無効とすることによって直ちに違憲状態が是正されるわけではないため、選挙自体を無効としない方が合理的です。選挙が違法であることを指摘することにとどめ、具体的な是正措置を求めるべきです。
簡単に言えば、議院議員選挙の議員定数配分が憲法に違反する可能性があることを認めつつも、そのような違反があるとしても、選挙自体を無効とすることは憲法の意図に反すると主張しています。選挙制度の設計には、多くの複雑な要素が関わっており、人口の変動などを考慮した合理的な期間内での是正が求められるとしています。
引用・参考元:https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=53255